かつて看護婦と呼ばれていた職業も「看護師」という名称に変わり、看護=女性のイメージは払拭されつつあります。男性看護師の割合も年々増加していますが、いまだに女性と比べると少ないのが現状です。
 ryanta73
ryanta73男性看護師はなぜ少ないのか。その理由と実態を、現役の男性看護師が徹底解説します。
本記事では、日本の男性看護師が少数に留まる5つの主な理由を明らかにし、実際の職場での経験や課題、そして活躍できる診療科についても詳しく解説。これから看護師を目指す男性や、すでに働いている男性看護師のキャリア戦略まで、現状の分析と将来の展望を交えてお届けします。
日本における男性看護師の現状と統計データ


国内の男性看護師について、具体的な統計データをもとに現状を分析していきます。
- 男性看護師の割合
- 国際比較でみる男性看護師の少なさ
- 看護師全体の需要と男性看護師の位置づけ
男性看護師の割合
厚生労働省「令和4年衛生行政報告例」によると、2022年現在、日本の看護師総数は約131万人です。そのうち男性看護師は約11万人で、全体の約8.6%に留まっています。



男性看護師は10人に1人もおらず、まだまだ女性社会と言わざるを得ません。
男性看護師の割合は、過去10年で徐々に増加していることがわかります。2012年には全体の約6.2%だった男性看護師は、2022年に約8.6%まで増加しました。しかし、この増加率を見ても、依然として女性が9割以上を占める状況です。
| 年度 | 看護師総数 | 男性看護師数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 約101万人 | 約6.3万人 | 6.2% |
| 2020年 | 約128万人 | 約10万人 | 8.1% |
| 2022年 | 約131万人 | 約11.2万人 | 8.6% |
この統計からも明らかなように、男性看護師の数自体は増加しているものの、看護師全体に占める割合の増加はゆるやかであり、まだまだ少数派であることがわかります。
国際比較でみる男性看護師の少なさ
日本の男性看護師の割合は、国際的に見ても非常に低い水準にあり、以下のような差が見られます。
| 国名 | 男性看護師の割合 |
|---|---|
| イギリス | 約11.5% |
| オーストラリア | 約11.4% |
| 台湾 | 約3.8% |
| 日本 | 約7.8% |
| スペイン | 約15.9% |
特に欧米諸国と比較すると、日本の男性看護師割合の低さが際立ちます。スペインでは男性看護師が約16%を占めており、日本の2倍以上の割合です。これは、文化的背景や職業に対する社会的イメージの違いが大きく影響していると考えられます。



逆に台湾では男性看護師の割合が3.8%と、かなり少ないです。しかし、さまざまな施策により年々増加傾向にあります。
看護師全体の需要と男性看護師の重要性
日本は超高齢社会を迎え、医療・介護人材の需要が急増しています。厚生労働省の推計によると、2025年には約200万人の看護師が必要とされていますが、現状の増加ペースでは約10〜20万人の看護師が不足すると予測されています。
この看護師不足という社会問題に対して、男性の看護師への参入は重要な解決策の一つとして期待されています。現在の日本の労働人口の約半数を男性が占めていることを考えると、看護職における男性割合の低さは大きな潜在的人材プールを活用できていないことを意味します。
男性看護師の需要が高まっている分野
- 救急医療
- 体力を必要とする場面や緊急時の対応
- 精神科医療
- 暴力行為のリスク管理が必要な場面
- 在宅医療
- 独居男性高齢者のケア
- 手術室
- 長時間の立ち仕事や重い機器の取り扱い
全国男性看護師会「男性看護師に関する調査結果報告書」によれば、男性看護師は特に救急部門や精神科での就業率が高く、これらの分野では男性看護師の専門性や特性が活かされていることがわかります。



私は手術室と精神科を経験しましたが、半数近くが男性看護師でした。特に精神科は男性の多さが顕著です。
男性患者に対するケアにおいても、男性看護師の存在は重要です。特に男性特有の疾患や、同性による身体的ケアを希望する患者にとって、男性看護師の存在は心理的な安心感につながります。
男性看護師は数の上では少数派ですが、医療現場における多様性や人材確保の観点から、その存在意義と重要性は徐々に認識されるようになっています。
男性看護師が少ない理由5選
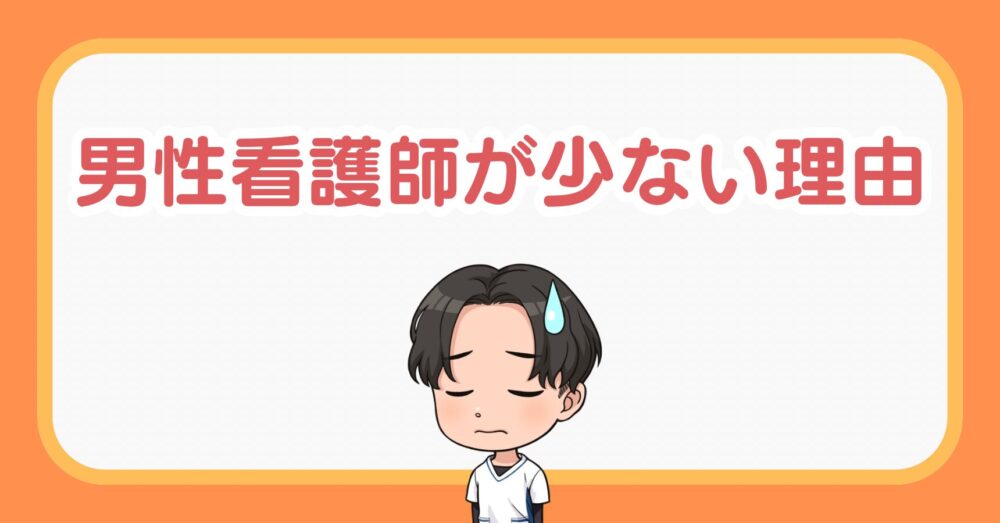
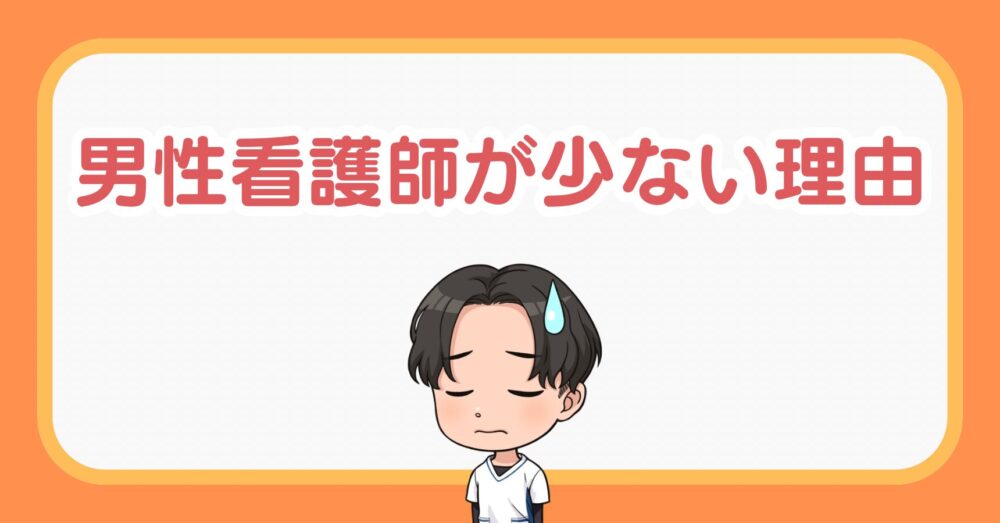
ここでは、なぜ男性看護師が少ないのか、5つの理由を解説します。
- まだまだ「看護師は女性の仕事」というイメージがある
- 一般男性の年収と比較すると低い
- 肉体的・精神的にハードな仕事
- 女性社会のなかで働く大変さ
- 前例が少なくキャリアプランを立てづらい
まだまだ「看護師は女性の仕事」というイメージがある
日本社会では長年、看護という職業は「女性の仕事」というイメージが根強く定着しています。この性別による職業への先入観は、若い男性が看護師を進路として検討する際の大きな障壁となっています。



「ナース」という言葉自体が女性を連想させる傾向があり、メディアでの看護師の描写も女性が中心です。
歴史的に見ても、近代看護の基礎を築いたのはフローレンス・ナイチンゲールであり、看護教育の初期から女性中心で発展してきました。この歴史的背景が、現代でも「看護=女性の仕事」という固定観念を強化しています。
しかし、全国男性看護師会では「看護に性別は関係ない」として、男性看護師の増加を促進するための情報発信を行っています。社会の意識改革には時間がかかりますが、徐々に変化の兆しも見えています。
一般男性の年収と比較すると低い
経済的な側面も、男性看護師が少ない大きな理由の一つです。看護師の給与水準は、一般的な男性の平均年収と比較すると低い傾向にあります。
| 職種 | 平均年収(概算) | 備考 |
|---|---|---|
| 男性看護師 | 約525万円 | 夜勤手当等含む |
| 男性会社員 | 約569万円 | 企業規模により差異あり |
国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」
現在も日本社会では、男性は「家庭を支える存在」という期待があり、結婚や家族形成を考えた場合に経済面での不安が職業選択に影響します。看護師の給与は夜勤手当などを含めると決して低くはありませんが、他の男性が多く就く専門職と比較すると見劣りする傾向があります。



看護師の給与は年々上昇傾向にあるものの、他の専門職(エンジニアや薬剤師など)と比べると依然として格差があります。
看護師はキャリアアップによる収入増加の幅が、他業種と比較して限定的な面もあります。特に男性にとって、長期的な経済計画を考えた際に不安要素となっています。
肉体的・精神的にハードな仕事
看護師という職業は、肉体的にも精神的にも負担が大きい仕事です。この労働環境の厳しさが、男性の参入を躊躇させる要因となっています。
肉体面での負担
- 24時間体制の交代制勤務による不規則な生活リズム
- 長時間の立ち仕事
- 患者の移乗介助 など
精神面での負担
- 命に関わる緊張感の中での業務継続
- 患者やその家族との深い関わりによる感情労働
- 医療ミスへの恐怖 など
人手不足による業務過多も深刻な問題です。一人当たりの担当患者数が多く、残業や休日出勤も珍しくありません。このような労働環境は、ワークライフバランスを重視する傾向にある現代の若者、特に男性にとって参入障壁となっています。



実際に、看護師の離職率は他業種と比較しても高く、男性看護師の場合は特に入職後3年以内の離職率が高いというデータもあります。
女性社会のなかで働く大変さ
看護の現場は圧倒的に女性が多い環境であり、その中で少数派として働く男性看護師特有の困難があります。
- コミュニケーションスタイルの違い
- 一般的に女性中心の職場では、細やかな気配りや感情的なコミュニケーションが重視される傾向があり、男性がこうした環境に適応するのに時間がかかることがあります。
- 力仕事を任せられる
- 男性看護師は「力仕事」を頼られることが多く、本来の業務以外の重労働(患者の移動や物品の運搬など)を期待されがちです。これにより本来の看護業務に集中できないケースもあります。
- 設備面での不便さ
- 更衣室やトイレといった施設面でも、男性への配慮が不足している医療機関もあります。古い病院では、男性看護師用の更衣室がなく、他部門の男性スタッフと共用したり、遠い場所に設置されていたりするケースもあります。



人間関係面では、少数派であるがゆえの孤立感や疎外感を感じることもあります。
前例が少なくキャリアプランを立てづらい
男性看護師にとって、ロールモデルとなる先輩や明確なキャリアパスが見えにくいことも大きな課題です。
看護師としてのキャリア形成において、同性の先輩の存在は非常に重要です。男性看護師の場合、身近にロールモデルとなる先輩が少なく、将来の自分のキャリアをイメージしづらい状況があります。特に、管理職になった男性看護師や専門分野で活躍する男性看護師の情報は限られています。
また、男性特有のライフイベント(結婚後の家計の担い手としての役割や育児参加など)と看護師としてのキャリアをどう両立させるかについての情報も不足しています。特に、男性看護師の育休取得事例や復帰後のキャリア形成については、参考となる事例が少ないのが現状です。



私が勤務している施設も、私以外に男性看護師は1人しかいません。将来の不確実性が、看護師として働いている男性の中長期的なキャリアプランニングを難しくしています。
現役男性看護師が語る職場での実態
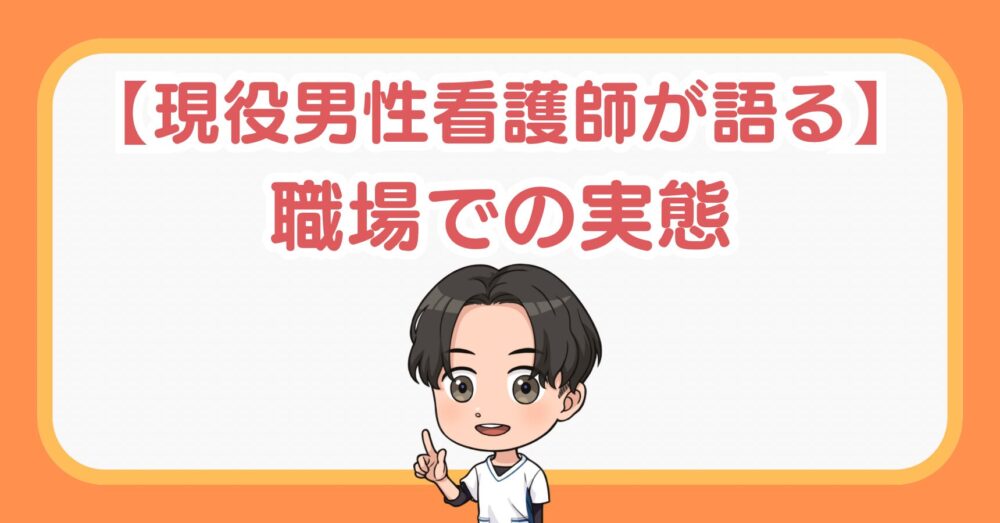
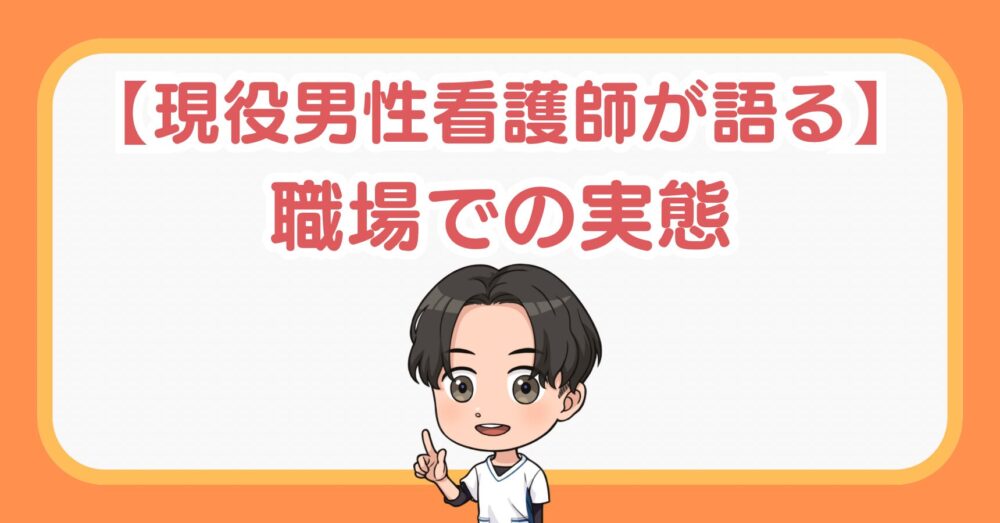
現役の男性看護師として働く私「ryanta73」が、実際の職場環境や日常業務での経験を詳しく紹介します。
- 男性看護師が日常的に感じる困難
- 患者や家族からの反応と対応
- 女性中心の職場環境での人間関係
男性看護師が日常的に感じる困難
男性看護師として日々の業務をこなしていくなかで、様々な困難に直面します。業務内容そのものだけでなく、職場環境や社会的認識に関わる問題も含まれます。
「男性なのになぜ看護師に?」と質問されることは本当に多いです。10年以上のキャリアがありますが、いまだにその質問は続いています。



細やかな配慮を求められる場面では、男性というだけで能力を疑問視された経験もあります。
処置の際、「男性だから雑そう」と先入観を持たれることも多いです。実際には性別と仕事の丁寧さには関連ありませんが、「女性の方が丁寧」というイメージは、私でさえも感じています。
| 困難の種類 | 具体的な事例 | 対処法 |
|---|---|---|
| 社会的認識 | 「男性なのに看護師」という偏見 | 患者への丁寧な説明と自己紹介 |
| 業務上の制限 | 女性患者のケアへの参加制限 | チーム内での役割分担の明確化 |
| キャリア形成 | ロールモデルの不足 | 外部の男性看護師ネットワークへの参加 |
| 職場環境 | 休憩室やロッカーの設備不足 | 職場への改善提案 |
男性看護師は、力仕事を頼られる一方で、繊細さが求められる業務では敬遠されるというジレンマも抱えています。



重い患者さんの移動や、暴れる患者さんの抑制は必ず呼ばれますが、細かい処置は「女性の方が上手」と言われるのは、男性看護師あるあるですね。
患者からの反応と対応策
男性看護師が直面する課題の一つに、患者や家族からの反応があります。初対面の患者には「男性の看護師さんですか?」と驚かれることも少なくありません。特に高齢の方は「看護婦さん」という言葉を使う人も多く、男性である私を見て戸惑うこともあります。
女性患者のケアにおいては、特に配慮が必要です。入浴介助や清拭など、直接身体に触れるケアでは「女性の看護師にお願いしたい」と言われることは日常的です。
一方で、男性患者からは男性看護師の存在を歓迎される場面もあります。精神科に勤務していた頃、男性特有の悩みや症状について、同性である私に打ち明けてくれる患者は多かったです。



「男の看護師さんで良かった」と言われると、とてもやりがいを感じます。
対応策としては、まず丁寧な自己紹介と説明を心がけること、患者の意向を尊重しながらも専門職としての役割をしっかり果たすことが重要です。患者の尊厳を守りながら、性別に関わらず質の高いケアを提供する姿勢が求められています。
女性中心の職場環境での人間関係
看護師という職業は、依然として女性が多数を占める環境です。男性看護師は、独特の人間関係の難しさに直面します。
現在の職場では20人以上の看護師がいますが、男性は私一人という状況がほとんどです。会話の話題についていけないことも多く、休憩時間が苦痛に感じることもあります。
女性とのコミュニケーションスタイルの違いもあります。女性同士の「暗黙の了解」や察し合いの文化に適応するのは難しいと感じることも多いです。



直接的なコミュニケーションを好む私としては、時々戸惑うことがあります。
コミュニケーションの違い
男女間のコミュニケーションスタイルの違いは、看護の現場でも顕著に表れます。一般的に、女性は共感的・感情的なコミュニケーションが多く見られる一方、男性看護師は事実や結論を重視する傾向があります。
申し送りやカンファレンスでは、女性の同僚は患者の感情面や細かい変化について詳しく共有する人が多いです。私は要点を簡潔に伝えようとするため、報告が淡白だと指摘を受けたこともあります。



女性特有の気配りや感情を細かく汲み取る性質には、看護師として正直うらやましさもあります。
チームワークと孤立感
女性が大多数を占める環境の中で、男性看護師は時として孤立感を抱くことも多いです。男性が少ないことで、時に「男性代表」として見られるプレッシャーがあります。失敗すれば「やっぱり男性は…」と一般化されやすいのも辛いところです。
男性看護師ならではの視点や役割を活かしてチームに貢献している例も少なくありません。私は職場で唯一の男性として、時に女性間の微妙な人間関係の調整役になることがあります。主任という立場上、職員同士のトラブルを処理する機会も多いですが、男性だからこそ中立的な立場で解決しやすいです。



女性中心の環境だからこそ、異なる視点や考え方を持つ私の意見が新鮮であり、重視されることもあります。
職場での人間関係構築にあたっては、性別の違いだけでなく個々の人間性や専門性を尊重し合う文化が重要です。
男性看護師が活躍できる診療科と領域
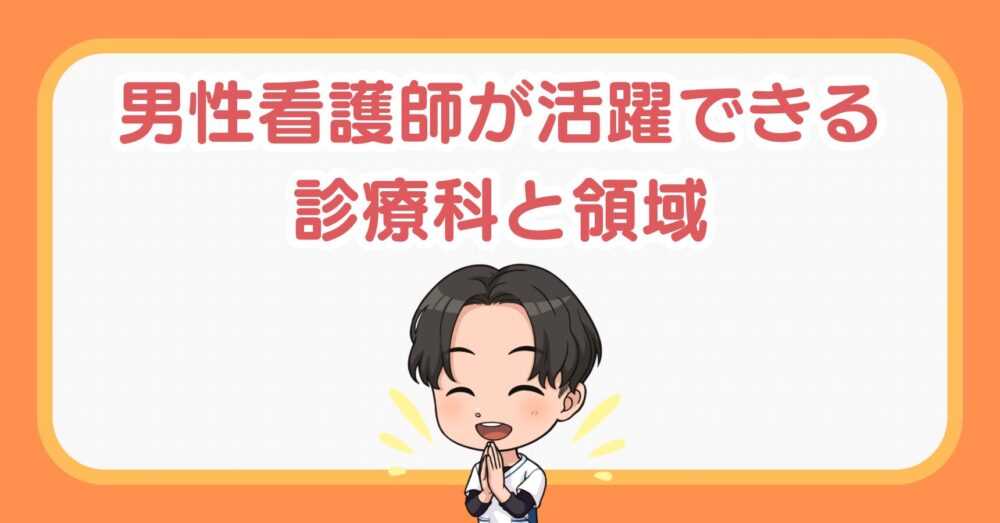
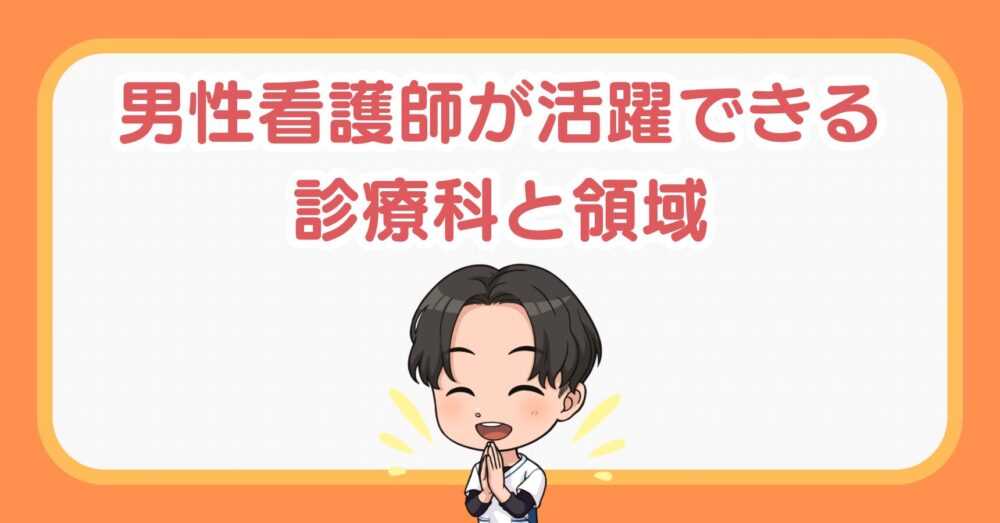
男性看護師が少ない看護業界ですが、実は男性の特性を活かして活躍できる診療科や領域が数多く存在します。ここでは、男性看護師が特に活躍しやすい診療科と、そのメリットについて詳しく解説します。
- 救急・ER
- 精神科
- 手術室
- 整形外科・リハビリテーション
- 管理職としてのキャリアパス



「男性看護師が輝ける職場へ転職したい!」そんな人には、転職エージェントへ相談する方法がオススメです。
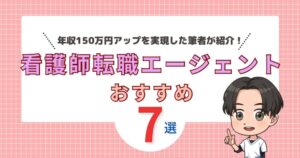
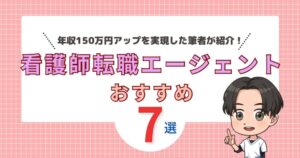
救急・ER
救急外来(ER)は、男性看護師の活躍が最も目立つ領域の一つです。救急現場では、緊急性の高い状況で冷静な判断力が求められるとともに、重症患者の移動や処置において体力が必要とされるケースが多くあります。
救急科で男性看護師が重宝される場面
- 意識不明患者や大柄な患者の移乗・体位変換
- 暴力的な傾向のある患者への対応
- 心肺蘇生法実施時の胸骨圧迫(長時間の体力が必要)
- 救急車からの患者搬入
救急領域では他の診療科と比較して男性看護師の割合が高い傾向にあります。



患者や家族としても、救急の現場に男性がいることで安心感を得られるメリットがあります。
精神科
精神科は、男性看護師の需要が高い代表的な診療科の一つです。精神科では患者の状態が急変し、興奮状態になることもあるため、身体的な制止が必要になる場面があります。
精神科での男性看護師の主な役割
- 興奮状態にある患者さんへの対応
- 暴力行為のリスク管理
- 男性患者のケアや相談対応
- 行動制限(身体拘束など)が必要な場面での支援
精神科では男性患者の割合も比較的高く、男性患者が同性のケアを希望するケースも少なくありません。特に統合失調症や双極性障害などの疾患では、男性患者が男性看護師に対して心を開きやすいという傾向もあります。



私が勤務していた精神科病院では、約半数が男性看護師でした。
手術室
手術室も男性看護師が活躍しやすい場所です。手術室では長時間の立ち仕事や重い機器の移動、患者の体位変換などが多く、体力的な面で男性看護師の貢献が期待されます。
手術室での男性看護師の役割
- 全身麻酔下の患者の移動・体位変換
- 重量のある医療機器のセッティング
- 長時間手術における器械出し業務
- 緊急時の迅速な対応
手術室の看護師は、外科医や麻酔科医との密接な連携が必要であり、コミュニケーション能力やストレス耐性が重要です。男性看護師は、緊迫した環境でも冷静さを保ちながら業務を遂行できる点が評価されています。



もちろん、女性ならではの観察力も大切です。私も手術室に配属された経験がありますが、男女ともにそれぞれの特性を活かせる分野だと感じました。
手術室勤務を経験した男性看護師は、専門性の高いスキルを身につけることができるため、キャリアアップにも有利です。
整形外科・リハビリテーション
整形外科やリハビリテーション科では、患者の移動や歩行訓練など、体力を必要とする場面が多く、男性看護師の体格や筋力が大きなアドバンテージとなります。
整形外科・リハビリテーション科での男性看護師の強み
- 脊椎疾患や大腿骨骨折などの患者の移乗介助
- 歩行訓練や関節可動域訓練のサポート
- 牽引装置や装具の装着補助
- ADL(日常生活動作)訓練の実施
高齢者が多い整形外科では、患者の身体を支えながらのケアが多く、男性看護師の身体的特性が活かせます。スポーツ外傷を扱う病院ではアスリートの患者も多く、男性患者とのコミュニケーションがスムーズに行える点も利点です。



中途半端な介助は、怪我を悪化させる原因になります。しっかりと体を支えられる男性の筋力は必要不可欠です。
管理職としてのキャリアパス
男性看護師は、臨床経験を積んだ後に管理職へとキャリアアップする道も開かれています。実際に、看護部長や副看護部長などの管理職に就く男性看護師も徐々に増えています。
管理職としての男性看護師の役割と特徴
- 看護部門の組織マネジメント
- 人員配置や勤務表作成などの労務管理
- 病院経営への参画
- 医療安全や感染対策の責任者
- 看護教育・人材育成の統括
男性看護師が管理職に就くメリットとして、多様な視点での組織運営が可能になり、女性中心の職場に新たな風を吹き込めることが挙げられます。



具体的なキャリアパスと経験年数の目安は、以下のとおりです。
| キャリアパス | 必要な経験年数(目安) | 必要なスキル・資格 |
|---|---|---|
| 主任看護師 | 5〜10年 | リーダーシップ、コミュニケーション能力 |
| 看護師長 | 10〜15年 | マネジメント能力、認定看護管理者研修 |
| 副看護部長 | 15〜20年 | 組織運営能力、認定看護管理者資格 |
| 看護部長 | 20年以上 | 経営戦略、人事管理、認定看護管理者資格 |
男性看護師にとって、管理職は単なるキャリアアップの道だけでなく、看護業界全体の改革や男性看護師の地位向上にも貢献できる重要な立場と言えます。
≫看護師が主任になると年収はいくら上がる?現役主任の筆者が明かす給与の実態
男性看護師のメリットと社会的価値
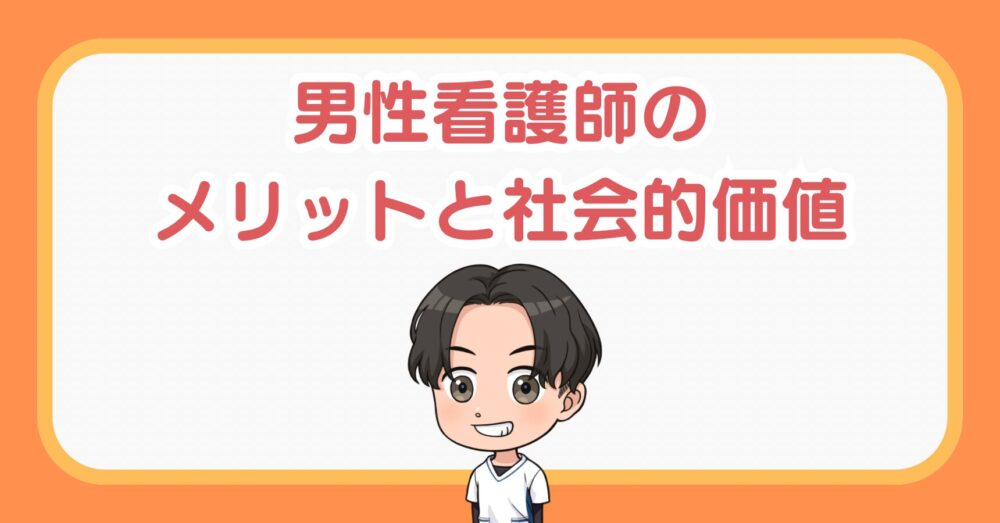
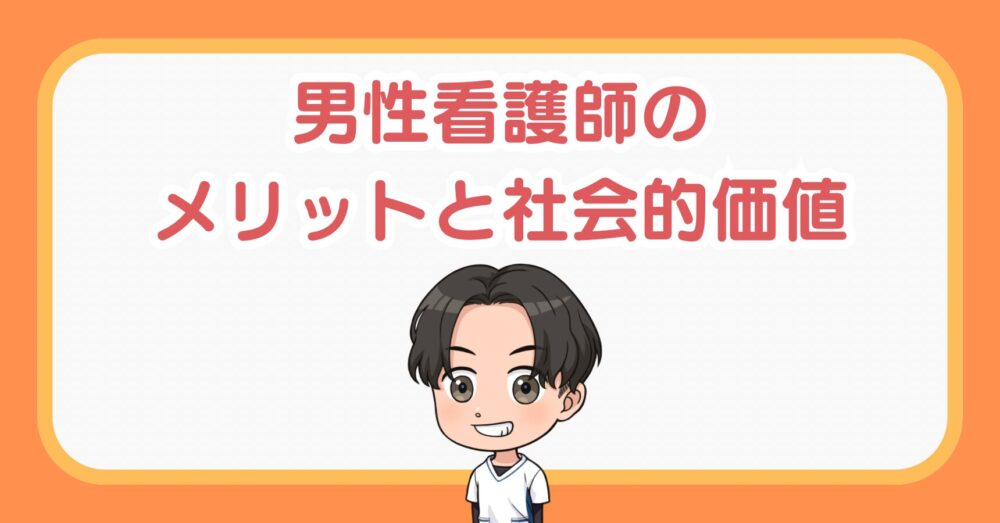
ここでは、男性看護師の存在が医療現場や社会全体にもたらす価値について詳しく解説します。
- 多様な視点がもたらす医療の質向上
- 男性患者のケアにおける心理的安心感
- 看護師不足解消への貢献
多様な視点がもたらす医療の質向上
男性看護師が増えることで、より柔軟で総合的な患者ケアが可能になります。例えば、以下のような点で男性看護師の視点が役立っています。
- 問題解決アプローチの多様化
- 男性特有の健康問題への理解と対応
- チーム内での異なる意見交換による意思決定の質向上
- 医療機器や物理的環境の改善提案
厚生労働省が推進する医療の質向上施策においても、多様な人材の確保は重要な要素として位置づけられています。
男性患者のケアにおける心理的安心感
特に男性患者にとって、同性からケアを受けることで心理的な安心感を得られるケースが多くあります。特に、以下のような場面で顕著です。
| ケアの種類 | 男性看護師が関わる意義 |
|---|---|
| 排泄ケア | 男性患者の羞恥心の軽減と心理的抵抗の減少 |
| 陰部洗浄 | 同性によるケアでの安心感提供 |
| 泌尿器科的処置 | 男性特有の身体的特徴への理解と適切な対応 |
| 男性特有の悩み相談 | 同性としての共感と理解に基づくサポート |



若い男性患者の場合、女性看護師によるケアに抵抗を感じるケースがあり、男性看護師が求められます。
精神科領域においても、暴力行為などの危険性がある患者への対応や、男性特有のメンタルヘルスの問題に対して、男性看護師の存在が治療効果を高める要因になります。
看護師不足解消への貢献
日本の医療現場では慢性的な看護師不足が問題です。厚生労働省の統計によれば、2025年には約10〜20万人の看護師が不足すると予測されています。この状況において、男性を積極的に活用することは、看護師不足解消への重要な手段です。
男性が看護師不足の解消に役立つ理由
- 労働力人口の約半分を占める男性の参入による人材確保
- 夜勤や交代制勤務における人員配置の柔軟化
- 男性看護師の定着率の高さ(キャリア志向が強い傾向)
- 力仕事を含む業務での負担分散
特に、地方や過疎地域の医療機関では看護師の確保が困難であり、性別に関わらず人材を確保することが地域医療を支える上で重要です。災害時や緊急時の医療現場においても、女性と比べて体力面での優位性がある男性看護師の存在は重要です。
男性看護師が長く働き続けるためのキャリア戦略
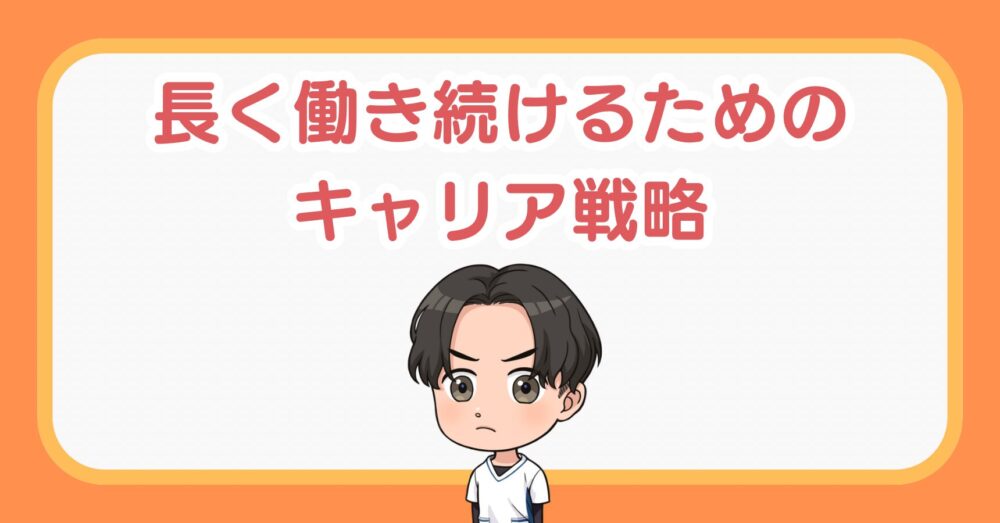
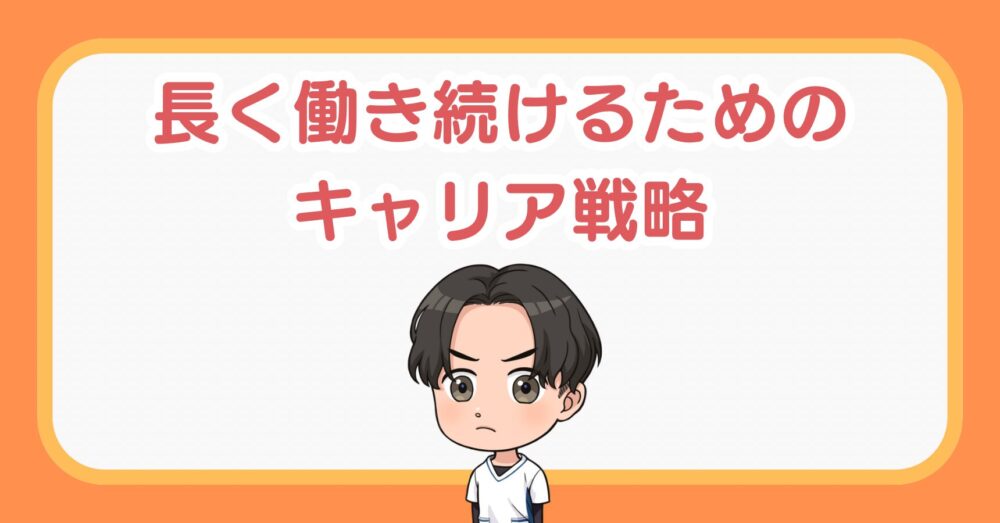
看護師として長く活躍するためには、計画的なキャリア戦略が欠かせません。長期的なキャリア形成のためのステップとして、以下のような戦略が挙げられます。
- スキルアップと専門性の確立
- ワークライフバランスの確立
スキルアップと専門性の確立
継続的な学習と資格取得は、男性看護師のキャリア発展に不可欠です。救急看護、集中ケア、精神看護、手術室看護などの分野では、男性看護師の割合が比較的高く、専門性を発揮しやすい環境があります。
認定看護師・専門看護師制度を活用した専門性の確立は、男性看護師のキャリアアップに有効な手段と言えるでしょう。



キャリアアップに役立つ資格については、以下の記事でも詳しく解説しています。
ワークライフバランスの確立
近年、男性看護師においても育児や家庭との両立が重要なテーマとなっています。女性中心の職場では、男性の育休取得などに対する理解が不足している場合もありますが、制度を積極的に活用する先駆者となることも大切です。
男性看護師の長期キャリア戦略のポイント
- 5年ごとのキャリア目標を設定し、定期的に見直す
- メンターとなる先輩男性看護師を見つける
- 看護以外の関連分野(医療情報、医療安全、感染管理など)にも視野を広げる
- 院内委員会活動に積極的に参加し、病院運営の視点を養う
- 男性看護師会などのネットワークに参加し、情報交換を行う
日本男性看護師会では、男性看護師同士のネットワーク構築やセミナーなどを提供しており、キャリア形成の支援を行っています。



組織を積極的に活用することで、孤立せずに長期的なキャリアを築くことができるでしょう。
まとめ


本記事では、男性看護師が少ない理由について解説しました。「看護師は女性の仕事」という根強いイメージや一般男性と比較して低い年収、肉体的・精神的な負担、女性中心の職場環境での苦労、そしてキャリアパスの不透明さが主な要因です。
ただし、救急や精神科などの分野では、男性看護師の需要が高い傾向にあります。多様な視点による医療の質向上や男性患者へのケアなど、社会的価値も大きいです。教育機関や医療機関の取り組み、社会的イメージの改善を通じて、性別に関わらず活躍できる看護の未来を築いていくことが重要です。
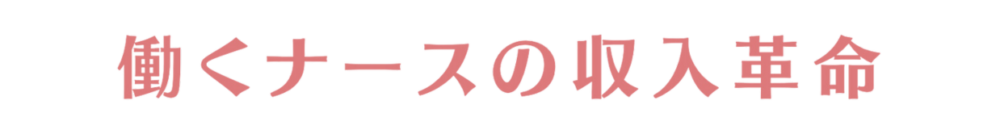
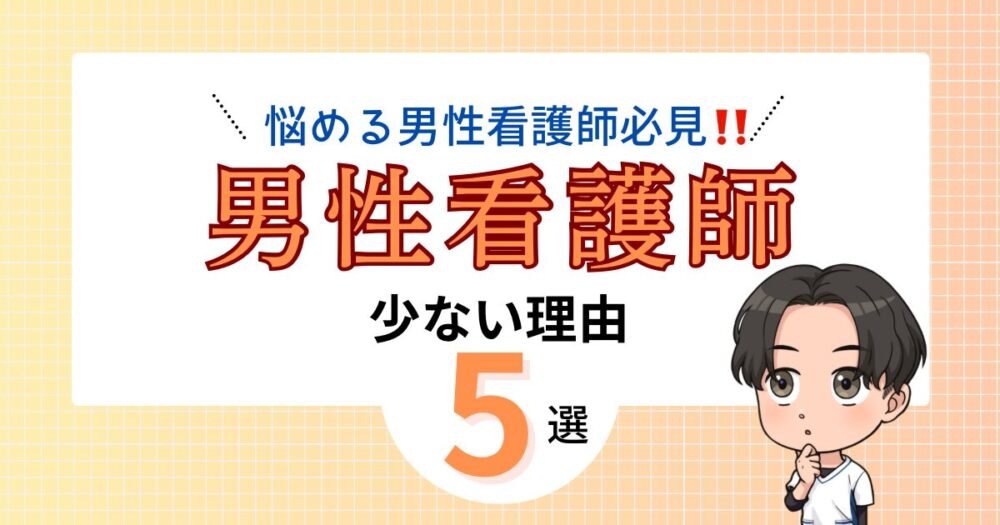

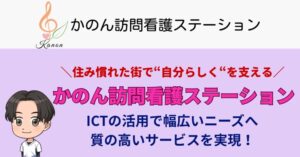
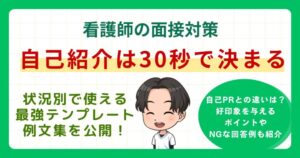

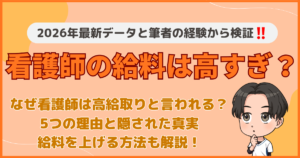
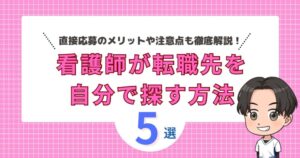
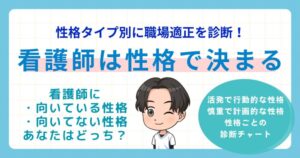

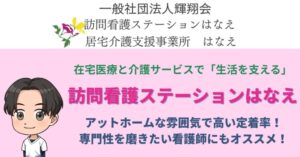
コメント