「人生100年時代」といわれる昨今、定年を迎えても働き続けたいと思う看護師も多いでしょう。多くの医療機関では60〜65歳が定年ですが、看護師不足の現状から、再雇用制度を導入する施設は増加中です。
本記事では、2025年最新の病院・施設別定年年齢の実態から、定年後も看護師として活躍できる職場、そのメリット・デメリットまで徹底解説します。豊富な経験を活かした定年後のキャリア選択肢と具体的な働き方のポイントを知ることで、人生設計に役立つ情報が得られます。
 ryanta73
ryanta73年齢を重ねても、看護スキルを活かして働き続けるための具体的なアドバイスも満載なので、ぜひ参考にしてください。
看護師の定年は60歳または65歳が一般的
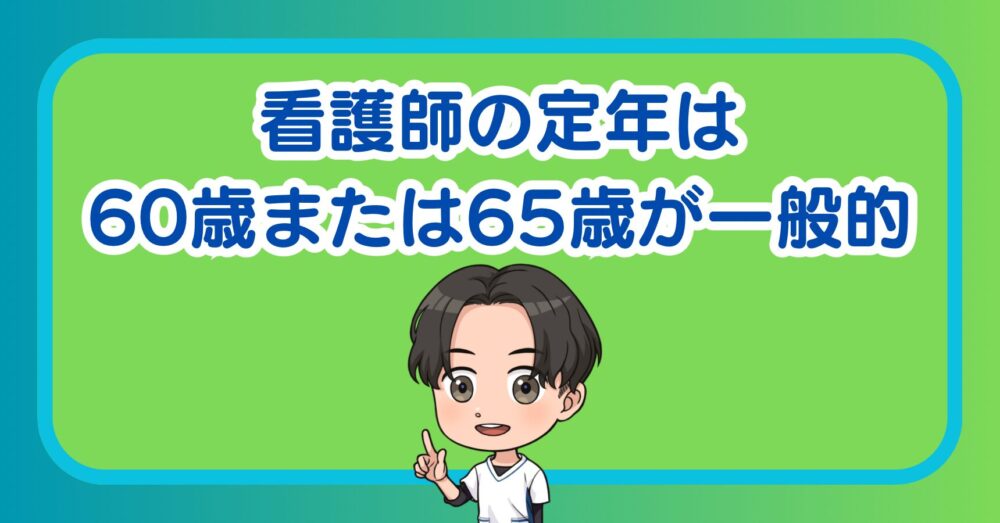
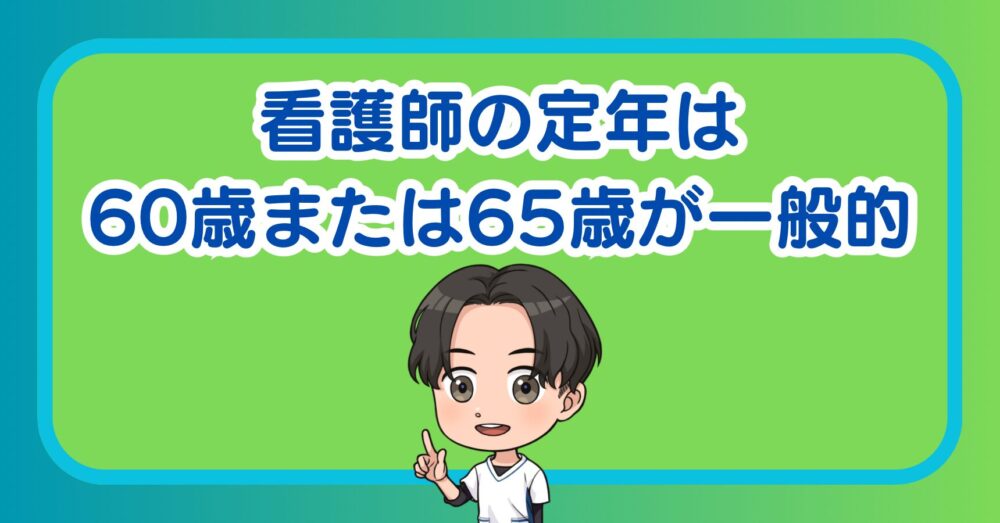
看護師の定年年齢は、勤務先の施設によって異なりますが、一般的には60歳から65歳に設定されています。近年は人材不足や高齢化社会の影響から、定年年齢を引き上げる医療機関も増加傾向にあります。
医療機関の種類別・定年年齢の実態
医療機関の種類によって、看護師の定年制度には違いがあります。以下に主な医療機関別の定年年齢の傾向をまとめました。
| 医療機関の種類 | 一般的な定年年齢 | 再雇用制度の有無 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 大学病院 | 60〜65歳 | あり(多くの場合) | 比較的厳格な定年制度を採用 |
| 総合病院 | 60〜65歳 | あり(多くの場合) | 再雇用制度を整備している施設が多い |
| クリニック | 65歳または定年なし | 場合により異なる | 柔軟な雇用体制の施設が多い |
| 介護施設 | 65歳または定年なし | 場合により異なる | 経験を重視する傾向がある |
| 訪問看護 | 65歳以上または定年なし | 場合により異なる | 経験豊富なベテラン看護師を優遇する傾向 |
公立病院と私立病院の定年制度の違い
公立病院と私立病院では、定年に関する制度や運用に違いがあります。
公立病院の定年制度
公立病院は地方公務員法に準じた定年制度を採用しているケースが多く、一般的には60歳が定年とされています。ただし、総務省の地方公務員定年引上げに関する制度改正により、2023年度から段階的に65歳に引き上げられる流れがあります。
公立病院では、定年制度が比較的厳格に運用されており、定年後は非常勤や嘱託として再雇用されるケースが一般的です。再雇用の場合、給与は定年前と比較して下がることが多いですが、豊富な経験を活かせる管理職やアドバイザー的な役割を担うこともあります。
私立病院の定年制度
私立病院では、法人ごとに独自の就業規則を定めているため、定年年齢は60歳から65歳とばらつきがあります。近年は看護師不足を背景に、65歳定年や定年後の継続雇用制度を導入する病院が増えています。
厚生労働省の高年齢者雇用安定法により、65歳までの雇用確保措置が義務付けられていることから、60歳定年後も継続雇用制度を設けている医療機関がほとんどです。
看護師の定年後の再雇用制度


多くの医療機関では、定年後も看護師としての経験やスキルを活かすために再雇用制度を設けています。再雇用制度には以下のパターンがあります。
- 継続雇用制度
- 定年後も同じ職場で働き続けられる制度です。一般的に雇用形態は非常勤や嘱託に変更され、勤務時間や日数が減少するケースが多いです。日本看護協会の調査によると、定年後も同じ職場で働き続けるシニア看護師は増加傾向にあります。
- 短時間勤務制度
- 週20時間程度の短時間勤務で、夜勤免除など身体的負担を軽減した形での雇用を継続する制度です。ワークライフバランスを重視しながら、経験を活かして働き続けることができます。
- 特定業務専従制度
- 教育担当や外来専従など、特定の業務に特化して働く制度です。長年の臨床経験を若手看護師の育成や特定の専門分野で活かすことができます。
定年延長の最新動向
医療現場における看護師不足や高齢化社会の進展に伴い、看護師の定年に関する考え方も変化しています。
定年年齢の引き上げ
少子高齢化による看護師不足を背景に、定年年齢を65歳以上に引き上げる医療機関が増えています。特に地方の医療機関では、人材確保のために定年年齢の引き上げや撤廃を進めているケースも見られます。
厚生労働省の高年齢者雇用対策によると、65歳以上の高齢者の就業促進が国の方針として打ち出されており、医療機関でもこの流れに沿った対応が進んでいます。



もはや60歳で定年を迎えることはほぼありません。
働き方改革の影響
働き方改革により、シニア看護師でも無理なく働き続けられる環境整備が進んでいます。具体的には夜勤免除、短時間勤務、業務内容の調整など、年齢に配慮した勤務形態の導入が広がっています。
これにより、60歳以降も自分のペースで看護師として働き続けられる選択肢が増えています。日本看護協会の調査によると、現役看護師の7.8人に1人が60歳以上というデータもあります。
年代別・看護師の就業実態
年齢層によって看護師の就業状況には特徴があります。以下に年代別の就業実態をまとめました。
| 年齢層 | 構成割合 | 主な勤務形態 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 50代前半 | 約11.6% | 常勤(夜勤あり/なし) | 管理職や専門職として活躍 |
| 50代後半 | 約9% | 常勤(夜勤なし)・非常勤 | 夜勤免除や時短勤務へ移行する傾向 |
| 60〜64歳 | 約5.7% | 非常勤・パート | 経験を活かした役割、勤務時間の短縮 |
| 65歳以上 | 約3.7% | パート・嘱託・ボランティア | 週2〜3日程度の勤務が多い |



やはり定年後は一気に働く人が減少します。しかし、准看護師の場合は65歳以上が約16%と、全年齢層のなかで最も高い割合です!
定年制度に対する看護師の意識調査
看護師自身が定年についてどのように考えているかも重要なポイントです。日本看護協会による調査では、「体力や健康に問題がなければ、定年後も看護師として働きたい」と考える看護師が全体の多くを占めています。特に50代以上の看護師では、58.9%の人が「経験を活かせる場で働き続けたい」という意見が多く見られます。
一方で、定年後の働き方としては「フルタイムではなく、週2〜3日程度の勤務」「夜勤のない職場」「身体的負担の少ない職場」を希望する声が多く、ワークライフバランスを重視する傾向があります。「定年制度そのものよりも、年齢に関わらず働き続けられる環境整備が重要」という意見も多いです。



高齢化が進む現在、柔軟な勤務体制や高齢看護師の経験を活かせる職場の増加が求められています。
定年後も看護師として働ける職場
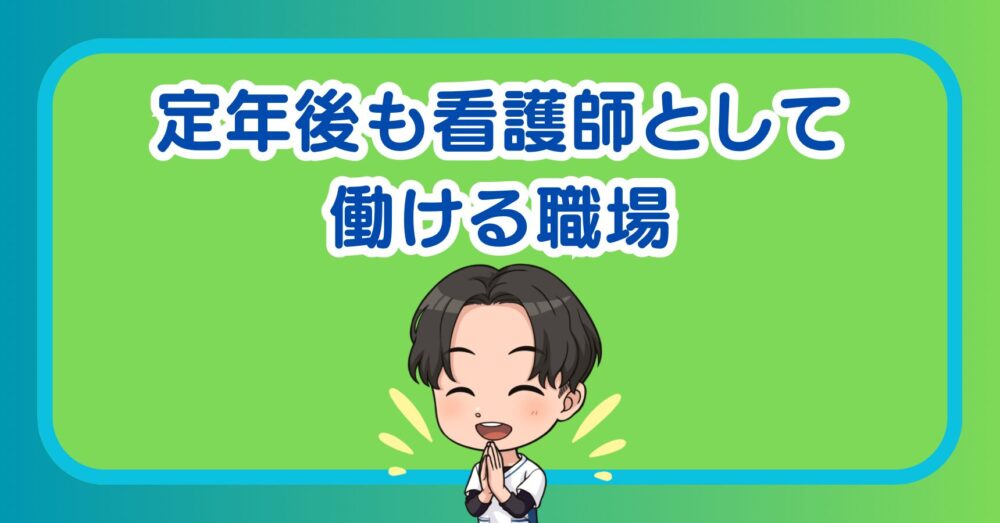
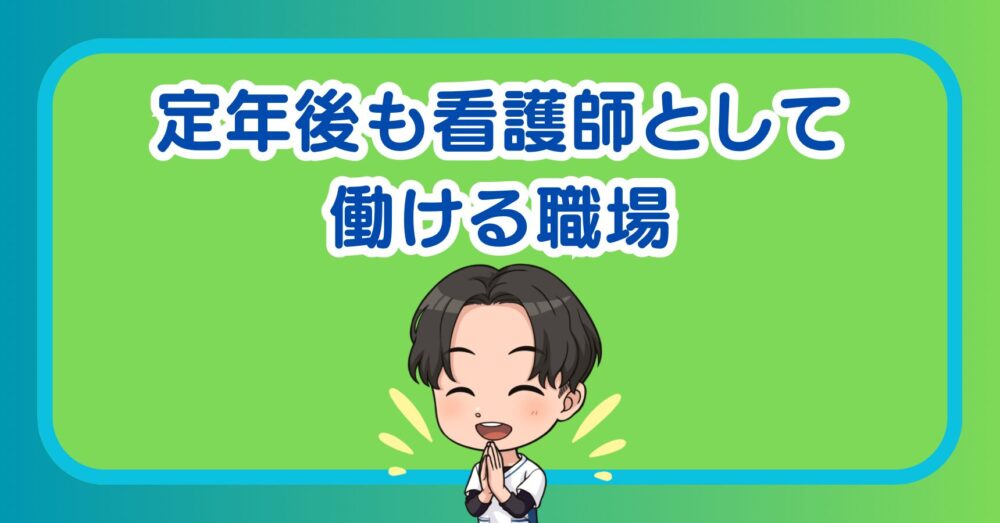
看護師の定年後も、その豊富な経験と専門知識を活かせる職場は数多く存在します。ここでは、60歳以上の看護師が活躍できる代表的な職場とその特徴を詳しく解説します。
- クリニック
- 介護施設
- 訪問看護ステーション
- 保育園・学校
- 健診センター
クリニック
クリニック(診療所)は、看護師の定年後のキャリアとして人気の高い職場です。大規模病院と比較して業務負担が軽減される傾向があり、体力面での不安を抱える定年後の看護師にとって働きやすい環境と言えます。
クリニックでの主な業務は、診療の補助、医療器具の準備・管理、患者の誘導・対応、電話対応などです。急性期医療の現場と比べて緊急性の高い処置が少なく、規則的な勤務時間が設定されていることが多いため、ワークライフバランスを重視したい方に適しています。クリニックは夜勤がない場合が多く、日勤のみの勤務形態を希望する高齢看護師の受け皿となっています。
| クリニックの種類 | 特徴 | 働きやすさ |
|---|---|---|
| 内科・小児科クリニック | 比較的患者層が幅広く、基本的な看護スキルを活かせる | ◎ |
| 皮膚科・眼科などの専門クリニック | 専門的な知識が求められるが、処置が限定的 | ○ |
| 美容クリニック | 医療と美容の知識が必要だが、体力的負担は少ない | ○ |
介護施設


介護施設は、医療と介護の両方の知識を持つ看護師にとって、その専門性を発揮できる職場です。特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、グループホームなど様々な種類の施設があり、それぞれの特性に合わせた看護ケアが求められます。
介護施設での看護師の主な役割は、入居者の健康管理、服薬管理、医療処置、急変時の対応などです。介護職員と連携しながら、入居者の生活全体をサポートする点が特徴的です。厚生労働省の介護サービス施設・事業所調査によると、高齢者人口の増加に伴って介護施設での看護師需要は年々高まっており、60歳以上の看護師の採用にも積極的な施設が増えています。
| 介護施設の種類 | 特徴 | 看護師の役割 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 要介護度の高い高齢者が入居 | 医療的ケア、健康管理、緊急時対応 |
| 有料老人ホーム | 自立度に応じた様々なタイプがある | 健康チェック、服薬管理、医療連携 |
| グループホーム | 認知症高齢者向けの小規模な住居 | 定期訪問による健康管理、相談対応 |
| デイサービス | 日帰りの介護サービス | バイタルチェック、レクリエーション補助 |



私が勤務していた老人ホームでも、50代の転職者はかなり多かったです。むしろ若い人は比較的少なめでした。
多くの介護施設では夜勤が必要な場合もありますが、非常勤やパートとして日勤のみの勤務も可能な場合が多く、働き方の柔軟性があります。長年の看護経験を活かし、介護職員への指導や入居者とのコミュニケーションを重視できる点も、定年後のやりがいにつながっています。
訪問看護ステーション
訪問看護ステーションは、在宅療養中の患者の自宅を訪問し、医療的ケアや生活支援を行う看護サービスを提供する職場です。高齢化社会により在宅医療のニーズが高まる中、訪問看護師の需要は急増しています。
訪問看護師の業務は、患者の状態観察、医療処置、服薬管理、家族への介護指導など多岐にわたります。一人で判断し、行動する場面も多いため、豊富な臨床経験を持つベテラン看護師の知識と判断力が特に重宝されます。



基本的に夜勤がないため、定年後のセカンドキャリアとして選ぶ看護師も増加傾向にあります。
全国訪問看護事業協会の調査によると、訪問看護ステーションで働く看護師の年齢層は他の医療機関と比較して高く、50代以上の看護師も多く活躍しています。訪問看護の特徴として、以下の点が挙げられます。
- 勤務時間が比較的柔軟で調整しやすい
- 患者一人ひとりとじっくり向き合える
- 自分のペースで業務を進められる
- 地域に密着した活動ができる
- 長年の看護経験を直接活かせる
体力面では、訪問先への移動や階段の上り下りなどの負担がありますが、訪問件数や担当エリアの調整によって無理なく働くことが可能です。運転免許を持っていることが条件となる場合が多いため、応募前に確認が必要です。
保育園・学校


保育園や学校の保健室などで働く看護師は、子どもたちの健康管理や応急処置、保健指導などを担当します。病院とは異なる環境で、予防医療や健康教育に携わりたい看護師にとって魅力的な職場です。
保育園看護師の主な業務は、園児の健康チェック、ケガや急な体調不良への対応、感染症対策の指導、医療的ケア児のサポートなどです。一方、学校看護師(養護教諭ではなく看護師として勤務)は、保健室での応急処置や健康相談、健康診断の補助などを行います。
厚生労働省によると、医療的ケア児の受け入れ体制整備のため、保育園に看護師を配置する自治体が増えています。また、私立学校や特別支援学校でも看護師の需要があります。
| 勤務先 | 主な業務 | 勤務の特徴 |
|---|---|---|
| 保育園・認定こども園 | 園児の健康管理、応急処置、保健指導 | 平日日勤のみ、長期休暇は少ない |
| 小中学校・高校 | 保健室支援、健康診断補助 | 日勤のみ、長期休暇あり |
| 特別支援学校 | 医療的ケア、健康管理 | 専門的スキルが必要、日勤勤務 |
教育機関での勤務は、土日祝日が基本的に休みであり、夜勤がないため、規則正しい生活リズムで働きたい定年後の看護師に適しています。



子どもたちの成長を見守れる点にやりがいを感じる人も多いです。
健診センター


健診センターや人間ドック施設は予防医療に特化した職場で、健康診断や人間ドックの実施、結果説明のサポートなどを行います。
健診センターでの看護師の主な業務は、採血、心電図検査の実施、問診対応、受診者への生活指導などです。医療的な知識を活かしながらも、身体的負担が比較的少ない点が特徴です。急性期医療と比較して緊急性の低い業務が中心となるため、定年後も無理なく働ける環境として人気があります。
日本人間ドック学会によると、2025年2月時点で人間ドック実施施設は全国に約1,800カ所あり、看護師の需要は安定しています。特に経験豊富なベテラン看護師は、受診者への適切な対応や的確な指導ができるため重宝されています。健診センターの勤務の特徴として、以下の点が挙げられます。
- 基本的に日勤のみの勤務形態
- 土日祝日が休みの場合が多い
- 夜勤がない
- 急変対応が少ない
- 予定された業務が中心で比較的落ち着いた環境
健診センターでは、健康な人を対象とした業務が中心となるため、精神的負担も軽減されます。健康指導や予防医療の観点から、これまでの臨床経験を活かした指導ができる点もやりがいにつながっています。
企業の健康管理室・産業保健師
企業の健康管理室や産業保健師として働くことも、定年後の看護師のキャリア選択肢の一つです。従業員の健康管理、メンタルヘルスケア、健康相談、保健指導などを担当し、企業の健康経営をサポートする役割を担います。
産業看護の現場では、健康診断の事後措置、職場巡視、健康教育、メンタルヘルス対策など、予防的な活動が中心となります。医療機関とは異なる職場環境で、ビジネスパーソンの健康をサポートする専門職として、新たなやりがいを見出せる職場です。
厚生労働省の産業保健活動情報によると、働き方改革や健康経営の推進に伴い、企業における産業保健師・看護師の需要は高まっています。特に大手企業では、経験豊富な看護師を嘱託や非常勤として採用するケースも増えています。
| 企業規模 | 看護師の役割 | 勤務形態 |
|---|---|---|
| 大企業(1,000人以上) | 健康管理部門での専門職、保健師との協働 | 常勤または非常勤 |
| 中小企業 | 嘱託看護師、健康相談対応 | 非常勤やパートが多い |
| 健康保険組合 | 加入者向け健康支援、保健事業運営 | 常勤または非常勤 |
企業の健康管理室での勤務は基本的に平日日勤のみで、夜勤や休日出勤がないため、ワークライフバランスを重視したい定年後の看護師に適しています。



企業によっては週2〜3日のパート勤務など、柔軟な働き方にも対応しているところが多いです。
定年後も看護師として働くメリット


定年後も看護師を続けることで得られるメリットは、以下のとおりです。
- 長年の経験やスキルを活用できる
- 経済的に安定する
- 社会とのつながりを維持できる
- 精神的健康への好影響
- キャリアの集大成を活かす喜び
長年の経験やスキルを活用できる
看護師として数十年働いてきた人は、豊富な経験と専門的なスキルを持っています。経験と知識は、とても価値のある財産です。定年後も看護師として働くことで、これまで培ってきた専門知識や技術を無駄にすることなく活用できます。特に以下のような場面で、ベテラン看護師の経験は大きな価値を発揮します。
- 若手看護師への指導や教育役
- 患者さんやご家族への適切な対応
- 緊急時の冷静な判断と対応
- 複雑な症例への対応
- 組織内のリーダーシップ
医療現場では、マニュアルだけでは対応できない状況が数多くあります。緊急性の高い場面で、長年の経験に基づく判断力や対応力は非常に重宝されます。



患者さんの急変時などは、ベテラン看護師の存在はすごく頼りになりますよね。
経済的に安定する


定年後も看護師として働き続けることは、経済的な安定をもたらします。特に日本の年金制度の現状を考えると、収入源を持つことの重要性は高まっています。
内閣府の「国民生活に関する世論調査」では、60〜69歳のなかで65%以上の人が資産・貯蓄に不満を持っています。看護師として働き続けることで、以下のような経済的メリットが得られます。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 安定した収入源 | 年金に加えて給与収入を得ることで、生活の質を維持できる |
| 年金受給額の増加 | 繰下げ受給により年金額がアップする可能性がある |
| 医療費の負担軽減 | 勤務先の健康保険に加入することで、医療費の自己負担を抑えられる場合もある |
| 老後資金の形成 | 定年後の収入で老後の資金をさらに蓄えることができる |
特に短時間勤務やパートタイムでの就労は、無理なく収入を得られる選択肢として人気があります。「高年齢者雇用安定法」の改正により、70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となったことも、シニア看護師の雇用促進につながっています。
社会とのつながりを維持できる
定年退職後に起こりがちな「社会からの孤立」を防ぐという点でも、看護師を続けることには大きなメリットがあります。
内閣府の「高齢社会白書」によると、社会との接点を持ち続けることは高齢者の精神的健康に大きく寄与するとされています。看護師として働き続けることで得られる社会的メリットには以下が挙げられます。
- 職場での人間関係を通じた社会的つながりの維持
- 患者さんやご家族との関わりによる充実感
- 社会の役に立っているという自己有用感
- 規則正しい生活リズムの維持
- 新しい知識や技術の習得による知的刺激
- 目標を持って日々を過ごすことによる生きがい



長年培った知識と経験を次世代に伝えるという役割も、ベテラン看護師の大きなやりがいとなっています。
精神的健康への好影響


看護師として働き続けることは、精神的健康にも良い影響を与えます。患者の回復や感謝の言葉など、看護師の仕事は日々の小さな達成感を得られる機会が多いです。こうした達成感の積み重ねが自己肯定感を高め、心の健康を支えます。
医療や看護の世界は常に新しい知識や技術が生まれる分野です。学び続けることで脳を活性化し、認知機能の維持にも役立ちます。



私のまわりのベテラン看護師も「仕事は大変だけど、働き続けることで若々しい気持ちでいられる」と話しています。
キャリアの集大成を活かす喜び
定年後の看護師としての働き方は、これまでのキャリアの集大成として新たな形を見出すチャンスでもあります。例えば、以下の要素も喜びのひとつです。
- 後進の育成・指導に力を入れる
- 患者さんとじっくり向き合える環境を選ぶ
- 特定の分野でのスペシャリストとして活躍する
- 医療安全管理など、経験を活かせる専門分野で力を発揮する
これまでの看護人生で培った「人を看る力」は、さまざまな場面で必要とされています。その力を社会に還元することで、自分自身の人生にも深い満足感をもたらすことができるでしょう。



経験でしか得られないスキルは多いです。ベテランならではの高いアセスメント力には私も脱帽です。
定年後も看護師として働くデメリット


定年後に看護師として働く際に直面する可能性のある課題は、以下のとおりです。
- 体力面の不安
- 給与水準の変化
- 職場の人間関係の変化
- 最新医療知識・技術への適応
- 雇用の不安定さ
- ワークライフバランスの変化
体力面の不安
看護師の仕事は、身体的な負担が大きい職業の一つです。定年を迎える60〜65歳になると、若い頃と比較して体力の低下を感じる人が多くなります。特に病院勤務の場合、夜勤や長時間の立ち仕事、患者の移乗介助など、身体的負担の大きい業務が多く含まれています。厚生労働省の調査によると、50代看護師の退職者の約10%が健康上の理由です。
具体的な身体的負担として、以下のような問題が挙げられます。
- 長時間の立ち仕事による足・腰への負担
- 患者の移乗や体位変換時の腰痛リスク
- 夜勤による睡眠リズムの乱れと回復の遅れ
- 繁忙期の連続勤務による疲労の蓄積
年齢を重ねるにつれて、体調不良からの回復に時間がかかるようになり、若い頃のようにハードワークを続けることが難しくなる傾向があります。



私も30代後半になり、若い頃よりも夜勤後の疲れが大きくなりました。
給与水準の変化


多くの医療機関では、定年後の再雇用制度を採用していますが、その際に給与水準が大幅に下がるケースが一般的です。
| 雇用形態 | 給与変化の特徴 | 平均的な減少率 |
|---|---|---|
| 定年前(正規雇用) | 基本給+諸手当(夜勤手当、資格手当など) | ー |
| 再雇用(契約社員) | 基本給の減額、賞与の減額または廃止 | 約20〜30%減 |
| パート・アルバイト | 時給制への変更、福利厚生の縮小 | 約30〜50%減 |
厚生労働省の調査によると、60歳以降の看護師の平均給与は減少傾向にあるというデータがあります。特に注意すべき点として、以下の要素が挙げられます。
- 退職金支給後の再雇用では、新たな退職金制度が適用されないケースが多い
- 役職手当や管理職手当が無くなることがある
- 年金受給と給与の調整(在職老齢年金の仕組み)による実質収入の減少
- 社会保険料の負担割合の変化



収入面での変化は、定年後の生活設計に大きな影響を与える可能性があります。
職場の人間関係の変化
定年後、これまでと同じ職場で働き続ける場合でも、立場や役割の変化により人間関係に戸惑いを感じるケースは多いです。管理職からスタッフへの立場の変化、若い上司の下で働くことになるなど、これまでの人間関係や権限関係が大きく変わることがあります。
具体的な人間関係の変化として、以下のような課題があります。
- かつての部下が上司になることによる心理的抵抗感
- 年齢差による価値観やコミュニケーションスタイルの違い
- 新しい医療技術や電子カルテなどのシステム導入についていけない焦り
- 若い世代との協働に対する適応の難しさ
- 「ベテラン」として過度に期待される場合のプレッシャー
新しい職場へ移る場合は、長年培ってきた人間関係やコミュニティから離れ、新たな環境に適応する必要があります。環境変化は、精神的ストレスの大きな要因です。
最新医療知識・技術への適応
医療業界は常に進化しており、新しい技術や知識、電子カルテなどのシステムが次々と導入されています。定年を迎える年齢になると、これらの変化に対応することが若い世代より難しく感じられることがあります。特に、新しい医療機器や電子カルテなどのIT技術への適応に不安を感じるケースが多いです。
具体的な課題は以下のとおりです。
- 電子カルテなど新しいシステム操作の習得
- 日進月歩で変化する医療知識のアップデート
- 新しい医療機器の操作技術の習得
- 若い世代と比較して研修機会が限られる場合がある
特に、長年同じ環境で働いていた看護師が、定年後に全く異なる分野(例:急性期病院から介護施設へ)に移る場合、業務内容や求められるスキルセットの違いに戸惑うことがあります。



記録や看護計画など、すべて手書きで行っていた時代からみれば、電子カルテの操作や最新機器の取り扱いに戸惑うベテランも多いです。
雇用の不安定さ


多くの場合、定年後の再雇用は有期契約となります。通常1年ごとの契約更新であることが多く、長期的な雇用が保証されていないことが不安要素となります。体調不良や家族の介護など、高齢になるにつれて直面する問題が増えることから、契約更新が難しくなるケースも多いです。雇用に関して、以下の不安要素が挙げられます。
- 短期契約による将来への不安
- 景気変動や医療機関の経営状況による雇用への影響
- 体調変化による雇用継続の不確実性
- 正規雇用と比較して解雇リスクが高い
雇用の不安定さは精神的なストレスとなるだけでなく、将来設計や住宅ローンなどの長期的な金銭的計画にも影響を与える可能性があります。



ただし、看護師は定年後も需要が高いため、他の職種と比べてもかなり安定性はあります。
ワークライフバランスの変化
定年後も看護師として働き続けることで、家族との時間や自分の趣味に費やす時間が制限される可能性があります。特に、「第二の人生」として楽しみにしていた活動や、孫の世話、旅行などの計画が実現しにくくなる場合があります。配偶者が退職している場合、生活リズムの不一致が生じることもあります。
ワークライフバランスの課題として、以下が挙げられます。
- 家族との時間の確保が難しい
- 同年代の友人が退職している中での孤独感
- 自己啓発や趣味の時間の減少
- 健康管理のための時間確保の難しさ
デメリットを認識した上で、自分のライフスタイルや価値観に合った働き方を選択することが重要です。定年後も看護師として働くことを選ぶ場合は、直面する課題に対する対策を事前に考えておくことで、より充実したキャリア継続が可能になります。
看護師が定年後も無理なく働き続ける方法
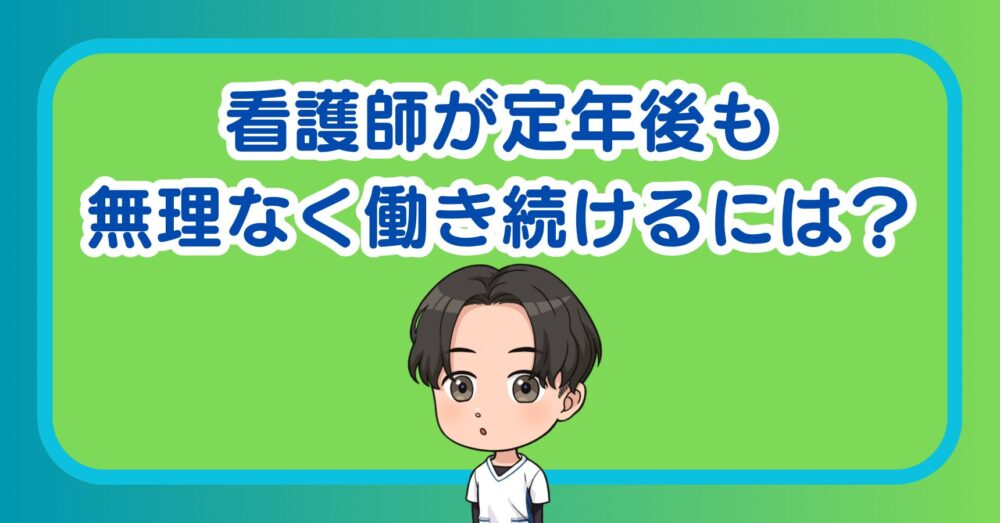
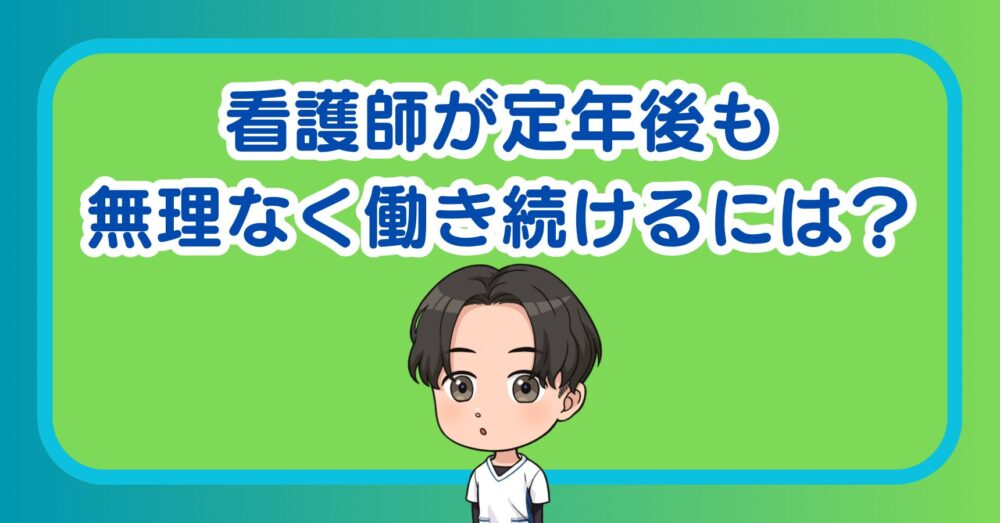
定年後も看護師として充実したキャリアを続けるためには、以下の方法が効果的です。
- 健康管理と体力作り
- 人脈作りとコミュニケーション力の強化
- 定年後を見据えたキャリアプランの設計
健康管理と体力作り
定年後も看護師として働き続けるためには、日頃からの健康管理と体力維持が欠かせません。特に50代以降は体力の衰えを自覚する人が増えるため、計画的な健康管理が重要です。日常的な健康管理のポイントは、以下の表のとおりです。
| 項目 | 具体的な取り組み |
|---|---|
| 定期的な健康診断 | 年1回の健康診断に加え、50歳以降は半年に1度のペースで検診を受けることをおすすめします |
| 適度な運動 | ウォーキングや水泳など無理のない有酸素運動を週2〜3回行うことで体力維持につながります |
| 栄養バランス | タンパク質やカルシウムを意識した食事で筋力低下や骨粗しょう症を予防します |
| 十分な休息 | 質の良い睡眠を確保し、シフト勤務の場合は体調管理に特に注意しましょう |
特に看護師は立ち仕事や夜勤など身体的負担が大きいため、腰痛や足の浮腫みなどの職業病対策も重要です。腰痛予防のためのコルセットの使用や、適切な姿勢での業務遂行を心がけましょう。



日本看護協会が公開している「看護職の労働安全衛生ガイドライン」では、年齢に応じた労働環境の調整についても触れられています。
50代・60代の体力作りのポイント
- 50代:有酸素運動と軽い筋力トレーニングのバランスが重要
- 60代以降:関節に負担をかけない水中ウォーキングやヨガなどがおすすめ
人脈作りとコミュニケーション力の強化


定年後の再就職や転職を円滑に進めるためには、日頃からの人脈形成とコミュニケーション力の強化が欠かせません。特に看護業界では、人と人とのつながりが重要な役割を果たします。
効果的な人脈形成の方法
- 看護協会や専門分野の研究会に積極的に参加する
- SNSやオンラインの看護師コミュニティに参加する
- 勉強会やセミナーに参加して同業者とのネットワークを広げる
- 前職の同僚や上司との関係を大切にする



日本看護協会では、各都道府県の支部で定期的に研修会や交流会が開催されています。積極的に参加することで、同じ境遇の看護師との情報交換ができるだけでなく、求人情報を得る機会にもなります。
- 世代間コミュニケーションのコツ
- 定年後に新しい職場で働く場合、若い世代との協働が不可欠です。世代間の価値観の違いを理解し、円滑なコミュニケーションを図ることが重要になります。
| 世代別の特徴 | コミュニケーションのコツ |
|---|---|
| 20〜30代の若手看護師 | デジタルツールに慣れている世代。LINEなどのメッセージツールも活用し、押し付けがましくない助言を心がける |
| 40代のミドル層 | キャリアと家庭の両立に悩む世代が多い。経験者としての共感を示しつつ、サポート姿勢を示す |
| 管理職層 | 経験豊富なベテランとしての意見は尊重されるが、謙虚な姿勢で新しい環境や方針にも適応する柔軟性を示す |
定年後を見据えたキャリアプランの設計


充実した定年後のキャリアを築くためには、40代〜50代のうちから計画的にキャリアプランを設計しておくことが重要です。突然の定年ではなく、段階的な移行を考えることで、無理なく長く働き続けることができます。
定年の5年前から始めるキャリア準備
定年後の働き方を考える際には、余裕を持って準備を始めることが重要です。以下のようなステップで計画的に進めましょう。
- 自己分析
- 自分の強み、専門性、好きな看護分野を再確認する
- 情報収集
- 定年後も働ける職場の情報を集め、条件を比較する
- スキルアップ
- 必要に応じて資格取得や研修を受講する
- 試験的な移行
- 非常勤やパートなど、働き方を徐々に変えてみる
- 経済計画
- 年金と給与のバランスを考えた収入計画を立てる
看護師としての専門性を高めるための資格取得も効果的です。特に、以下の資格は定年後のキャリアに役立ちます。
| 資格名 | 定年後の活躍の場 |
|---|---|
| 認定看護師 | 専門クリニック、教育機関での講師、コンサルタント |
| 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 介護施設、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所 |
| 訪問看護認定看護師 | 訪問看護ステーション、在宅医療支援 |
| 産業保健師 | 企業の健康管理室、健診センター |
働き方の多様化を検討する
定年後は、フルタイムでの勤務にこだわらず、自分のライフスタイルや体力に合わせた働き方を検討しましょう。
- 週2〜3日のパート勤務
- 日勤のみの勤務形態
- 短時間正社員制度の活用
- 季節限定の臨時職員
- オンコールや応援スタッフとしての登録
近年では、厚生労働省が推進する「働き方改革」の一環として、医療機関でも柔軟な勤務形態を導入する動きが広がっています。



自分に合った働き方を職場に提案できる交渉力も身につけておくと良いでしょう。
看護師の定年に関するよくある質問
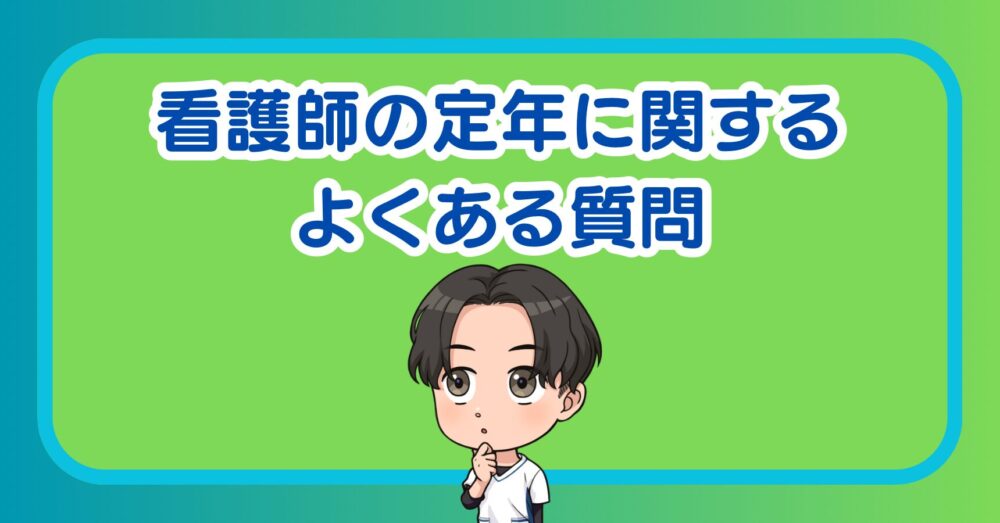
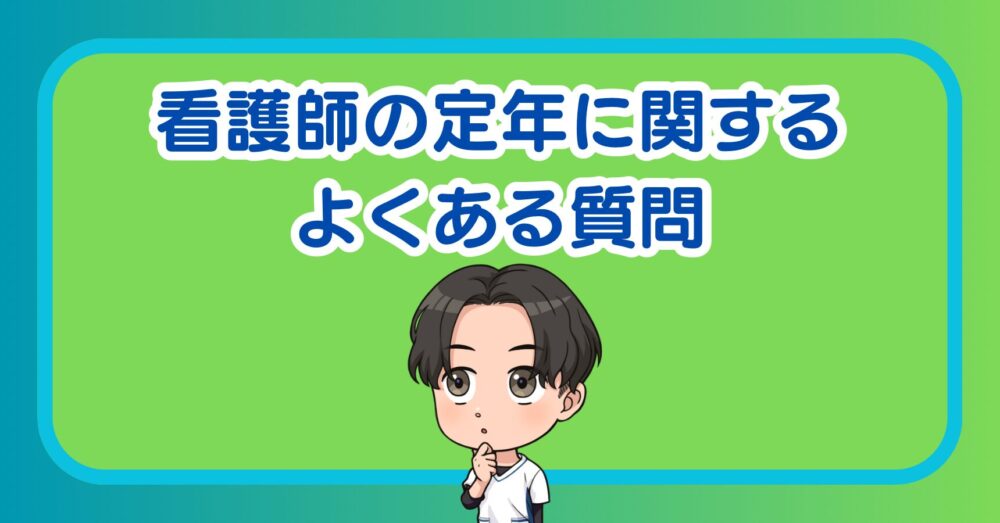
看護師の定年に関して、多くの方が疑問や不安を抱えています。特に多く見られる質問は、以下のとおりです。
- 定年後も資格は有効?
- 男性看護師の定年は?
- 70歳以上でも働ける求人はある?
- 再雇用制度とは何ですか?
- 定年退職後の年金はどうなる?
定年後も資格は有効?
看護師の資格は一度取得すれば、定年退職後も含めて生涯有効です。ただし、長期間現場を離れていた場合には、最新の医療知識や技術に差が生じている可能性があります。再就職の際には、以下のような研修を受けるのがおすすめです。
- 日本看護協会が提供する「看護職の復職支援研修」
- 各都道府県ナースセンターが実施する復職支援プログラム
- 病院・施設が独自に行う研修制度
日本看護協会ナースセンターでは、ブランクのある看護師向けに無料の復職支援研修を提供しています。これらの研修は、最新の医療知識のアップデートや実技の復習ができるため、ブランクがある方には特に有効です。
男性看護師の定年は?
男性看護師と女性看護師の定年年齢に法的な違いはありません。性別に関わらず、勤務先の規定に基づいた定年制度が適用されます。多くの医療機関では60歳または65歳を定年としているケースが一般的です。男性看護師特有の課題としては、以下が挙げられます。
| 課題 | 対応策 |
|---|---|
| 体力の低下に伴う業務負担 | 体力維持のための健康管理、力仕事が少ない部署への異動 |
| 管理職への昇進機会 | 管理者研修の受講、リーダーシップスキルの向上 |
| 少数派ゆえのキャリアモデル不足 | メンター制度の活用、男性看護師のネットワーク構築 |



定年後のキャリア選択において、性別による大きな違いはありません。男性看護師の場合、体力的特性を活かした介護施設や精神科病院での需要が高い傾向にあります。
70歳以上でも働ける求人はある?
70歳以上の看護師でも働ける求人は存在します。特に、近年は高齢化社会の進展と人材不足を背景に、経験豊富なシニア看護師の採用に積極的な医療機関や施設が増えています。
厚生労働省によると、2021年4月より70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となりました。70歳以上の看護師に適した職場としては以下が挙げられます。
- 外来診療のクリニック(特に日勤のみの勤務形態)
- デイサービスなどの介護施設(夜勤なし)
- 健診センター(定期的な健康診断業務)
- 産業保健師(企業内での健康管理業務)
- 電話相談(健康相談や医療相談のコールセンター)
70歳以上で働く場合の勤務条件の特徴としては、以下のような傾向があります。
| 勤務条件 | 一般的な傾向 |
|---|---|
| 勤務時間 | 短時間勤務(週20時間程度)が多い |
| 勤務形態 | 日勤のみ、夜勤免除が一般的 |
| 給与体系 | 時給制が多く、年金との併用を考慮 |
| 業務内容 | 経験を活かした指導や相談業務が中心 |
実際に70歳以上で活躍している看護師の例として、医療技術の教育指導者、患者相談窓口担当者、新人看護師のメンターなど、長年の経験を活かせる役割で重宝されているケースが多いです。
再雇用制度とは何ですか?
再雇用制度とは、定年退職した従業員を一定の条件下で引き続き雇用する制度です。看護師の場合、多くの医療機関では定年後に希望者を対象として再雇用制度を設けています。再雇用制度の特徴は以下のとおりです。
- 雇用形態が正社員から契約社員やパートタイムに変更されることが多い
- 給与体系が変更され、定年前より減額されることが一般的
- 勤務時間や業務内容を調整できる場合が多い
- 通常1年単位の契約更新制が採用されている
再雇用制度を利用する際のメリットとデメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 馴染みのある職場で継続して働ける | 給与が定年前より減少する場合が多い |
| 職場環境や業務に関する新たな学習負担が少ない | 役職や責任が変わることによる心理的影響 |
| 年金受給と組み合わせた収入計画が立てやすい | 契約更新の不安定さ |
定年退職後の年金はどうなる?
厚生年金は原則65歳から受給開始ですが、60歳から繰り上げ受給することも可能です(ただし減額されます)。逆に、70歳まで繰り下げると増額されます。
60歳以上65歳未満で再雇用などにより働く場合、在職老齢年金制度により、収入に応じて年金が一部または全額支給停止になる場合があります。具体的には、以下の基準があります。
| 対象年齢 | 月収+年金の合計 | 年金支給状況 |
|---|---|---|
| 60〜64歳 | 28万円以下 | 全額支給 |
| 28万円超 | 超過分に応じて一部支給停止 | |
| 65〜69歳 | 47万円以下 | 全額支給 |
| 47万円超 | 超過分に応じて一部支給停止 |
定年後の収入と年金のバランスを考えることで、最適な働き方を選択することが重要です。



例えば、年金受給額を最大化するために勤務時間を調整したり、年金の繰り下げ受給を選択するなどの方法があります。
まとめ


看護師の定年は一般的に60〜65歳ですが、病院や施設によって異なります。定年後も看護師として働ける場所は多く、クリニックや介護施設、訪問看護ステーション、保育園・学校、健診センターなどが選択可能です。
定年後も働くことは、長年の経験を活かせる、経済的安定が得られる、社会とのつながりを維持できるといったメリットがある一方で、体力面の不安や給与水準の変化などのデメリットも考慮する必要があります。定年後も無理なく働き続けるためには、日頃の健康管理と体力づくり、人脈形成、そして早い段階からのキャリアプラン設計が重要です。



看護師免許は、一度取得すれば生涯有効です。年齢に関わらず専門性を活かしたセカンドライフを送ることができます。
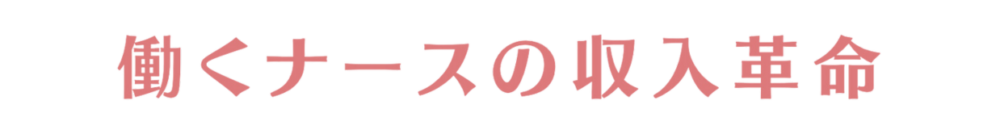
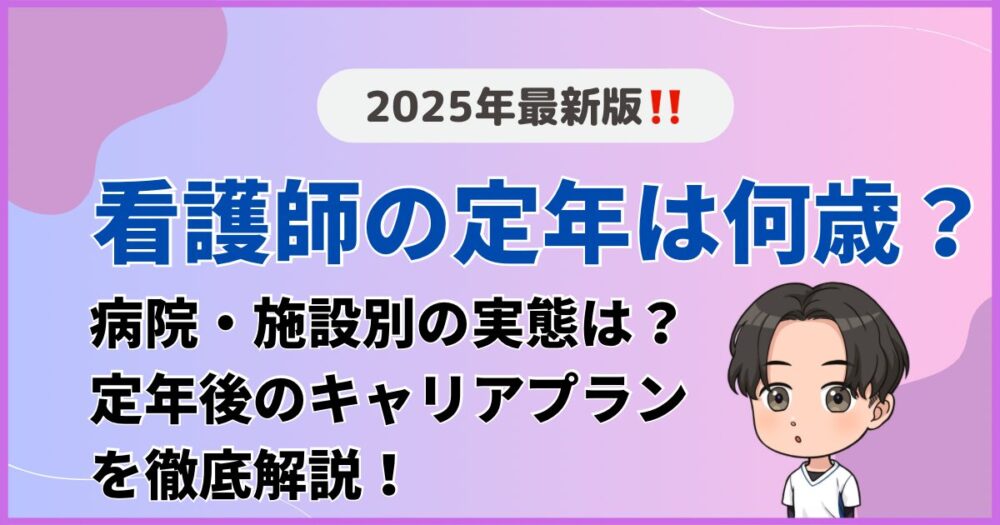
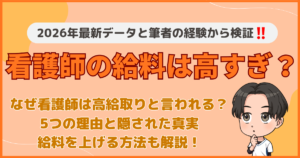
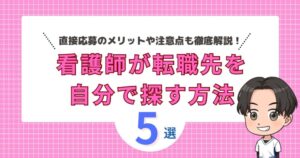
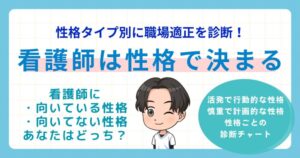

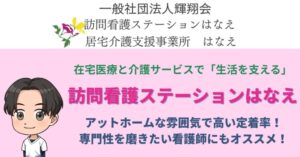
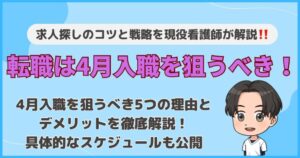
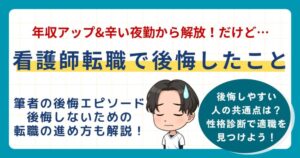
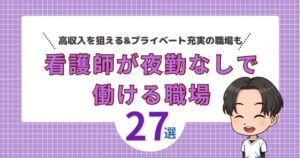
コメント