「もう看護師4年目なのに仕事ができない…」
看護師4年目ともなると、新人の頃の緊張感から解放される一方、後輩の指導やより高度な業務が求められ、理想と現実のギャップに苦しむ人も多いのではないでしょうか。実際、私自身も病棟勤務未経験の状態で4年目を迎え、「仕事ができない」「看護師に向いていない」と自信を失い悩み続けました。
≫看護師に向いている人の特徴5選!理想の職場選びのコツも解説
 ryanta73
ryanta73看護師の4年目では誰もがぶつかる壁があります。
この記事では、私の実体験をもとに、同じ悩みを抱える看護師の方が前を向いて進むための具体的な方法をお伝えします。
筆者「ryanta73」のプロフィール
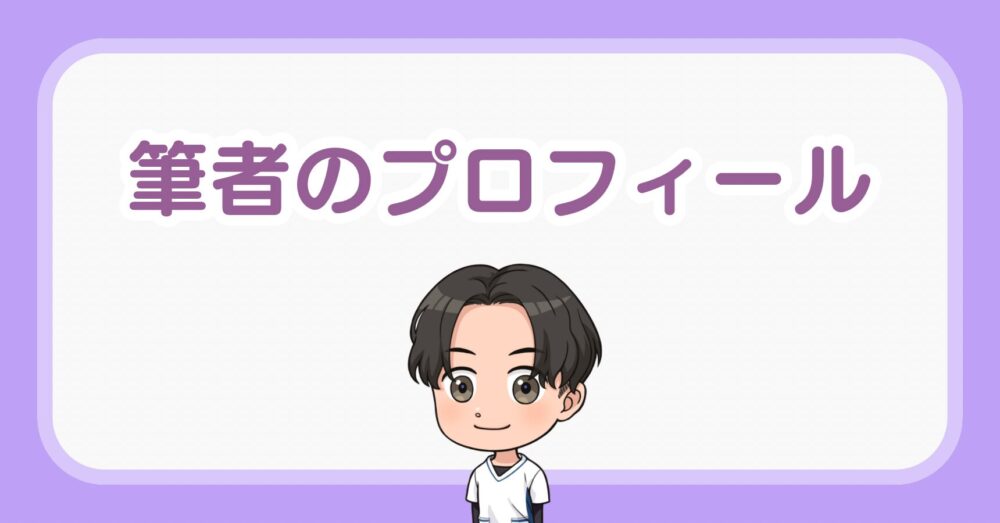
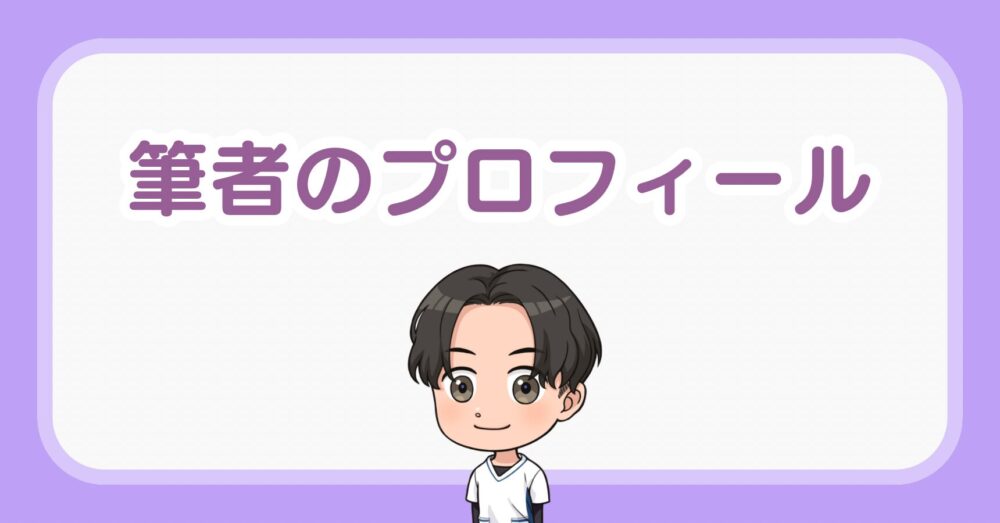
私は看護師歴10年以上であり、急性期病院、精神科病院、介護施設を経て、現在は介護施設で主任看護師として勤務しています。看護師4年目当時はオペ室から病棟勤務へ異動したばかりで、業務の違いや知識不足に悩み、挫折を経験。その後、数々の困難を克服し、現在は自身の経験を活かして後輩指導やチームのマネジメントにあたっています。
≫【現役主任が語る】主任看護師の本当の役割とは?必要スキル・現場のリアルを徹底解説



そんな私も、4年目の頃は同じような壁にぶつかり、毎晩のように「もう辞めたい」と考えていました。
特に、オペ室から未経験の病棟へ異動した4年目は、私の看護師人生で最も辛い時期でした。しかし、その経験があったからこそ、自分なりの働き方を見つけ、今では後輩指導やマネジメントという新しい役割を担うことができています。
これまでの経歴サマリー
私のキャリアは決して順風満帆ではありませんでした。様々な現場で悩み、試行錯誤を繰り返したからこそ得られた視点があります。
- 1〜3年目
- 資格取得後、急性期病院で勤務。主に心臓外科の手術全般の器械出し・外回り看護を経験。専門性の高い環境で、正確性とスピードを徹底的に叩き込まれました。
- 4〜6年目
- 同じ病院内での勤務だが、本人希望ではない異動となる。病棟業務はほぼ未経験の状態からスタート。アセスメント能力や多重課題への対応に苦しみ、「仕事ができない」と最も悩んだ時期です。
- 7〜9年目
- 精神科単科の病院へ転職。患者さんとの対話を重視する精神科看護に魅力を感じ、コミュニケーションスキルと傾聴力を磨きました。
- 10年〜現在
- 有料老人ホームへ転職。元々介護士だったこともあり、いつが福祉業界に身を置くことは決めていました。急性期から精神科まで多様な領域を経験したことを評価され、入職2年目で看護主任に昇進。現在はスタッフの育成や多職種連携、施設全体のケアの質向上に努めています。
この記事を通じて読者に伝えたいこと
看護師の4年目は、一人前の看護師として扱われ、後輩指導も始まるなど、周囲からの期待が一気に高まる時期です。しかし、その期待と自分の実力とのギャップに苦しむ人は少なくありません。多くの看護師が通る道であり、成長するために必要な「産みの苦しみ」でもあります。



大切なのは、一人で抱え込まず、正しい方向に向かって一歩を踏み出すことです。
かつての私のように暗いトンネルの中にいる人が、自分らしいキャリアの光を見つけるための道しるべとなることを願っています。
私が看護師4年目で直面した「仕事ができない」辛さ
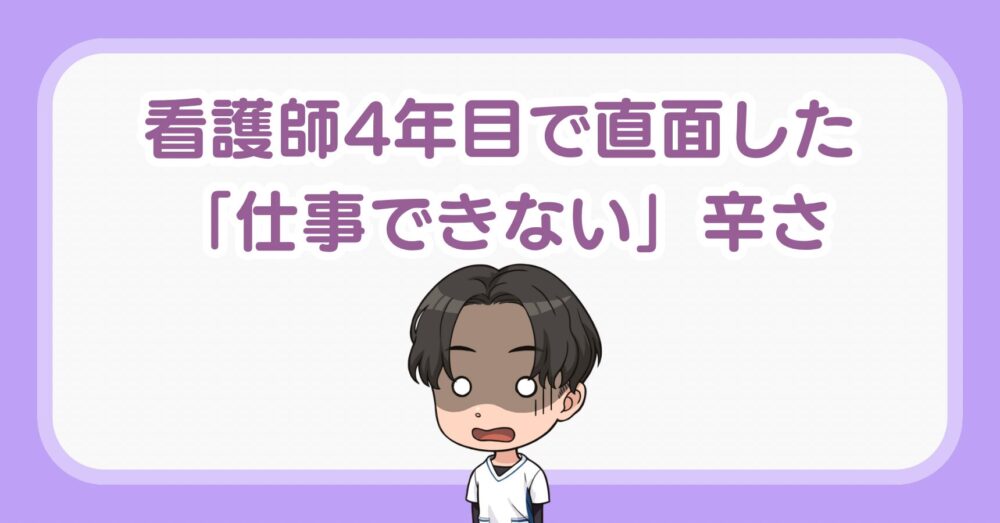
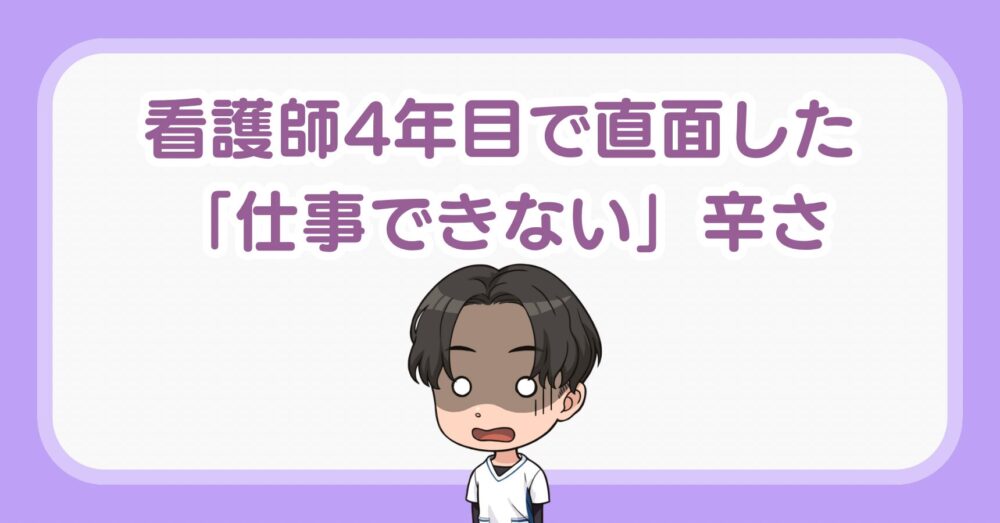
「看護師4年目にもなって、どうしてこんなに仕事ができないんだろう…」
もし自分が今、そんな風に自分を責めているのなら、少しだけ私の話を聞いてください。何を隠そう、私自身が看護師4年目のときにキャリア最大の壁にぶつかり、毎日「辞めたい」と涙をこらえていた一人だからです。
私は新卒から3年間、急性期病院のオペ室(手術室)で勤務していました。専門的な知識と技術が求められる環境で、それなりに自信を持って仕事に取り組んでいたつもりです。しかし、4年目の春、突然の辞令で一般病棟への異動が決定。



これが、私の自信を打ち砕く期間の始まりでした。
オペ室と病棟では、求められるスキルが全く異なります。患者と密に関わることも、多重課題を同時にこなすことも、私にとってはすべてが未経験。「4年目」という肩書きだけが重くのしかかり、経験とスキルのギャップに苦しむ日々が続きました。
同期や先輩との差を感じ、自信喪失した日々
病棟に異動して最も辛かったのは、周囲との圧倒的な差を突きつけられることでした。特に、同期の存在は私の心を大きく揺さぶりました。
病棟で3年間経験を積んできた同期は、すでにチームリーダーを任され、急変時も冷静に対応し、後輩指導までこなしていました。一方の私は、ナースコール対応に追われ、点滴の準備に手間取り、日々の記録ですら時間がかかる始末。同期がテキパキと仕事をこなす横で、私はまるで新人看護師のように、一つひとつの業務に戸惑っていました。
先輩看護師からの視線もプレッシャーでした。「4年目なんだから、これくらい分かるよね?」という無言の圧力をひしひしと感じ、簡単なことでも質問するのをためらってしまうのです。プリセプターとしてついてくれた先輩は親身になってくれましたが、「また同じようなことを聞いている」と思われるのが怖くて、分からないことを分からないままにしてしまい、結果的に小さなミスを繰り返す悪循環に陥りました。



新人の頃であればあれこれ聞けたのですが、4年目ともなると気軽に聞けなくなります。
さらに、病棟経験では私より先輩である2年目や3年目の後輩に、業務の進め方や病棟のルールを教わる場面も少なくありませんでした。彼らに悪気がないのは分かっていても、年下の看護師に指示される状況は、私のプライドを少しずつ削り取っていきました。「4年目なのに情けない」という自己嫌悪に陥り、出勤前には吐き気がし、夜は仕事の失敗ばかりが頭をよぎって眠れない。そんな自信喪失の日々が続きました。
「仕事ができない」と感じた具体的なエピソード
当時の私が「自分は仕事ができないダメな看護師だ」と痛感した、具体的なエピソードをいくつかご紹介します。
- 私の失敗と周囲の反応
- 受け持ち患者の点滴更新、Aさんのトイレ介助のナースコール、Bさんの家族からの病状説明の希望、Cさんの術後バイタル測定が同時に発生。パニックになり、緊急性の低いトイレ介助を優先してしまった結果、術後患者の観察が遅れ、リーダー看護師から「なぜ報告しなかったの?優先順位を考えて」と厳しく指導されました。
- 当時の心境
- オペ室では一つの業務に集中できたのに、病棟では次から次へとタスクが降りかかってきます。頭が真っ白になり、何から手をつければ良いか判断できませんでした。周りに迷惑をかけてしまった罪悪感でいっぱいになりました。
アセスメントと医師への報告
- 私の失敗と周囲の反応
- 患者の発熱と倦怠感の訴えに対し、医師へ報告。しかし、オペ室の癖で局所的な情報しか伝えられず、「全体のバイタルは?食事や排泄の状況は?ドレーンからの排液は?」など、病棟で必要な視点が抜けた報告をしてしまい、「情報が足りない。もう一度アセスメントしてきて」と突き返された。
- 当時の心境
- 4年目として的確な報告ができないことが恥ずかしく、医師に話しかけるのが怖くなりました。自分のアセスメント能力の低さを痛感し、患者の異変に気づけないのではないかと不安になりました。
患者・家族とのコミュニケーション
- 私の失敗と周囲の反応
- 長期入院で精神的に不安定になっている患者への声かけに戸惑い、マニュアル通りの対応しかできなかった。結果、患者から「あなたじゃ話にならない」と言われてしまい、先輩にフォローしてもらうことに。ご家族への退院支援に関する説明も要領を得ず、不信感を与えてしまった。
- 当時の心境
- 麻酔で眠っている患者と接することが主だったため、意識のある患者やご家族と継続的な信頼関係を築くことの難しさに直面しました。自分のコミュニケーション能力のなさに絶望し、人と関わること自体が苦痛に感じられました。



これらの経験は、ほんの一部です。毎日のように小さな失敗と反省を繰り返し、「私は看護師に向いていないのかもしれない」と本気で悩み続けました。
看護師4年目が仕事できないと感じる主な理由
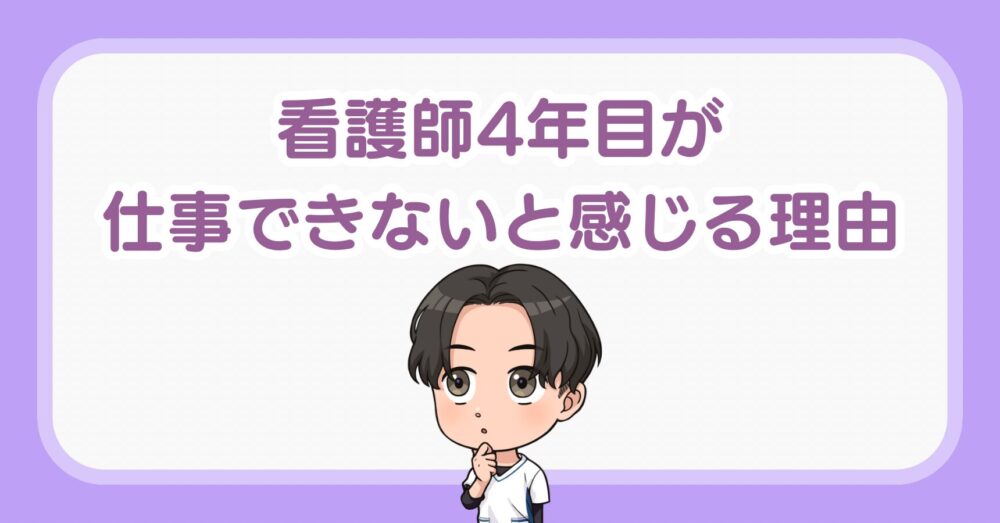
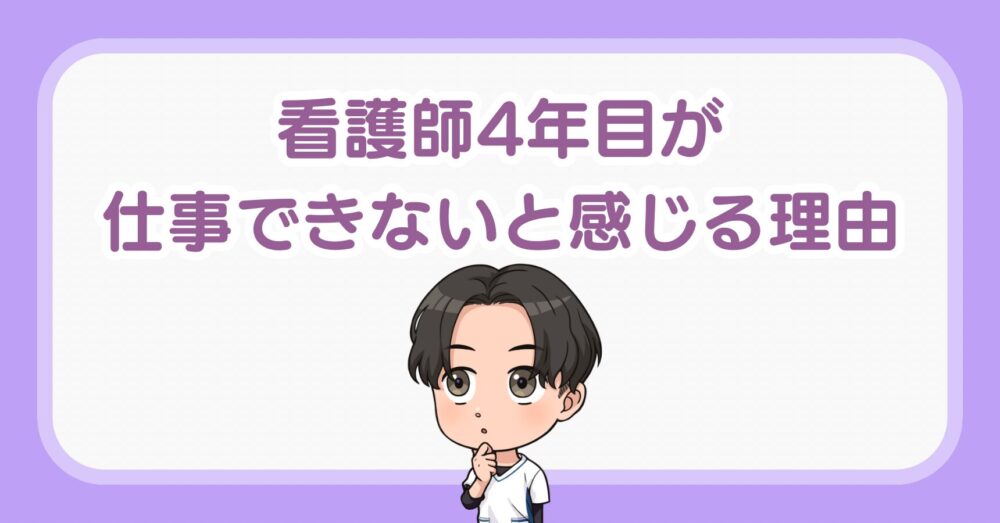
「もう4年目なのに、どうしてこんなに仕事ができないんだろう…」と感じてしまうのは、決して珍しいことではありません。実は、看護師4年目というキャリアステージは、多くの人が同じような壁にぶつかりやすい時期です。ここでは、なぜ4年目の看護師が「仕事ができない」と感じてしまうのか、その主な理由を3つの側面から深掘りしていきます。
- 業務の幅が広がり求められるレベルが上がる
- 同期や後輩との比較で焦りが生じる
- 周囲からの評価やプレッシャー
業務の幅が広がり求められるレベルが上がる
4年目になると、単に日々の業務をこなすだけではなく、より高度で複雑な役割を期待されるようになります。新人や若手の頃とは責任の重さも、求められるスキルも格段に上がり、その変化に戸惑ってしまうことは少なくありません。
一人前として扱われ、任される責任が重くなる
入職して3年間で基本的な看護業務は一通り経験し、周囲からは「一人前の看護師」として認識され始めます。その結果、これまで先輩のサポートのもとで行っていた業務も、基本的には一人で完結させることが求められます。例えば、緊急入院の受け入れや、重症度の高い患者の担当、急変時の初期対応など、判断の正確さとスピードが問われる場面が増え、その責任の重さにプレッシャーを感じてしまうのです。
リーダー業務や後輩指導など役割の変化
4年目は、プレイヤーとしての役割に加え、チーム全体を見る「リーダー」や、新人を育てる「プリセプター(実地指導者)」といった役割を任され始める時期です。自分の業務に加えて、チーム全体の進捗管理やメンバーへの指示出し、後輩の業務フォローや精神的なサポートまで担うことになります。これらのマネジメントや教育に関するスキルは、これまでの臨床スキルとは全く別物です。新たな役割にうまく適応できず、「自分はリーダーに向いていない」「教えるのが下手だ」と感じ、仕事ができないという自己評価に繋がってしまうのです。
求められるアセスメント能力の高度化
若手の頃は、バイタルサインの異常を報告するなど、目の前の事象への対処が中心でした。しかし4年目になると、そのデータから患者の状態が今後どのように変化していくかを予測する「臨床推論」や、複数の情報を統合して看護上の問題を的確に捉える高度な「アセスメント能力」が求められます。根拠に基づいた的確な判断ができないと、先輩から「なんでこう考えたの?」と指摘されたり、医師との情報共有がスムーズにいかなかったりして、知識や思考力の不足を痛感する場面が増えてきます。
同期や後輩との比較で焦りが生じる
自分では精一杯やっているつもりでも、周りのスタッフと自分を比べてしまい、焦りや劣等感を抱いてしまうのも4年目特有の悩みです。特に、身近な存在である同期や後輩の成長が、かえって自分を追い詰める原因になることがあります。
活躍する同期とのスキル差への劣等感
同じスタートラインにいたはずの同期が、リーダー業務をそつなくこなしていたり、難易度の高い看護技術を習得していたりする姿を見ると、「自分はなんて要領が悪いんだろう」「同期に比べて成長が遅い」と落ち込んでしまいがちです。特に、自分が苦手としている業務を同期が難なくこなしている場面に遭遇すると、その差をまざまざと見せつけられたように感じ、自信を失ってしまいます。
優秀な後輩の存在がプレッシャーに
自分たちが新人だった頃よりも飲み込みが早く、積極的に質問してくる優秀な後輩の存在も、プレッシャーの一因です。後輩から受けた質問に的確に答えられなかったり、後輩の方が知識が豊富だと感じたりすると、「先輩として頼りないと思われているのではないか」「追い抜かれてしまうのではないか」という焦りが生まれます。



指導する立場でありながら、内心では後輩の優秀さに引け目を感じてしまうこともあります。
周囲からの評価やプレッシャー
4年目という立場は、本人だけでなく周囲からの見られ方も大きく変わる時期です。その期待と現実の自分とのギャップが、大きな精神的負担となることがあります。
「4年目だからできて当たり前」という無言の圧力
先輩や上司から「もう4年目でしょ?」「これくらいは分かるよね?」といった言葉をかけられたり、そのような雰囲気を感じ取ったりすることが増えます。周囲からの「できて当たり前」という期待は、時に大きなプレッシャーとなり、些細なミスでも過剰に自分を責める原因になります。この無言の圧力が、新しいことへの挑戦をためらわせたり、分からないことを素直に質問できなくさせたりする悪循環を生むこともあります。
「中堅」という立場での板挟み
看護師4年目は、先輩看護師と後輩看護師の間に立つ「中堅」という難しい立場に置かれます。上からはチームへの貢献を求められ、下からは指導やサポートを期待される、いわば「板挟み」の状態です。双方の期待に応えようとするあまり、自分のキャパシティを超えてしまい、結果的にどちらの役割も中途半端になってしまうことがあります。



こうした状況が、「自分は調整役も務まらない、仕事のできない人間だ」という無力感につながります。
看護師4年目には、役割や責任、人間関係の変化に伴う特有の悩みが集中します。以下の表は、看護師のキャリアステージにおける役割の変化をまとめたものです。
| 時期 | 主な役割・業務 | 求められる能力・スキル | 感じやすい悩み |
| 1~3年目(若手) | 日常業務の習得 指示されたケアの実践 | 基本的な看護技術 報告・連絡・相談(報連相) | 業務に慣れることへの不安 インシデントへの恐怖 |
| 4年目以降(中堅) | チームリーダー 後輩指導(プリセプター) 委員会活動 複雑な症例の担当 | 応用的な看護実践力 アセスメント・臨床推論能力 多重課題処理能力 リーダーシップ・指導力 | 責任の重さへのプレッシャー 役割の変化への戸惑い 同期・後輩との比較による焦り |
こうした4年目特有の課題は、多くの看護師が経験する成長過程の一部です。まずは「悩んでいるのは自分だけではない」と知り、客観的に自分の状況を把握することが、乗り越えるための第一歩となります。
看護師が4年目で仕事ができないと感じたときの具体的な乗り越え方
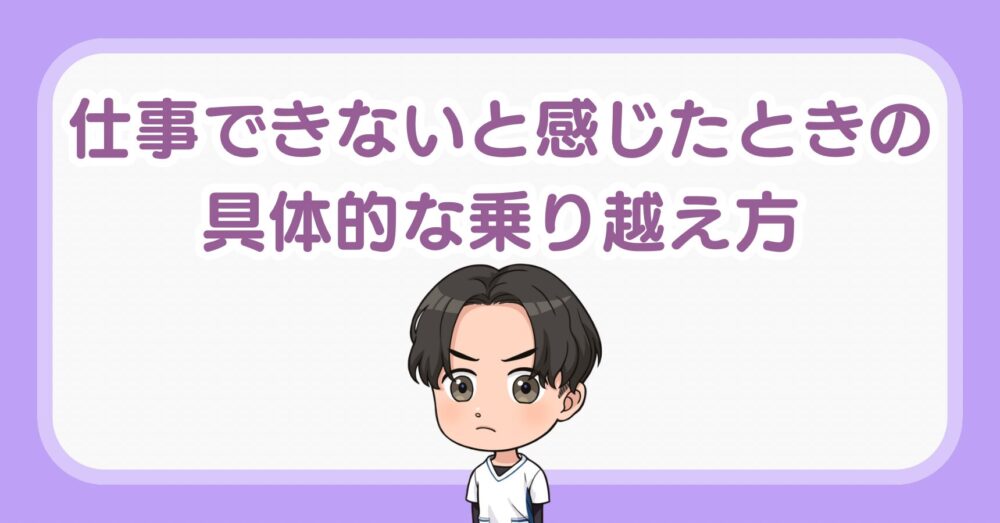
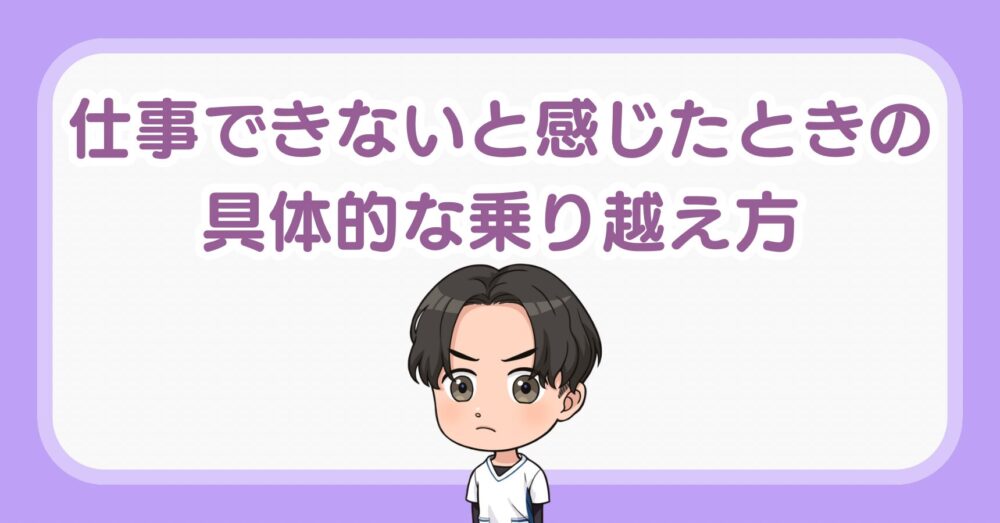
ここでは、つらい時期を乗り越え、再び自信を持って働くための具体的な方法を4つご紹介します。
- 自己評価をやめて客観的なフィードバックをもらう
- 先輩や信頼できる上司に素直に相談する
- 自分の得意分野を見つけて強みにする
- 勉強会や研修に積極的に参加する
自己評価をやめて客観的なフィードバックをもらう
「仕事ができない」という感覚は、自分自身の厳しい自己評価から生まれていることが少なくありません。自分一人で悩んでいると、できていない部分ばかりに目が行きがちです。まずは主観的な思い込みから離れ、客観的な視点を取り入れることから始めましょう。
信頼できるプリセプターや指導者、先輩看護師に「今の私の看護技術で、改善すべき点はありますか?」「〇〇さんのアセスメントについて、もっと良い視点があれば教えていただきたいです」など、具体的な業務を挙げてフィードバックを求めてみてください。勇気がいる行動ですが、自分が思っているほど評価が低くないことに気づいたり、具体的な改善点が見つかったりするはずです。



もらったアドバイスは必ずメモに取り、具体的な行動目標に落とし込んでいきましょう。
フィードバックをもらう際は、たとえ耳の痛い内容であっても、まずは「ありがとうございます」と感謝を伝え、素直に受け止める姿勢が大切です。客観的な評価を道しるべにすることで、漠然とした不安が解消され、着実に成長へと繋がります。
先輩や信頼できる上司に素直に相談する
一人で悩みを抱え込むことは、精神的な負担を増大させ、視野を狭めてしまいます。4年目という立場上、「今さら聞けない」「できないと思われたくない」という気持ちが先行しがちですが、思い切って先輩や上司に相談してみましょう。
相談相手は、自分の話を親身に聞いてくれる人や、同じような経験を乗り越えてきたであろう中堅以上の看護師が適しています。「少しお時間よろしいでしょうか。最近、業務のことで悩んでいまして…」と切り出し、具体的にどの業務で、どのように困っているのか、そしてどう感じているのかを正直に話してみてください。
経験豊富な先輩や上司は、自身が気づかなかった視点からアドバイスをくれたり、部署全体でサポートする体制を整えてくれたりする可能性があります。



何より、自分の状況を理解してくれる存在がいるというだけで心が軽くなります。
自分の得意分野を見つけて強みにする
「仕事ができない」と感じているときは、自分の苦手なことや失敗したことばかりに意識が向きがちです。誰もが必ず得意なことや、人よりスムーズにできることがあるはずです。一度立ち止まり、自分の得意分野=強みを見つけ、そこを伸ばすことに意識を向けてみましょう。
例えば、以下のようなことが挙げられます。
- 患者やそのご家族とのコミュニケーションが上手で、信頼関係を築くのが得意
- 電子カルテの記録が誰よりも正確で分かりやすい
- 急変時でも冷静に、かつ迅速に必要な物品を準備できる
- 後輩への指導が丁寧で、分かりやすいと褒められたことがある
- カンファレンスの資料作成や情報収集が得意
どんなに小さなことでも構いません。自分の強みを認識し、その分野で積極的に行動することで、自信を取り戻すきっかけになります。以下の表を参考に、自分の強みをキャリアに活かす方法を考えてみましょう。
- 患者とのコミュニケーション
- 入院時のオリエンテーションや退院指導を積極的に担当する。患者さんの心理的ケアに関する係や委員会に参加する。
- 記録の正確性・分かりやすさ
- 記録委員になる。後輩のカルテをチェックし、より良い書き方をアドバイスする。
- 特定の看護技術(採血・ルート確保など)
- 難しい症例の際に率先して実施する。後輩向けの技術練習会を企画・担当する。
- 後輩指導
- プリセプターや実習指導者になることを上司に相談する。部署内の勉強会で講師を務める。
苦手なことを克服する努力も大切ですが、まずは自分の強みを活かしてチームに貢献することで、自己肯定感を高め、仕事へのモチベーションを回復させましょう。
勉強会や研修に積極的に参加する
知識や技術の不足が不安の原因であるならば、学習によってその不安を直接解消することができます。院内の勉強会はもちろん、院外の学会や研修にも積極的に参加し、自分の知識をアップデートしていきましょう。
自分の興味がある分野や、苦手だと感じている領域のセミナーに参加することで、新たな知識を得られるだけでなく、他施設の看護師と交流する良い機会にもなります。同じような悩みを持つ仲間と出会えたり、目標となる看護師に出会えたりすることもあります。
どこで研修を探せばよいか分からない場合は、まずは日本看護協会の研修情報ページや、所属している学会のウェブサイトなどをチェックしてみるのがおすすめです。学んだことを日々の看護実践に活かすことで、知識はより確かなものとなり、自信へと繋がっていくでしょう。
私が実践した看護師4年目の「仕事ができない」を克服した具体的な行動
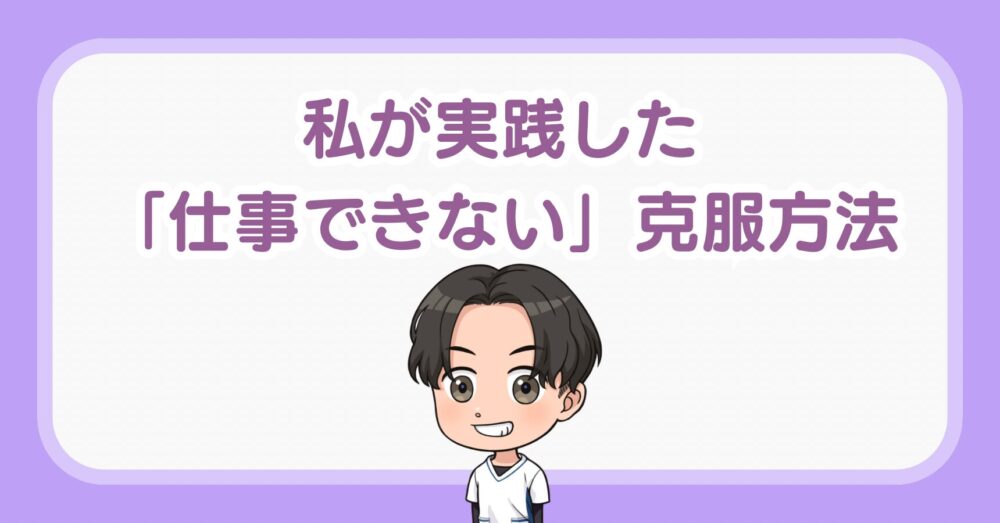
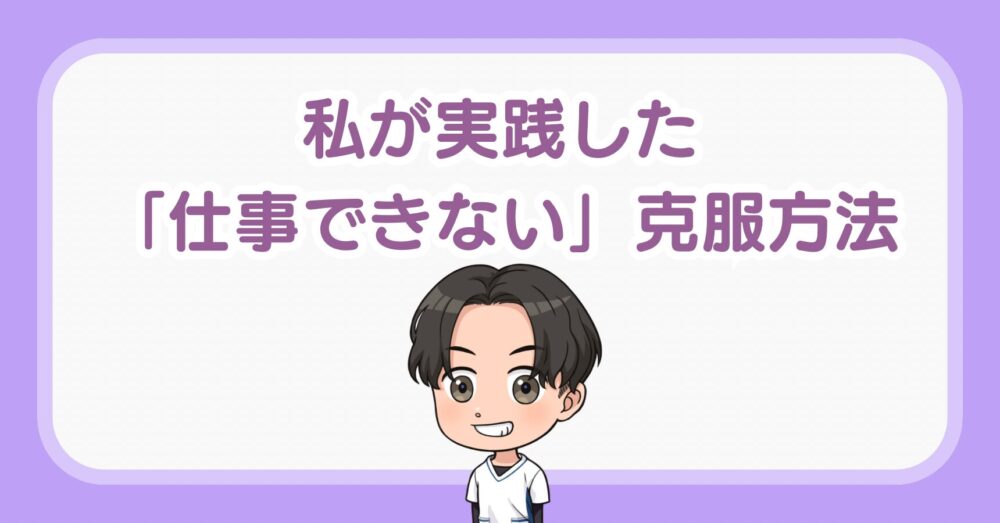
ここでは、オペ室から病棟へ異動し、まさに「何もできない」状態だった私が、実際に試行錯誤しながら実践し、効果があった具体的な行動を3つの側面に分けて詳しくお伝えします。すぐに真似できることばかりなので、ぜひ明日からの業務に取り入れてみてください。
- 病棟業務に馴染むために行った具体的な工夫
- 効率的な仕事の進め方と時間管理術
- 先輩看護師との関係を改善するためのコミュニケーション方法
病棟業務に馴染むために行った具体的な工夫
オペ室での経験はあっても、病棟業務はほぼ未経験。患者の1日の流れも、ケアの優先順位も、物品の場所すら分かりませんでした。そんな私がまず取り組んだのは、徹底的な「インプット」と「可視化」です。
自分専用の「病棟マニュアル」を作成する
病院で使われるマニュアルだけでは、現場の細かな動きは分かりません。そこで、ポケットに入るサイズの小さなノートを常に持ち歩き、自分だけのマニュアルを作成しました。



誰かに見せるためではなく、自分が見てすぐに理解できることが目的です。
- 物品の場所を写真とイラストで記録
- よく使う物品や緊急カートの中身など、どこに何があるかを簡単なイラストや言葉でメモしました。特に、病棟によって異なる物品の配置は、写真に撮って(許可を得て)ノートに貼ることもありました。
- 病棟の1日のタイムスケジュールを記録
- 朝の申し送りから、検温、ケア、配薬、記録、夜の申し送りまで、先輩看護師の動きを観察し、時間ごとの業務内容を時系列で書き出しました。
- 「暗黙のルール」を言語化
- 「〇〇先生への報告は、まず△△看護師を通す」「この処置の準備は、この手順が一番早い」といった、マニュアルには載っていない独自のルールやコツを、聞いたその場でメモしました。
この自分専用マニュアルのおかげで、次に何をすべきか迷う時間が減り、少しずつ業務の全体像を掴めるようになりました。
担当患者の疾患とケアを「線」で結ぶ勉強法
ただ疾患について勉強するだけでは、臨床に活かせませんでした。そこで、担当患者一人ひとりに焦点を当て、「なぜこのケアが必要なのか?」を常に考えるように意識を変えました。
例えば、心不全の患者なら、「なぜ水分制限があるのか?」「なぜ毎日体重を測るのか?」その根拠を解剖生理から学び直し、アセスメントに繋げます。参考書としては、イラストが多く視覚的に理解しやすい「病気がみえる」シリーズなどを活用し、得た知識を担当患者のカルテ情報と照らし合わせながらノートにまとめていきました。



この「知識」と「実践」を結びつける作業が、アセスメント能力の向上に直結したと感じています。
効率的な仕事の進め方と時間管理術
業務に慣れないうちは、時間に追われて残業ばかり。精神的にも体力的にも追い詰められました。そこで、業務の「見える化」と「優先順位付け」を徹底することで、時間管理のスキルを磨きました。
≫看護師のAppleWatch活用法!現場で効率化した実体験
タスクを書き出し優先順位を明確にする
出勤後、まずはその日にやるべきタスクをすべて情報収集用紙の余白に書き出しました。そして、それぞれのタスクを緊急度と重要度で分類し、取り組む順番を決めるのです。



いわゆる「時間管理のマトリクス」を頭の中で作るイメージです。
- 第1領域(緊急かつ重要)
- すぐに対応すべき最優先事項です。急変対応、術後患者のバイタルサイン測定、指示された時間指定の薬剤投与などが挙げられます。
- 第2領域(緊急でないが重要)
- 計画的に行うべき事項です。退院指導の計画、カンファレンスの準備、後輩への指導、自己学習などが挙げられます。
- 第3領域(緊急だが重要でない)
- すぐに対応すべきだが、他者に依頼できる可能性もある事項です。急な問い合わせ電話への対応、他部署からの依頼(内容による)などが挙げられます。
- 第4領域(緊急でも重要でもない)
- 後回しにする、またはやらないことを検討する事項です。過剰な情報収集、重要度の低い雑談などが挙げられます。
これを意識するだけで、本当にやるべきことが明確になり、焦りが大幅に軽減されました。特に、第2領域の業務に計画的に時間を使うことが、長期的なスキルアップと自信の回復に繋がりました。
「ついで業務」で動線を最適化する
病棟内を何度も行き来するのは、時間と体力の無駄です。そこで、一回の訪室で複数のケアを済ませる「ついで業務」を常に意識しました。
例えば、患者の病室に点滴交換で訪れた際に、「ついでに」環境整備を行い、排泄の有無を確認し、必要なケア用品が揃っているかチェックする、といった具合です。これを実践するために、訪室前に「この患者に今日必要なケアは何か」をリストアップし、必要な物品をまとめて持っていくようにしました。



細かいことですが、動線を意識することで歩く距離と時間が短縮され、他の業務に時間を充てられるようになりました。
先輩看護師との関係を改善するためのコミュニケーション方法
私も「仕事ができない」と思われているのではないかという不安から、先輩への報告・連絡・相談(報連相)が怖くなってしまう時期がありました。しかし、報連相の遅れは、インシデントに直結します。そこで、私はコミュニケーションの「型」を作ることで、心理的なハードルを下げました。
報連相は「結論」から。SBAR(エスバー)を活用する
忙しい先輩に状況を的確に伝えるため、医療現場で用いられる報告フレームワーク「SBAR」を意識しました。
- S (Situation) 状況
- 例:「〇号室の〇〇さん(患者名)の件で報告です。先ほどから38.5℃の発熱があります」
- B (Background) 背景
- 例:「〇〇さんは△△の疾患で入院中です。昨日までは熱はありませんでした」
- A (Assessment) 評価
- 例:「呼吸状態に変化はありませんが、悪寒を訴えています。感染の兆候かもしれません」
- R (Recommendation) 提案
- 例:「医師に報告しようと思いますが、よろしいでしょうか。その前に〇〇の検査準備をしておきますか?」
このように型に沿って話すことで、要点が整理され、簡潔かつ的確に情報を伝えられるようになりました。



「自分のアセスメントと提案」まで伝えることで、丸投げではなく、主体的に考えている姿勢も示すことができます。
質問の仕方を工夫して「教えたい」と思わせる
ただ「分かりません」と質問するのではなく、自分なりに調べたり考えたりした上で質問するように心がけました。先輩も「どこでつまずいているのか」が分かり、的確なアドバイスをしやすくなります。
| 改善前の質問(NG例) | 改善後の質問(OK例) |
| 「この薬、どうやって投与するんですか?」 | 「この薬の投与方法についてですが、マニュアルで確認したところ〇〇と記載がありました。ただ、この患者さんは腎機能が低下しているので、速度を調整すべきか迷っています。先輩ならどう判断されますか?」 |
| 「どうしたらいいですか?」 | 「〇〇さんのケアについて、A案とB案を考えました。私は〇〇という理由でA案が良いと思いますが、ご意見をいただけますか?」 |
自分で考えた過程を示すことで、学習意欲をアピールでき、先輩も「この後輩は成長しようとしている」と感じて、より丁寧な指導をしてくれるようになりました。



小さなことでも、教えてもらったら必ず感謝を伝えることも、良好な関係を築く上で非常に重要です。
看護師4年目の「仕事ができない」悩みがキャリアの強みに変わった話
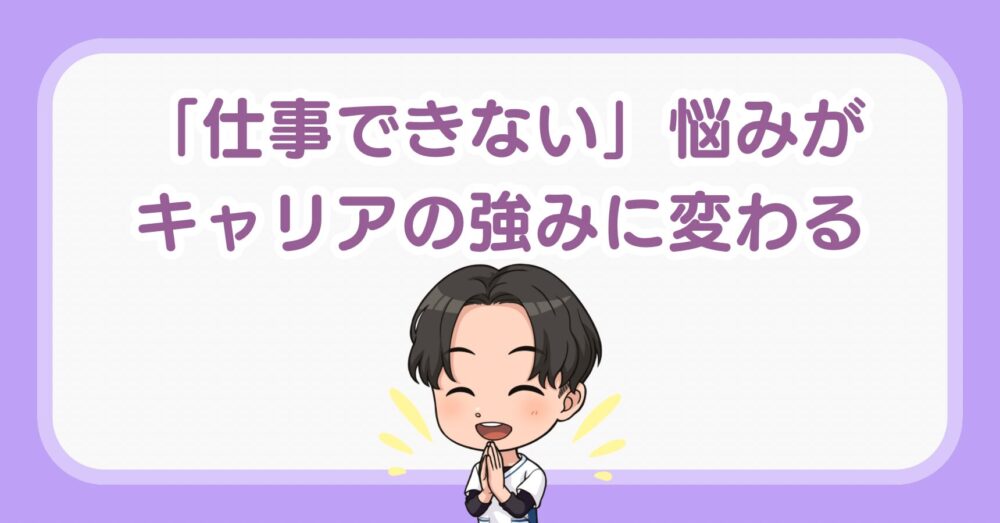
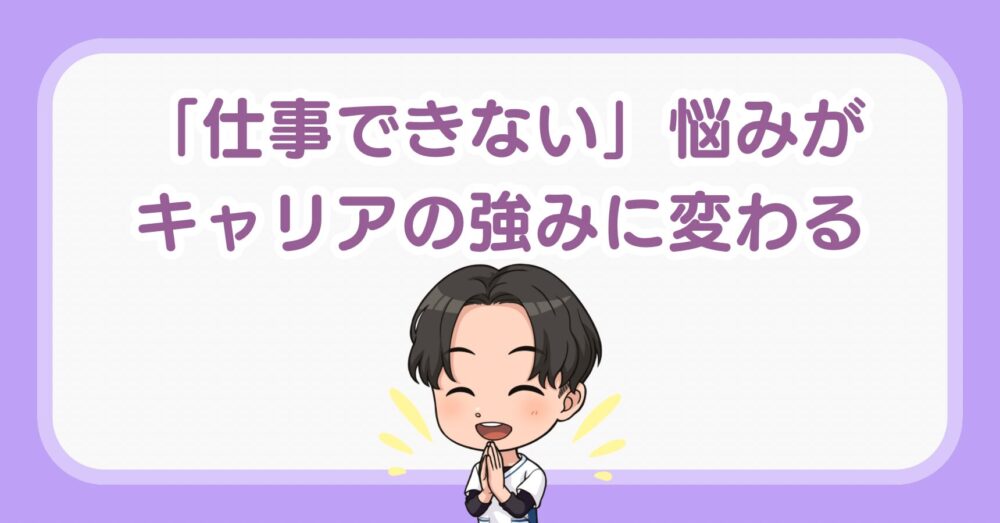
「もう看護師を辞めたい…」と本気で思い詰めていた4年目の自分。今振り返ると、あの時の苦しい経験こそが、現在の私を支える最大の糧となり、キャリアの強みに変わったと断言できます。
- 病棟未経験が強みとなった主任への道のり
- 悩んだ経験が後輩指導に活きている現在
病棟未経験が強みとなった主任への道のり
急性期病棟や精神科病院での経験を経て、私が選んだのは介護施設でした。介護士だったこともあり、いつかは福祉の世界で働くことは視野に入れていました。でも正直に言えば、当時は「病棟から逃げ出したい」という気持ちが大きかったかもしれません。



しかし、この環境の変化が、私の看護師人生における大きな転機となったのです。
介護施設では、病院とは異なる視点やスキルが求められました。治療が中心の病院に対し、介護施設は利用者の「生活」に寄り添い、その人らしい最期までを支える場所。病棟での経験が浅かった私は、ある意味「まっさらな状態」でした。それが、意外な形で強みとして発揮されたのです。
- 固定観念のない視点
- 「病院ではこうだった」という先入観がなかったため、施設のやり方を素直に吸収し、純粋に「どうすればもっと良くなるか?」を考えられました。例えば、申し送りの効率化や記録方法の見直しなど、前例にとらわれない改善提案ができました。
- 多様な経験の統合
- オペ室で培った「徹底した安全管理と準備の重要性」と、病棟で痛感した「多重課題への対応とコミュニケーションの難しさ」。この両極端ともいえる経験が、介護施設という多職種が連携する現場で、物事を多角的に捉える力になりました。医師、介護スタッフ、リハビリ専門職など、それぞれの立場を想像し、円滑な連携のハブとなる役割を担うことができたのです。
- 謙虚に学ぶ姿勢
- 「病棟のことは詳しくない」という自覚があったからこそ、誰に対しても謙虚に教えを請うことができました。年下の介護福祉士さんにも「この方のケアで大切なことは何ですか?」と素直に聞く。この姿勢が、スタッフとの信頼関係を築く上で非常に重要でした。
これらの経験を積み重ねる中で、私は業務改善チームのリーダーを任され、最終的に主任への昇進を打診されました。かつて「仕事ができない」と自分自身で思い込んでいた私が、チームをまとめる立場になったのです。
≫看護師が主任になると年収はいくら上がる?現役主任の筆者が明かす給与の実態
私のキャリアパスと、そこで得られたスキルをまとめると、以下のようになります。
| 経験した職場・役職 | 期間(目安) | 主な役割と業務 | 現在のキャリアに繋がった強み |
| 急性期病院(オペ室) | 1〜3年目 | 手術介助、器械準備、術後管理 | 正確性、危機管理能力、チーム医療における役割遂行力 |
| 急性期病院(病棟) | 4年目 | 一般病棟業務、多重課題への対応 | 挫折経験からくる共感力、患者・家族とのコミュニケーションの重要性の認識 |
| 精神科病院 介護施設(スタッフ) | 5年目〜 | 利用者の健康管理、生活支援、多職種連携 | マネジメント視点の獲得、個別性を尊重したケアプランニング、業務改善提案力 |
| 介護施設(主任) | 現在 | スタッフの指導・管理、施設全体の運営サポート | リーダーシップ、後輩指導力、多様な経験を統合し組織を動かす力 |



あの4年目の挫折がなければ、私はオペ室の専門性を深める道しか知らなかったかもしれません。
回り道に思えた経験こそが、私の視野を広げ、キャリアの可能性を切り拓いてくれました。
悩んだ経験が後輩指導に活きている現在
主任となった今、私が最も大切にしているのが後輩指導です。そして、ここでも4年目の「仕事ができない」と悩んだ経験が、私の大きな支えとなっています。
ミスをして落ち込んでいるスタッフ、思うように成長できず焦っている後輩を見ると、かつての自分と重なります。だからこそ、私は頭ごなしに叱責したり、正論を振りかざしたりすることは決してしません。彼らの辛さや悔しさが、痛いほどわかるからです。
私が指導の際に心がけているのは、以下の3つです。
- 「Why(なぜ)」ではなく「How(どうすれば)」を一緒に考える
- 「なぜできなかったの?」と原因を追及するのではなく、「次はどうすればできるかな?」と一緒に解決策を考えます。これにより、相手は前向きな思考に切り替えやすくなります。
- 自分の失敗談を話す
- 完璧な上司を演じるのではなく、「私も4年目の時、もっとひどい失敗をしたよ」と正直に話します。すると、後輩は安心し、「自分だけじゃないんだ」と心を開いてくれることが多いです。
- 成長を具体的にフィードバックする
- 「前はできなかった〇〇が、今日はできていたね」「〇〇さんへの声かけ、すごく良かったよ」など、小さな成長も見逃さずに言葉で伝えます。これは、自信を失っているスタッフにとって、何よりの励みになります。
私自身の「できなかった」経験が、その理念を血の通った実践として行う上で大きな力になっています。順風満帆なエリート看護師ではなく、挫折を知るリーダーだからこそ、多様なスタッフが安心して働けるチームを作ることができると信じています。
看護師4年目の「仕事できない」悩みが克服できないときは?
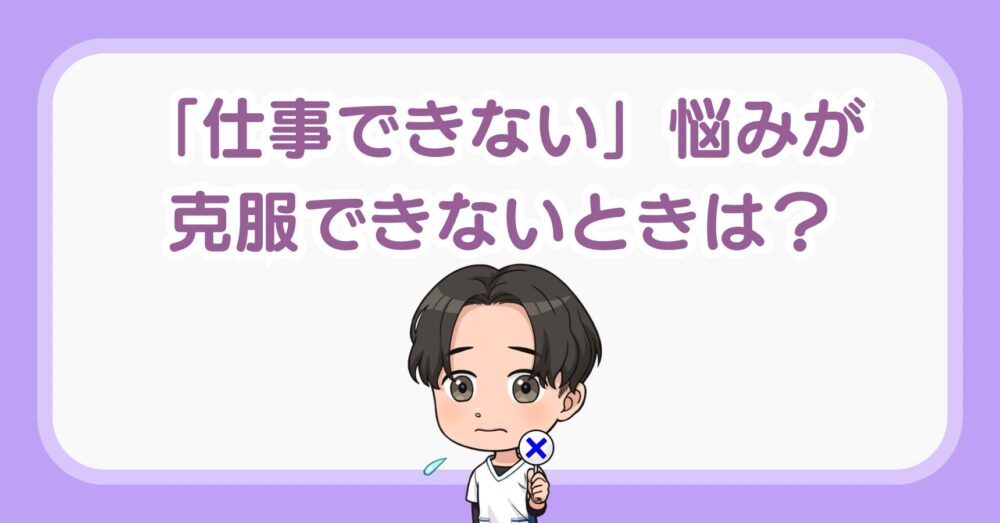
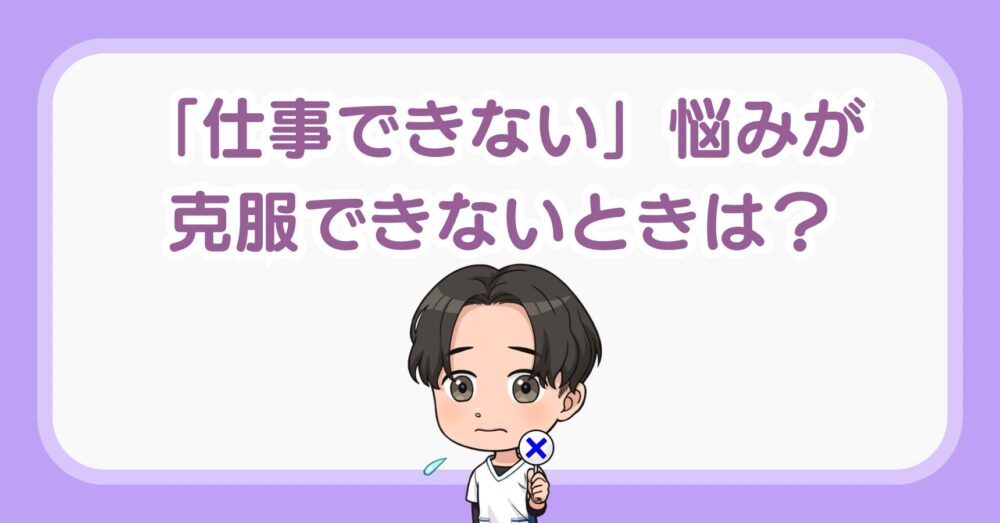
これまで紹介した方法を試しても、「やっぱり仕事ができない…」という苦しい気持ちから抜け出せない方もいるかもしれません。努力を続けても状況が改善しないとき、それは自分一人のせいではない可能性が高いです。



自分を責め続けるのではなく、少し視点を変えて、今の環境やこれからのキャリアについて考えてみましょう。
- 職場環境が合わない可能性を考える
- 転職を前向きに検討するメリット
職場環境が合わない可能性を考える
「仕事ができない」という悩みの根源は、能力不足ではなく今の職場環境とのミスマッチにあるのかもしれません。個人の努力には限界があります。もし、以下のような状況に当てはまるなら、環境を変えることを検討すべきサインです。
- 慢性的な人手不足で、十分な指導やサポートを受けられない
- 質問や相談がしにくい雰囲気があり、一人で抱え込んでしまう
- パワハラやいじめなど、人間関係に深刻な問題がある
- 病院の方針や看護観が、自分の目指す看護と大きくかけ離れている
- 心身の不調(不眠、食欲不振、出勤前の腹痛や動悸など)が続いている
≫スタッフがすぐ辞めるクリニックの共通点と看護師の職場選びのポイントを解説!
このような環境で我慢し続けることは、自信を失うだけでなく、心身の健康を損ない、燃え尽き症候群(バーンアウト)につながる危険性もはらんでいます。



自分のキャリアと心身を守るためにも、環境を見直すことは非常に重要な選択です。
転職を前向きに検討するメリット
もし現在の職場が合わないと感じるなら、転職は「逃げ」ではなく、自分自身が輝ける場所を見つけるための「戦略的なキャリアチェンジ」です。特に、一定の基礎スキルと経験を積んだ4年目というタイミングは、転職市場において有利に働くことが多いです。
4年目看護師の転職がもたらすメリット
転職には、今の悩みを解決し、新たな可能性を広げる多くのメリットがあります。
- 心機一転、再スタートが切れる
- 「仕事ができない」という周囲からのレッテルや、自分自身に染み付いたネガティブな自己評価をリセットできます。新しい環境で、新たな人間関係を築きながら、もう一度自信を取り戻すチャンスです。
- 自分に合った環境を選べる
- 教育体制が整っている、人間関係が良好、残業が少ない、自分の興味のある分野に特化しているなど、現職場の不満点を解消できる職場を自ら選ぶことができます。
- キャリアの可能性が広がる
- 急性期病棟だけでなく、クリニック、訪問看護、介護施設、企業など、看護師の資格を活かせるフィールドは多岐にわたります。4年間の経験を土台に、新たな分野へ挑戦することで、自分の新たな強みを発見できます。
- 客観的に自分の市場価値を知れる
- 転職活動を通して、自分の4年間の経験やスキルが社会でどのように評価されるのかを客観的に知ることができます。経験者として評価され、給与や待遇が改善するケースも少なくありません。
転職先の選択肢を広げてみよう
「病棟業務が苦手」と感じていても、看護師としての価値が下がるわけではありません。自分の特性や希望に合った職場は必ず存在します。視野を広げて、多様な働き方を検討してみましょう。
»看護師の働き方を徹底解説|3つの職場を経験した筆者のリアル比較と選び方
- クリニック
- 夜勤がなく、カレンダー通りの休みが多い。外来業務が中心で、比較的落ち着いて患者さんと関われる。
ワークライフバランスを重視したい人、プライベートの時間を確保したい人におすすめ。
≫クリニックに勤務する看護師の仕事内容がつらい理由【対処法も詳しく解説!】 - 訪問看護ステーション
- 利用者さんの自宅に訪問し、生活に密着したケアを提供。主体的な判断力やアセスメント能力が求められる。
1対1でじっくり向き合う看護がしたい人、自律的に働きたい人におすすめ。
≫【需要拡大】訪問看護とは?在宅患者を支える看護師の役割と仕事内容を解説 - 介護施設(特養・老健など)
- 医療行為は限定的だが、利用者の生活全般を支える視点が重要。多職種連携の中心的な役割を担う。
高齢者看護に興味がある人、穏やかな環境で長期的に関わるケアがしたい人におすすめ。
≫介護施設の看護師の役割と働き方を経験者が解説|施設別の具体例とリアルな本音 - 企業(産業保健師・治験関連など)
- 社員の健康管理やメンタルヘルスケア、新薬開発のサポートなど、臨床現場とは異なる視点で貢献できる。
予防医療や研究分野に興味がある人、新しいキャリアに挑戦したい人におすすめ。
≫【産業看護師になるには?】仕事内容から必要なスキル、向いている人の特徴を解説!
具体的な転職活動の進め方
転職を決意したら、計画的に進めることが大切です。在職しながらでも、効率的に情報収集や準備を進める方法はあります。
看護師専門の転職エージェントを利用する
無料で登録でき、キャリアアドバイザーが希望や悩みにあった求人を紹介してくれます。非公開求人も多く、履歴書の添削や面接対策、給与交渉までサポートしてくれるため、初めての転職でも安心です。
ハローワーク(公共職業安定所)やeナースセンターを利用する
地域の求人が豊富で、公的な機関ならではの安心感があります。日本看護協会が運営する「eナースセンター」は、全国の看護職の求人情報を検索でき、相談員によるサポートも受けられます。
知人からの紹介(リファラル)
実際にその場で働く知人から、人間関係や残業の実態など、リアルな内部事情を得られるのがメリットです。ただし、入職後にミスマッチを感じた場合に断りづらいなどの側面も考慮しましょう。
転職は、看護師人生をより豊かにするためのポジティブな一歩です。自分を追い詰める前に、新しい可能性を探る勇気を持ってみてください。転職活動を始める前に、労働条件をしっかり確認することも大切です。厚生労働省が提供する「確かめよう労働条件」などのサイトも参考に、自分を守る知識を身につけておきましょう。
まとめ


看護師4年目で「仕事ができない」と悩むのは、決してあなただけではありません。業務の幅が広がり、求められるレベルが上がる中で焦りを感じるのは自然なことです。大切なのは、一人で抱え込まず、客観的な視点を取り入れたり、信頼できる人に相談したりして、具体的な行動に移すこと。
この記事で紹介したように、今の悩みや経験は、必ず自分の強みとなり、将来のキャリアに繋がります。もし環境が合わないと感じるなら、転職も一つの道です。
関連記事:看護師の私が転職で後悔した5つの原因|年収アップの裏でやらかした失敗と対策



まずは小さな一歩から、あなたに合った働き方を見つけていきましょう。
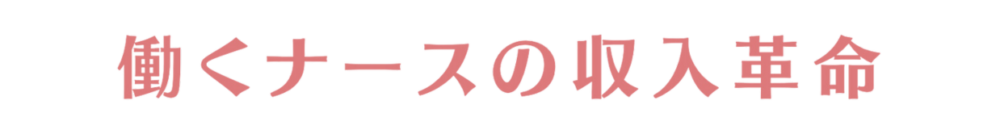
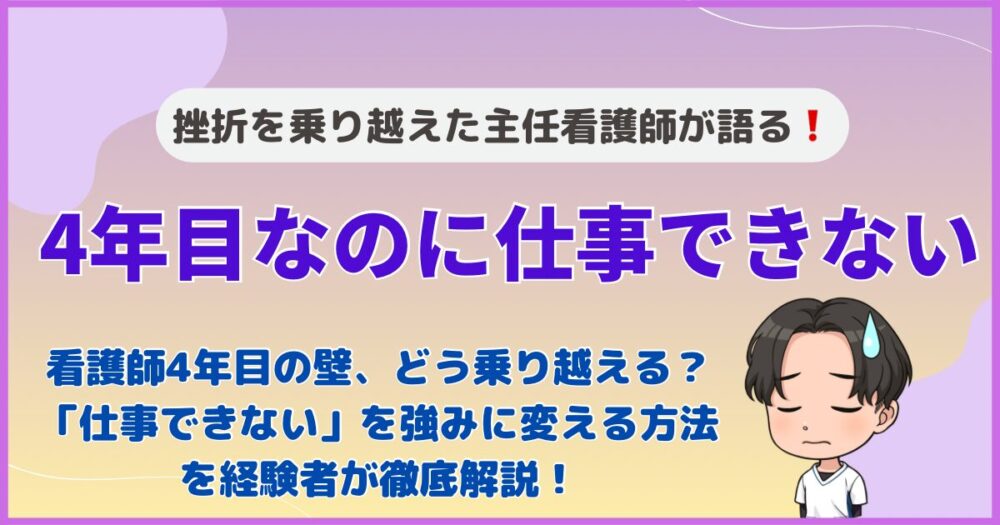

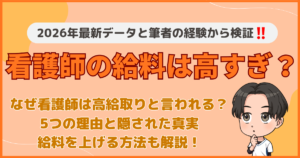
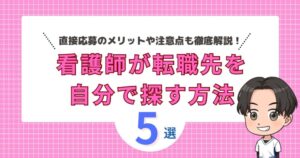
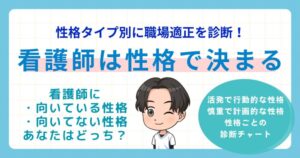

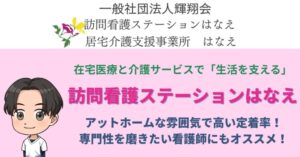
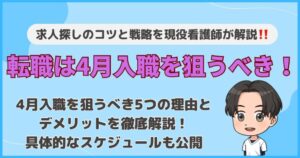
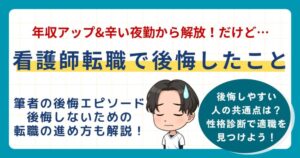
コメント