※この記事はプロモーションを含みます。
「排泄介助がつらい…そう感じるのは自分だけ?」
看護師として働く中で、排泄ケアに強い抵抗を感じたことはありませんか?
実は、におい・精神的負担・時間の制約など、「下の世話が苦手」と感じるのは決して珍しいことではありません。
 ryanta73
ryanta73現役ナースである私自身も、かつて同じ悩みに直面していました。
本記事では、
- 排泄介助をしたくないと感じる理由
- 現場での対処法(臭い対策・効率的なケアフロー)
- ストレスを減らせる診療科や職場の選び方
- 転職も視野に入れた具体的な行動プラン
まで、体験談を交えて詳しく解説します。
どうしても下の世話がつらいなら、排泄介助が少ない職場に転職するのが一番の近道です。とはいえ、自分で「下の世話が少ない求人」だけを探すのはかなり大変です。
そこでおすすめなのが、排泄介助が少ない求人を多く扱う転職エージェントに相談することです。
看護師が「下の世話をしたくない」と感じるのは自然なこと
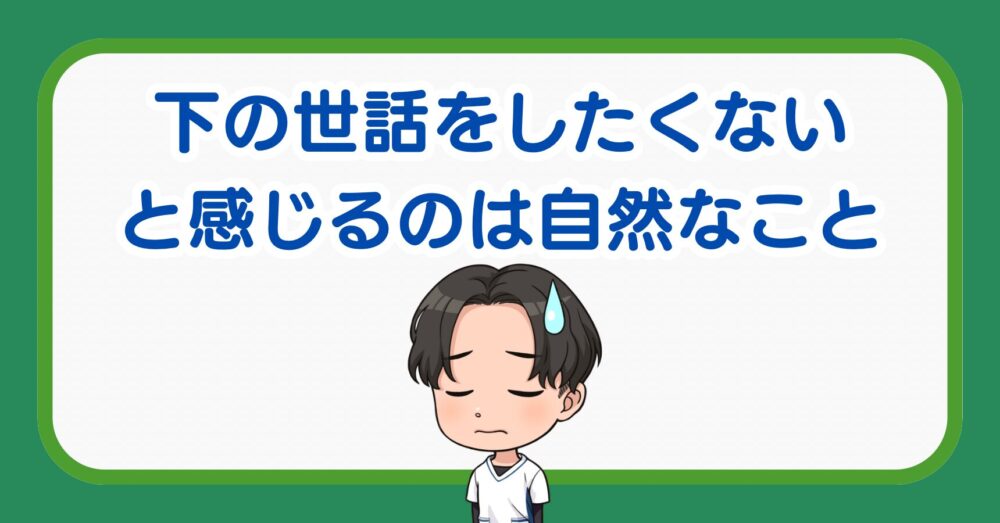
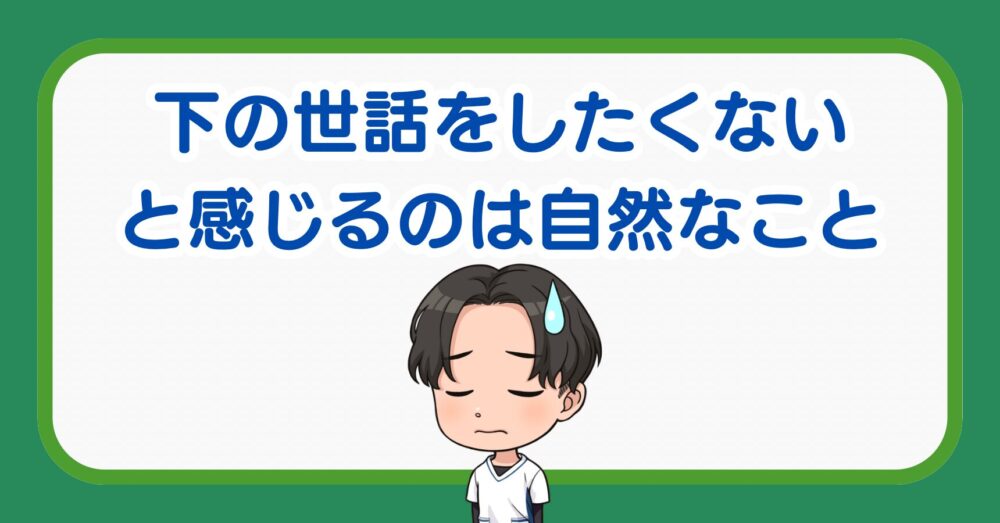
排泄介助やオムツ交換など、いわゆる「下の世話」は看護実践に欠かせないケアです。それでも多くの看護師が最初に抱くのは抵抗感や不安であり、これは生理的な反応としてごく自然なものです。
多くの看護師が下の世話を嫌う背景には、臭いや汚染に対する生理的負担だけでなく、患者の尊厳やプライバシーを守りながらケアを行う難しさが挙げられます。
- 多くの看護師が経験する「下の世話」への抵抗感
- 下の世話に抵抗を覚えるのは普通の感情
多くの看護師が経験する「下の世話」への抵抗感
看護師免許を取得したばかりの新人からベテランまで、下の世話を巡る心理的ハードルは共通しています。特に病棟デビュー直後は経験値が乏しく、臭い・汚染・時間的プレッシャーの三重苦が強いストレッサーとなります。一方、経験を積んでも「慣れ」だけでは解決しない倫理的ジレンマが残り続ける点も特徴です。
新人看護師の戸惑い
新人期は技術習得と感染対策の両立に追われがちで、排泄ケアに充てられる時間が限られることが多いです。マニュアルを頭で理解していても実践では「何から手を付ければ良いのか分からない」という状態に陥りやすいです。
経験年数によって変化する意識
中堅・ベテラン層になると技術的ストレスは軽減するものの、患者との信頼関係や尊厳保持を重視するあまり精神的負荷が増すケースがあります。特に認知症高齢者や意思疎通が難しい患者では、プライバシー保護と安全確保のバランスに悩むことが多いです
| キャリア段階 | 主な抵抗理由 | 必要とされる支援 |
| 新人 | 技術不足・手順が複雑 | プリセプターによる手技指導、シミュレーション教育 |
| 中堅 | 業務量増加・時間的余裕の欠如 | スタッフ配置の適正化、チームナーシング |
| ベテラン | 倫理的ジレンマ、身体的負担 | ローテーション勤務、身体介護機器の導入 |
下の世話に抵抗を覚えるのは普通の感情
排泄物に対する嫌悪感は進化心理学的にも本能的な防御反応とされ、看護師だけが特別に弱いわけではありません。東邦大学のホームページでも、「悪臭にさらされるとヒト唾液中のα-アミラーゼが増加することが明らかにされており、匂による不快感がストレス反応を誘発する可能性が示唆されている」とされています。この反応は感染リスクから自身を守るための生理的メカニズムであり、克服すべき欠点ではありません。
| 要因 | 具体例 | 対策の方向性 |
| 生理的 | 臭い・汚染への不快感 | 防臭マスク、早期廃棄ルートの確保 |
| 心理的 | 患者への申し訳なさ、羞恥心 | 声かけ・説明による相互理解 |
| 社会的 | 人手不足による時間圧迫 | チームケア、ICT導入で業務効率化 |
このように、下の世話に対して抵抗を抱くことは「プロ意識が低い」「向いていない」という評価には直結しません。むしろ患者の尊厳を守りたいという思いの裏返しである場合も多く、適切な知識・技術・組織的サポートによって負担を軽減しながら専門性を発揮することが可能です。
看護師がしたくない「下の世話」とは何を指すのか
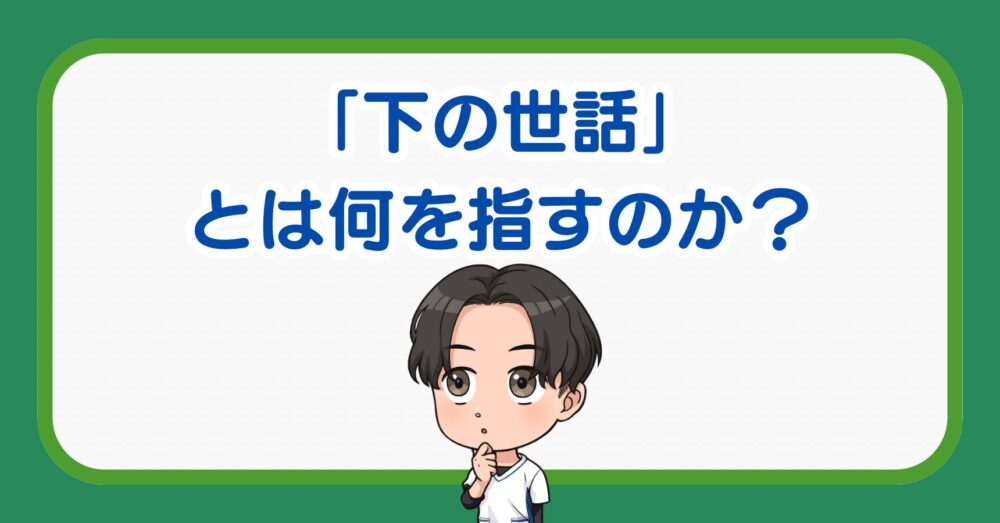
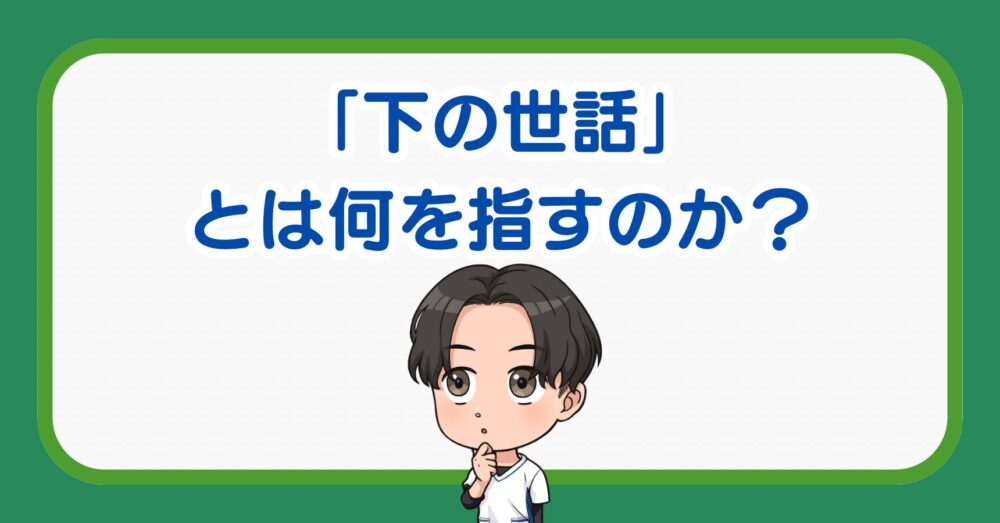
医療現場で「下の世話」と呼ばれるケアは、排泄介助を中心にADL(Activities of Daily Living)の中でも特にプライバシー保護と感染対策が求められる業務です。具体的にはオムツ交換、ポータブルトイレや車椅子でのトイレ誘導、陰部清拭、体位交換に伴う褥瘡予防、スキンケアなど多岐にわたります。いずれも患者の尊厳を守りつつ、適切な衛生管理を行う高度な専門性が必要とされます。



厚生労働省『新人看護職員研修ガイドライン』でも「排泄援助技術」が習得すべき臨床実践能力に挙げられています。
- 病棟でのオムツ交換とトイレ誘導の流れ
- 清拭や体位交換も含むケアの範囲
- 医療現場で求められる法的責任と倫理
- 便秘時に排便を促進する摘便処置
病棟でのオムツ交換とトイレ誘導の流れ
一般病棟や回復期リハビリ病棟では、高齢者や肢体不自由の患者が多く、オムツ交換やトイレ誘導は日勤・夜勤を問わず頻繁に発生します。排泄パターンをアセスメントし、声かけから後片付けまでをチームで連携しながら行うことが重要です。
オムツ交換の標準的手順
| ステップ | 具体的な行動 | 感染対策ポイント |
| 1.準備 | 手袋・エプロン装着、交換物品をベッドサイドへ配置 | 清潔域と不潔域を分ける |
| 2.交換 | 陰部観察→汚染オムツ除去→新しいオムツ装着 | 前方から後方へ拭き取り、褥瘡リスク部位を確認 |
| 3.後片付け | 汚染物は密閉廃棄、寝具を整える | 手指衛生を徹底 |
トイレ誘導のポイント
トイレ誘導では、患者の残存機能を活かすことが基本です。電動ベッドを最適な高さに調整し、歩行器や移乗ボードを使用しながら転倒リスクを低減します。タイミングは排泄リズムに合わせ、夜間は室内照明を弱めて覚醒を防ぐ工夫が推奨されます。



立ち上がりや歩行の安定性やズボンの上げ下げなどの動作から、どこまで援助すれば良いかをアセスメントします。
清拭や体位交換も含むケアの範囲
「下の世話」は排泄介助だけでなく、陰部・臀部の清拭や体位交換といったスキンケアも含まれます。清拭や体位変換は褥瘡や尿路感染症の予防と密接に関わるため、根拠に基づく実践が必要です。
清拭(陰部・臀部)の目的と手技
清拭は、清潔保持に加え皮膚トラブルの早期発見を目的とします。37〜40℃の微温湯で湿らせたタオルを用い、力を入れすぎず優しく拭き取ります。界面活性剤を含む洗浄剤は皮膚バリアを損なう恐れがあるため、メーカー推奨濃度を遵守しましょう。
体位交換による褥瘡予防
2時間ごとの体位変換が一般的ですが、低周波マットレスの使用状況や患者の循環動態により調整します。背抜き・ズレ防止シートを併用し、仙骨部や踵部の発赤を観察します。詳細は日本褥瘡学会「褥瘡管理ガイドライン」を参照してください。
医療現場で求められる法的責任と倫理
看護師は「保健師助産師看護師法」における業務独占資格として、排泄介助を含む日常生活援助を適切に提供する責務があります。また、日本看護協会「看護倫理綱領」では患者の尊厳保持とプライバシーの尊重が明記されています。適切な声かけとカーテン操作は、倫理的配慮と同時にインシデント防止にも直結します。
インフォームド・コンセントと患者の自己決定権
排泄介助の前には、目的・手順・所要時間を説明し、同意を得ることで患者の自己決定権を担保します。意思疎通が難しい場合は家族や介護福祉士と協働し、多職種カンファレンスでケア方針を共有します。
業務分担と安全配慮義務
人手不足で急性期病棟の夜勤帯はスタッフ2名体制となるケースもあります。労働安全衛生法に基づき、腰痛対策としてスライディングシートやリフトを活用し、スタッフの健康も守ることが組織の責任です。
便秘時に排便を促進する摘便処置
摘便とは、患者自身で排便が困難である際に、看護師をはじめとする医療従事者が指や専用の器具を使用して直腸内に貯留した便を人工的に取り除く医療行為です。
主に重度の便秘症や排便障害のある高齢者、寝たきりの患者に対して行われ、腹痛や食欲不振、腸閉塞などの合併症を防ぐ目的があります。患者にとって身体的・精神的な負担が大きいため、事前の説明や患者への配慮が重要とされる処置です。
看護師が下の世話をしたくないと感じる主な理由
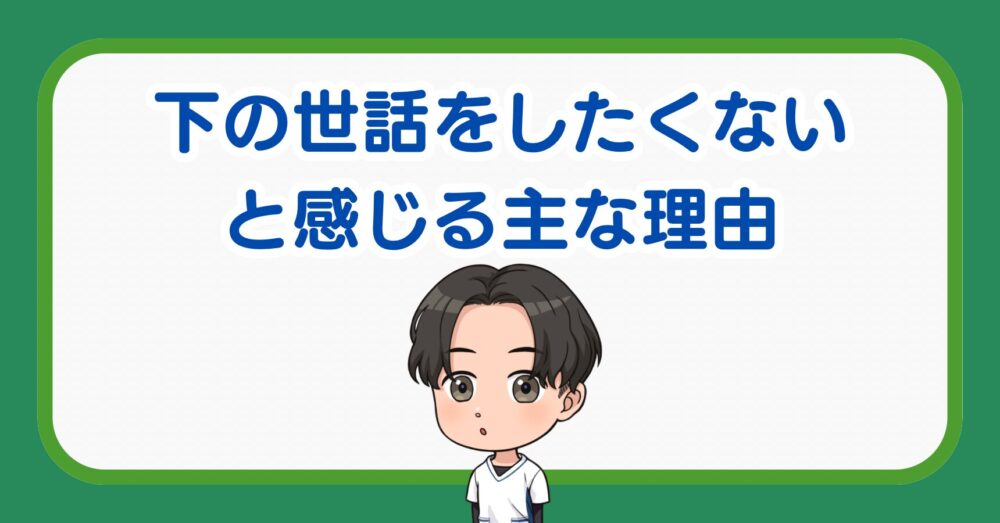
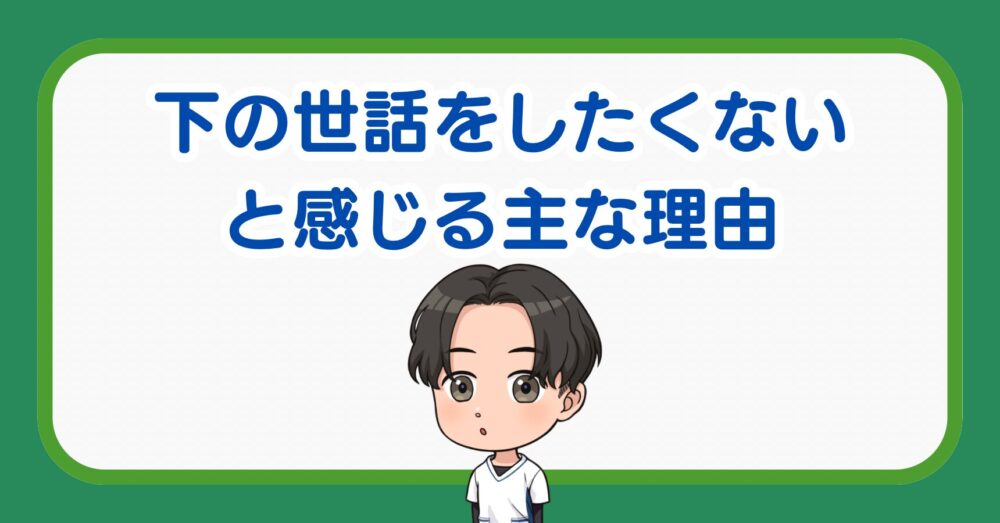
「下の世話」こと排泄ケアは、看護の根幹である一方、強い抵抗感を抱く看護師が少なくありません。ここでは、その代表的な要因を4つに整理し、背景と影響を解説します。
- 臭いと汚れに対する生理的ストレス
- 人手不足と時間的プレッシャー
- マニュアル不足と教育体制の問題
- コミュニケーションが難しい患者ケース
臭いと汚れに対する生理的ストレス
人間の嗅覚は本能的に排泄物を「危険」と判断するため、強い悪臭は嘔気や頭痛を誘発します。加えて、皮膚や衣類に汚染物が付着すると感染対策・清潔ケアが複雑化するため、心理的負担が増大します。
よくあるストレッサー
| 場面 | 具体的な行動 | ストレス反応 |
| おむつ交換 | 大量失禁・下痢便 | 悪臭による吐き気、作業遅延 |
| トイレ誘導 | 便座周囲の飛散汚染 | 清掃に時間を要し残業 |
| 清拭 | 皮膚に付着した便の除去 | 皮膚トラブル悪化の恐怖 |



知らずに衣類などに便が付着することもあります。私も、昼休憩の食事中にふと肘を見たら便が付着しており、一気に食欲を失った経験があります。
人手不足と時間的プレッシャー
慢性的な人員不足により、1人あたりの患者受け持ち数が増加しています。排泄ケアは突発的に発生しやすく、その他の医療行為や記録業務のスケジュールを圧迫します。
時間超過が引き起こす悪循環
残業・休憩時間短縮→疲労蓄積→ケアの質低下→苦手意識の強化、というサイクルが形成されがちです。
マニュアル不足と教育体制の問題
職場によっては標準化された手順書が存在せず、先輩看護師の「暗黙知」に依存しているケースがあります。新人は自分なりの方法が確立できず、ミスへの恐怖から回避行動を取りやすくなります。
教育格差が生むリスク
- 皮膚トラブル・褥瘡発生の増加
- 感染経路(接触感染)の拡大
- 患者プライバシーへの配慮不足
コミュニケーションが難しい患者ケース
認知症や脳血管障害により意思疎通が困難な患者では、排泄のタイミングを予測できず汚染頻度が増します。さらに拒否・暴言・暴力が加わることで、身体的・精神的ダメージが倍増します。
対応が難しい理由
排泄は羞恥心が伴う行為のため、説明や同意が得にくいと暴力行為につながりやすく、看護師の離職要因にもなっています。
現役看護師である私の「下の世話」に関する体験談
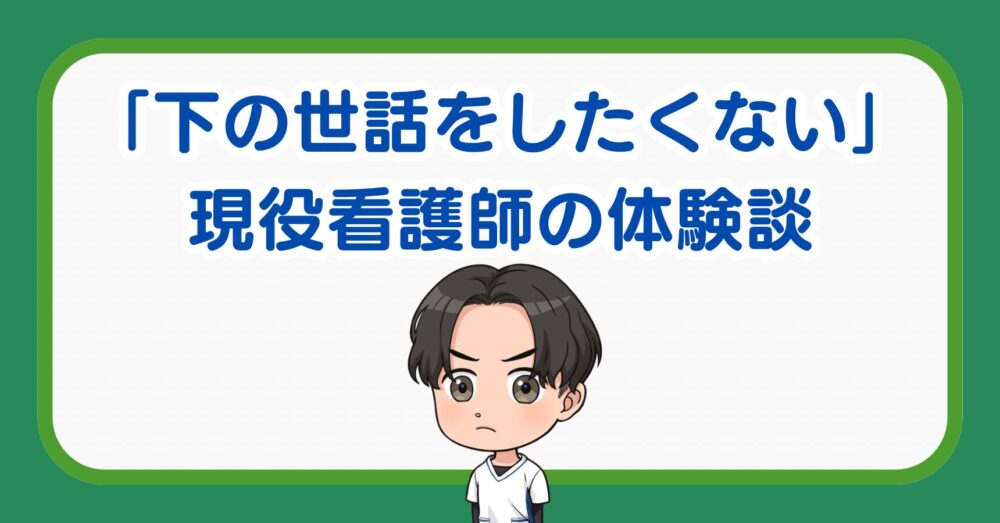
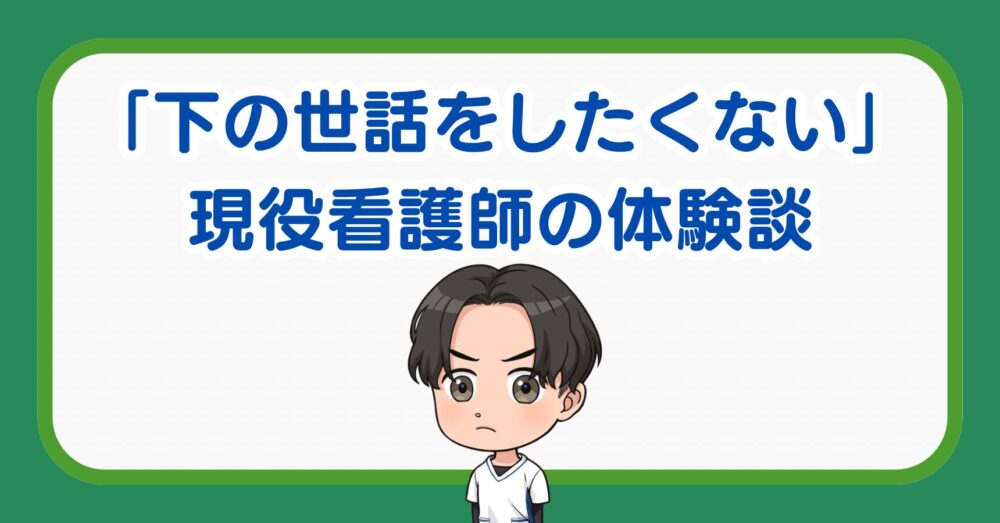
ここでは、私が実際に体験した「下の世話」にまつわる戸惑いや克服方法について解説します。
- 新人時代に戸惑ったオムツ交換の記憶
- ベテランに学んだコツと心構え
- 男女混合病棟でのプライバシー配慮
新人時代に戸惑ったオムツ交換の記憶
私は急性期病院に勤務していた新人時代、最初に直面した大きな壁がオムツ交換でした。学校の実習ではマネキン相手に練習したものの、実際の現場では「臭い・汚れ・時間との戦い」が想像以上で、始業からわずか30分でガウンが汗ばみ、精神的にもいっぱいいっぱいになったことを覚えています。



特にショックだったのは、排泄物が創部に付着しないよう素早く対応しなければならないプレッシャーです。自分の手技の遅さが患者さんの褥瘡リスクを高めるという恐怖で、心拍数が上がり手が震えました。
先輩からは「慣れよりもまず手順と根拠を覚える」とアドバイスされ、日本看護協会の排泄ケアガイドラインを読み込み、洗浄→乾燥→スキンケア→装着の流れを頭に叩き込みました。理論を理解してからは、時間を短縮でき、自分の焦りも軽減しました。
2年目になると、病棟のベテラン看護師から「五感を守る準備」を徹底する大切さを教わりました。
ベテランに学んだコツと心構え
| 準備 | 具体策 | 効果 |
| 嗅覚ガード | マスク内にメンソール入り軟膏を薄く塗布 | 不快臭を軽減し集中力を維持 |
| 視覚整理 | 防水シーツの色を統一して汚染範囲を判別 | 動線が見えやすく時短になる |
| 触覚セーフティ | ダブルグローブ+袖口をテープで固定 | 皮膚トラブルと感染リスクを低減 |
加えて、「患者さんの尊厳を守るためには“声かけの質”が最も重要」という指摘も印象的でした。手技に入る前に必ず「これからオムツを替えさせていただきますね」とタイムリーに伝えることで、患者さんの表情が明らかに和らぐのを感じました。
男女混合病棟でのプライバシー配慮
混合病棟では、男性患者さんの排泄介助を女性看護師が担当する場面が多々あります。抵抗感を最小限にするため、以下のポイントをチーム全体で共有していました。
- カーテンとスクリーンを二重使用し、視線を完全に遮断する
- 必ず同性スタッフがいれば優先して介助に入り、いない場合は2名体制で迅速に実施
- 体位変換シートを活用し、露出時間を短縮する



これらの対策は、患者さんだけでなく私たち看護師の心理的負担も減らします。
こうした経験から私が学んだ最大の教訓は「嫌悪感は悪ではなく、改善点を教えてくれるセンサー」だということです。自分の感情を否定せず、同じ悩みを抱える仲間と共有しながら、手技・環境・メンタルの三方向で工夫を重ねることで、下の世話への抵抗は確実に軽くできます。
看護師が下の世話を乗り切る対処法
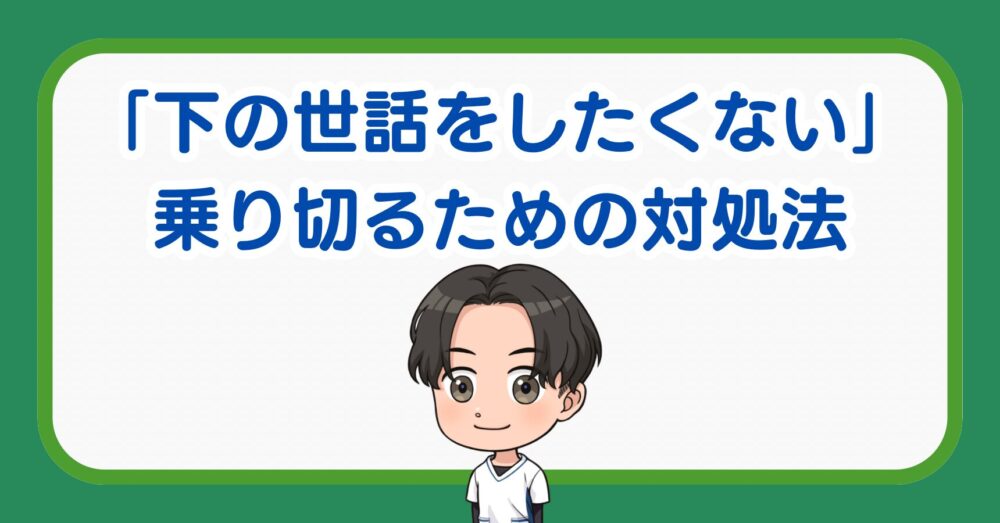
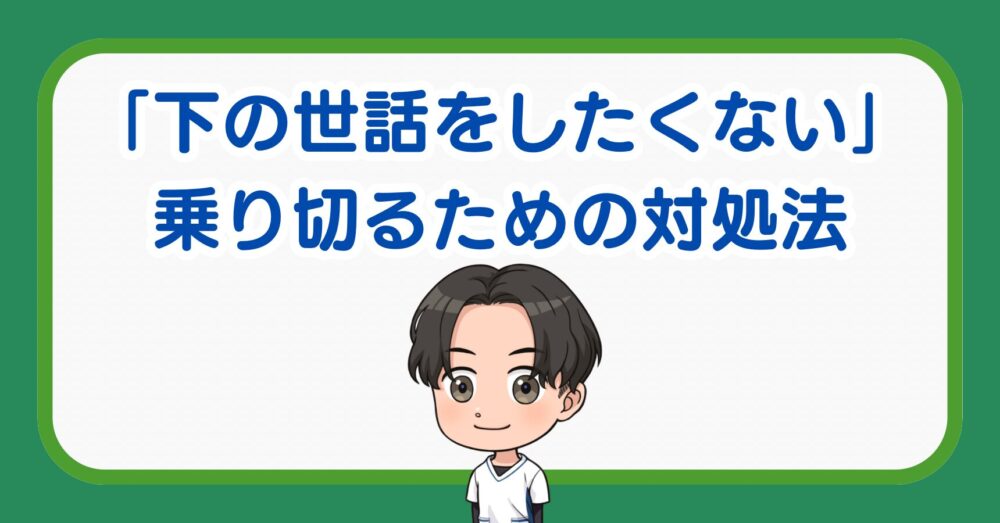
ここでは、「下の世話をしたくない」と悩む看護師でも負担を軽減し、受け入れやすくなるための4つの対処法を紹介します。
- 感染対策を兼ねた防臭テクニック
- 効率的な排泄介助フローで時短
- チームケアで負担を分散する方法
- メンタルケアと自己肯定感の保ち方



実際に私もこの方法を実践して、排泄援助への抵抗感を軽減できました。
感染対策を兼ねた防臭テクニック
排泄ケアでは感染症リスクと臭気ストレスを同時に軽減できる工夫が欠かせません。以下の基本を押さえることで、患者・スタッフ双方の安全と快適さを守れます。
個人防護具(PPE)の正しい使用
- 手袋は二重着用を徹底し、外す順番を守る
- フェイスシールドまたはゴーグルで飛沫を遮断
- ガウンは袖口をテープで固定し袖口汚染を防止
手指衛生やガウンテクニックは厚生労働省「医療施設における院内感染(病院感染)の防止について」で確認できます。
臭気を抑えるアイテム活用術
| アイテム | メリット | 使用のコツ |
| 消臭スプレー(医療用) | 細菌由来の臭気を化学的に分解 | 排泄物処理後すぐにリネンへ噴霧 |
| アロマパッチ付きマスク | マスク内に香りを閉じ込め長時間持続 | ミント・ユーカリ系が呼吸を楽にする |
| 防臭袋(高分子フィルム) | 廃棄物を完全密封し二次汚染を防止 | 袋の口をねじって二重結びする |
効率的な排泄介助フローで時短
限られた人員で質を落とさず排泄ケアを行うには、工程の標準化と可視化が鍵です。
タイムスケジュールの共有
- 患者ごとの排泄パターンを表計算ソフトで時間帯別に色分け
- デイリーミーティングで変更点を3分以内に報告
ワンウェイ方式の物品配置
使用物品を「清潔→準清潔→不潔」の動線順に並べることで、移動を最小限に抑えられます。
スライディングボードと電動昇降ベッドの活用
体位変換と移乗を機械化することで、腰痛リスクを軽減します。
チームケアで負担を分散する方法
「下の世話」はワンオペで抱え込まないことが長続きの秘訣です。チーム全体で支援し合えば、精神的・身体的負担を均等化できます。
ラウンド時のペア制度
- 看護師と看護補助者、または先輩ナースとの2人1組を原則化
- 患者への声掛けも2名で行うことで羞恥心を軽減
ICTツールによるタスクシェア
電子カルテの「排泄ケア完了」チェックボックスをデフォルト表示にし、リアルタイムで可視化することで、未完了タスクの偏りを防止します。
メンタルケアと自己肯定感の保ち方
排泄介助は「仕事として割り切ろう」としても感情がついてこない場面があります。セルフケア習慣を取り入れ、専門的支援も活用しましょう。
呼吸法とマインドフルネス
- 深呼吸4秒吸気→7秒停止→8秒呼気の「4-7-8呼吸法」で自律神経を整える
- 1日5分のマインドフルネス瞑想が感情の客観視に有効
リフレクション(内省会議)の実施
週1回、チームでケースを共有し感情を言語化することでバーンアウトを予防できます。リフレクションの効果については、日本看護学教育学会誌「看護学実習におけるリフレクション導入の効果」が参考になります。
EAP・カウンセリングの活用
病院が提携するEmployee Assistance Program(EAP)の無料カウンセリングを定期的に利用し、外部専門家の視点でストレスを評価してもらうと自己肯定感が維持しやすくなります。
下の世話をしたくない看護師におすすめの職場や診療科
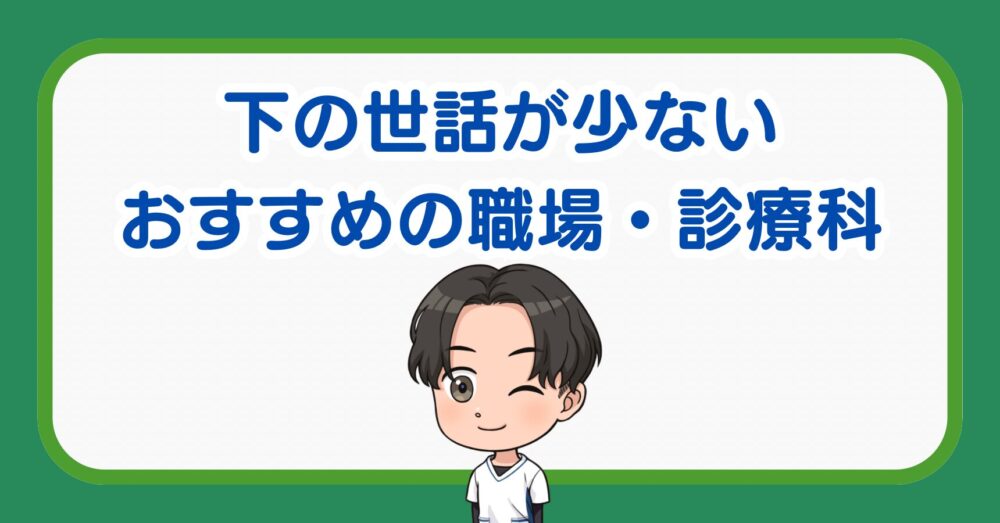
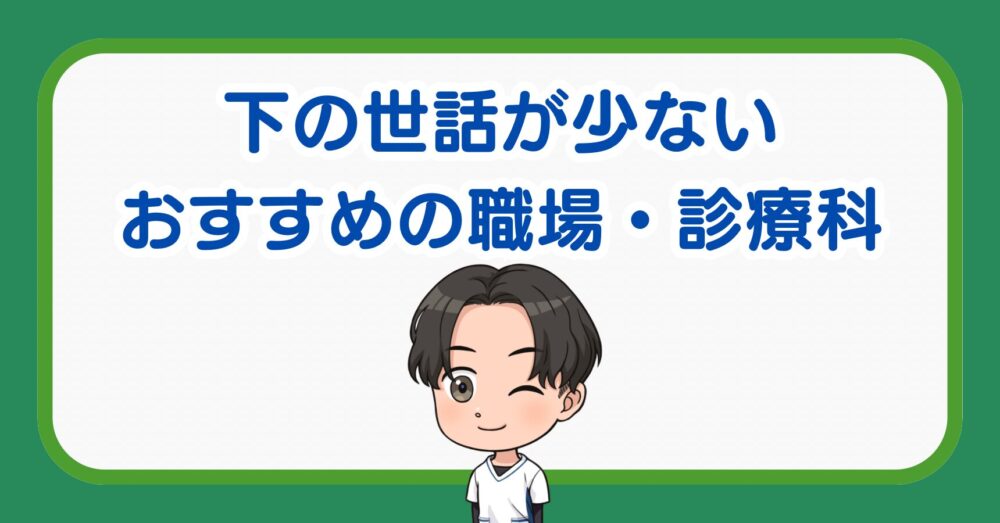
ここでは、下の世話をしたくない看護師の方に向けて、比較的排泄援助が少ない職場を4つ紹介します。
- クリニック(眼科・皮膚科・耳鼻咽喉科など)
- 健診センター・人間ドック施設
- 手術室(オペ室)
- 精神科病棟(身体的ケアが少ない場合)
クリニック(眼科・皮膚科・耳鼻咽喉科など)
外来診療が中心のクリニックでは、入院患者の排泄介助がほとんど発生しないため、下の世話に抵抗がある看護師でも働きやすい環境です。特に眼科や皮膚科、耳鼻咽喉科は処置内容が局所的であり、全身管理や長時間の体位変換を伴うケアが少ない点が魅力です。
業務内容とポイント
| 主な業務 | メリット | 注意点 |
| 診察補助、採血、点滴 | 身体介助が少なく技術習得に集中できる | 採血・点滴のスキルが必須 |
| 検査説明、患者指導 | コミュニケーション力が活かせる | 待ち時間クレーム対応が発生しやすい |
健診センター・人間ドック施設
健診センターは定期健康診断や人間ドックを専門に行うため、バイタル測定や採血、計測などの予防医療が中心です。検査前後の排尿介助はありますが、入院患者のオムツ交換などは原則ありません。
業務内容とポイント
| 主な業務 | メリット | 注意点 |
| 計測・採血・視力聴力検査 | 日勤のみ・土日休みの求人が多い | 検査のピーク時は流れ作業になりやすい |
| 検査結果説明・生活指導 | 予防医療の知識が深まる | 生活習慣改善を促すコミュニケーション力が必要 |
手術室(オペ室)
手術室看護師は周術期管理に特化しており、全身麻酔下での手術が多いため患者の排泄は麻酔科医や術前処置で管理されることがほとんどです。術中は機器出し・外回り業務が中心となり、下の世話は基本的に発生しません。
業務内容とポイント
| 主な業務 | メリット | 注意点 |
| 器械出し(直接介助) | 専門的知識・技術を深められる | 長時間手術で体力が必要 |
| 外回り(間接介助) | 多職種連携のスキルが向上 | 緊急オペで呼び出しがある |
精神科病棟(身体的ケアが少ない場合)
慢性期の精神科病棟では、身体合併症の少ない患者が多い場合、排泄介助の頻度は一般病棟より低めです。精神的サポートや生活リズムの調整が中心業務となります。
業務内容とポイント
| 主な業務 | メリット | 注意点 |
| 服薬管理・精神状態の観察 | カウンセリングスキルが身に付く | 暴力・自傷リスクへの対応が必要 |
| 生活リハビリ支援 | 患者の社会復帰を支援できる | 夜勤体制が手厚い病院を選ぶと安心 |
ここで紹介したようなオムツ交換がほとんどない健診センター・オペ室・精神科病棟などの求人は、一般公開されていない非公開求人も多いです。
ナース専科(旧ナース人材バンク)やレバウェル看護なら、こうした「排泄介助が少ない職場」に絞って求人を紹介してもらえるので、下の世話から解放されたい方は一度相談してみてください。
看護師資格を活かせる「下の世話」がない職種5選
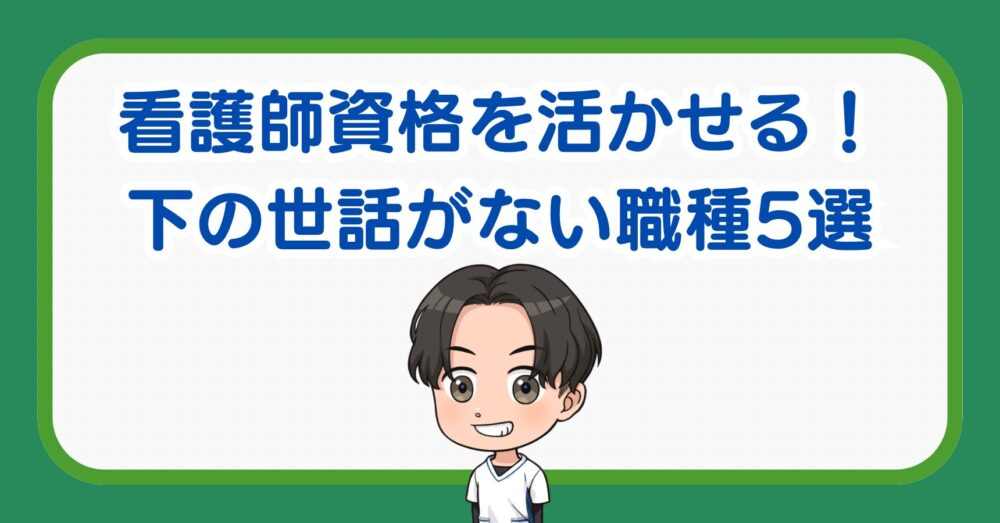
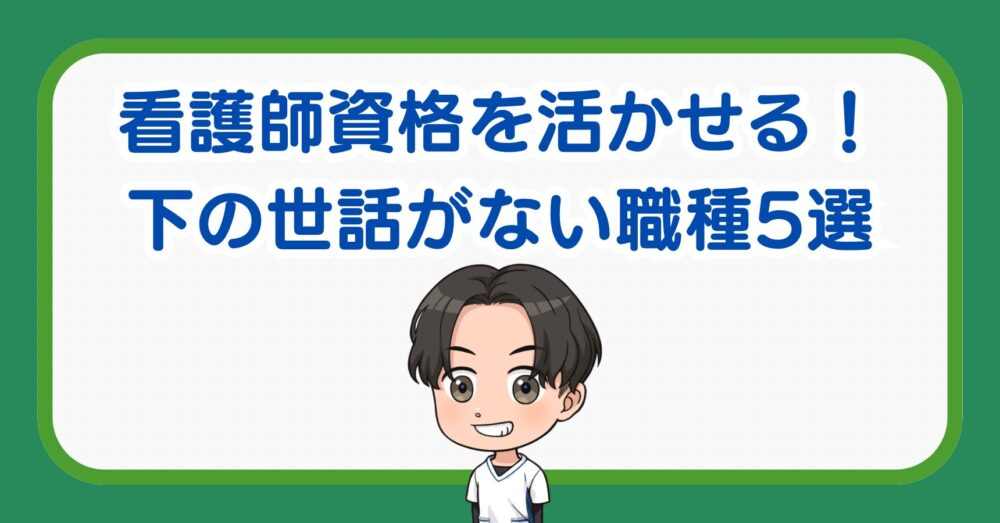
ベッドサイドケアに伴う排泄介助やオムツ交換を「どうしてもつらい」と感じるなら、業務の性質上ほとんど排泄介助が発生しない職種への転向も選択肢になります。ここでは看護師免許を活かしながら、下の世話とほぼ無縁で働ける代表的な5つの職種を紹介します。
| 職種 | 主な業務内容 | 働きやすさのポイント | 想定年収(目安) |
| 産業看護師 | 従業員の健康管理・健康相談、職場巡視、ストレスチェック対応 | 日勤のみ/土日祝休みが多い | 400万〜550万円 |
| 保育園看護師 | 園児の健康観察・応急手当、保健指導、感染症対策 | 夜勤なし/行事は平日中心 | 320万〜450万円 |
| 治験コーディネーター(CRC) | 治験参加者のスケジュール管理、データ収集、医師・企業との調整 | 病室滞在時間が短い/デスクワーク比率が高い | 400万〜600万円 |
| メディカルライター | 医学論文・学会抄録・医療機器マニュアルなどの執筆・校閲 | フルリモート可/成果物ベースで柔軟に働ける | 350万〜700万円 (フリーランスは出来高制) |
| 看護系教育機関の教員 | 講義・実習指導、シラバス作成、学生相談 | 年間休日が多い/長期休暇あり | 450万〜650万円 |
これらの仕事のもう一つの共通点は、「一人でできる事が多い」ことです。以下の記事で詳しく解説しています。
産業看護師|企業に勤めて従業員の健康管理を担当
企業や官公庁に雇用され、従業員の健康保持増進をサポートするのが産業看護師です。産業医と連携しながら、健康診断後のフォローや職場環境の改善提案、メンタルヘルス対策などを実施します。
ほぼ全てが日勤帯で、土日祝休み・年間休日120日以上という求人が多いのが魅力です。従業員の相談対応が中心のため、排泄介助は発生しません。



産業看護職の役割については、厚生労働省の資料「地域における産業保健活動の現状及び課題」に詳しくまとめられています。
保育園看護師|小児の成長を見守りながら定時で帰れる
認可保育所や認定こども園に配置され、園児の健康管理・怪我や急病時の応急処置、職員への保健指導を行います。オムツ交換は保育士が実施するため、看護師が排泄介助に関わるケースは極めて少ないのが特徴です。
行事準備などで残業が発生することはありますが、夜勤はなくワークライフバランスを取りやすい職種と言えます。



勤務基準や配置基準は、厚生労働省通知「保育所等における看護師等の配置基準の緩和について」で確認できます。
治験コーディネーター(CRC)|医薬品開発を支える専門職
治験コーディネーターは治験施設支援機関(SMO)や医療機関に所属し、治験の進行管理を担います。被験者対応はありますが、病棟ケアは行わないため下の世話はありません。ExcelやCTMS(治験管理システム)を使用するデスクワークが多く、医師・製薬企業・被験者間の調整力が重要です。



CRCの業務範囲や必要資格については、日本SMO協会公式サイトで公開されています。
メディカルライター|専門知識を文章化して発信
出版社・医療広告代理店・製薬企業などで医学系コンテンツを作成・監修する仕事です。臨床現場で得た知識を活かし、論文や学会資料を読解・要約する能力が求められます。在宅勤務やフリーランス案件も豊富で、身体介助は一切ありません。



メディカルライターの職能やキャリアパスは、日本メディカルライター協会(JMCA)のサイトで確認できます。
看護系教育機関の教員|未来のナースを育てる
看護大学・専門学校で講師や実習指導を担当します。教員養成課程の履修や実務経験が要件となりますが、講義準備や研究活動が中心で排泄介助はありません。長期休暇や学会参加で自身のスキルアップを図れる点も魅力です。



教員資格の要件は、文部科学省「看護師学校養成所における看護教員に関する規定」を参照してください。
下の世話をしたくない看護師におすすめの転職エージェント
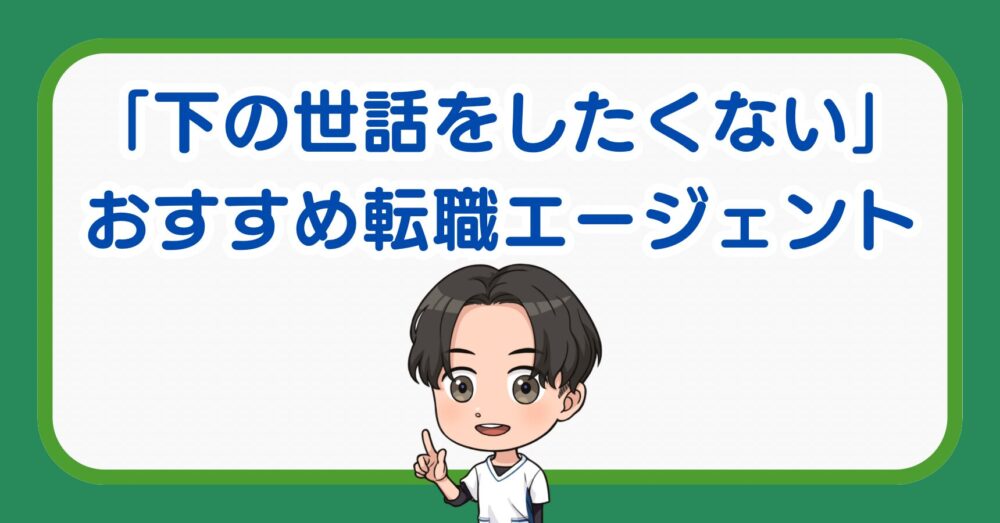
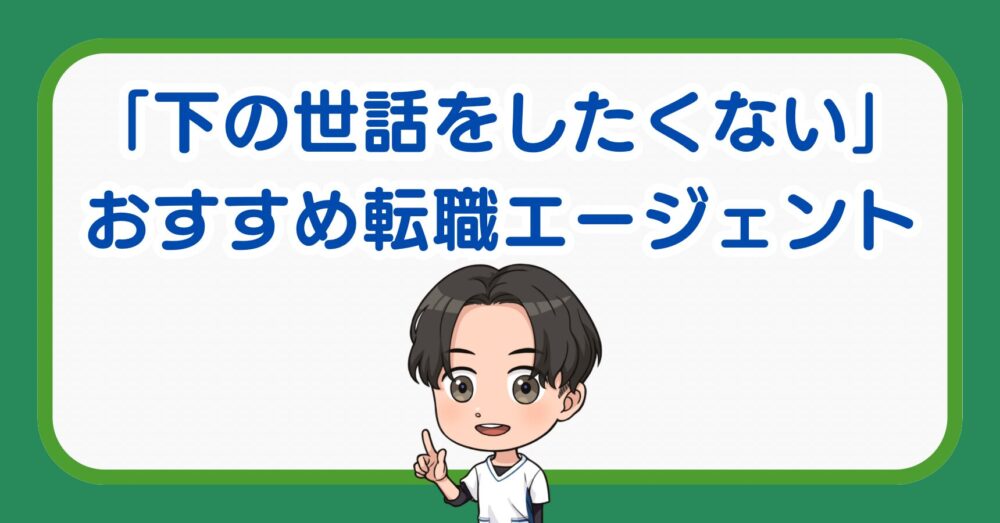
下の世話(オムツ交換・排泄介助)を避けたい看護師が転職を成功させるためには、「排泄介助が少ない求人を多く扱うエージェント」を利用するのが最短ルートです。一般公開されないクリニック・健診センター・手術室などの非排泄系求人は、転職エージェント経由で集中的に探すことで効率よく見つかります。
本章では、求人数が多いと評判の2社を厳選し、求人数・サービス内容・サポート体制を比較しました。
| エージェント名 | 公開求人数 (2025年5月時点) | 下の世話が少ない求人数 (筆者調べ) | 全国拠点 | 主なサポート特徴 |
| ナース専科 (旧ナース人材バンク) | 約200,000件 | ◎ | 47都道府県 | 専任制・電話&オンライン面談・医療機関への交渉力が高い |
| レバウェル看護 (旧看護のお仕事) | 約130,000件 | ◎ | 全国12拠点 | 24時間LINE相談・職場内部情報が豊富・履歴書添削が手厚い |
どちらに登録するか迷う方は、まずは求人数が多く全国対応の「ナース専科(旧ナース人材バンク)」に登録しつつ、LINEで気軽に相談できる「レバウェル看護」も併用するのがおすすめです。



エージェントは複数登録しても無料なので、それぞれから紹介される求人を比較しながら理想の職場を探しましょう。
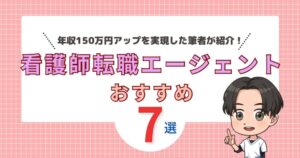
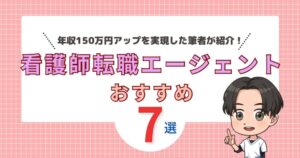
ナース専科(旧ナース人材バンク)


特徴
ナース専科公式サイトによると、公開求人だけで約20万件と業界最大級。多くの看護師に支持される大手転職エージェントです。病院からクリニック、健診センター、産業保健まで幅広い求人を保有し、排泄介助が少ない外来・オペ室案件も豊富です。


おすすめポイント
- 担当コンサルタントが1人の看護師に1人つく専任制。面接同席や条件交渉の代行で「排泄介助ゼロ」を具体的に伝えてくれる
- 地方在住でも電話・オンライン面談で転職活動が完結
- 47都道府県に拠点があり、地方のクリニック求人も網羅
- 年間3万人以上が利用しており、豊富なデータをもとにミスマッチを防止
注意点
求人数が多いゆえに、こまめに条件を伝えないと病棟求人が混ざりやすい点に注意しましょう。「オムツ交換なしの求人のみ紹介してほしい」と最初に明確化するとスムーズです。
利用の流れ
- Web登録(所要1分)
- 電話ヒアリングで「下の世話をしたくない」希望を伝達
- 求人紹介・書類選考
- 面接(担当者同席可)
- 内定・条件交渉・入職後フォロー
レバウェル看護(旧看護のお仕事)


特徴
レバウェル看護公式サイトによると、24時間365日LINEで相談できる体制が強み。年間4,000回以上の職場訪問で得る内部情報の数は業界トップクラスです。健診センター・美容クリニック・透析クリニックなど排泄介助が少ない求人を多数保有しています。
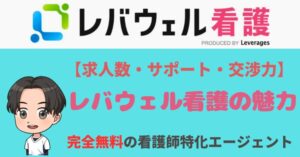
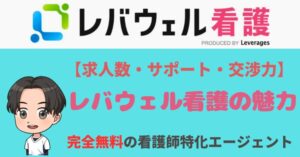
おすすめポイント
- LINEで気軽に求人検索・日程調整ができるため、夜勤中や休憩時間でも転職活動が可能
- 内部情報レポート制度により、スタッフ定着率や排泄介助の実態を事前に把握できる
- 履歴書・職務経歴書の添削に加え、面接想定質問集が充実しており、短期間で内定率を高めやすい
注意点
都市部の求人が中心で、地方は案件が限定的になる場合があります。地方在住の方はナース専科と併用することで選択肢が広がります。
利用の流れ
- LINEまたはWebから登録
- 担当者とチャットで条件整理(排泄介助ゼロを明記)
- 求人紹介・書類選考
- 面接(オンライン可)
- 内定後フォロー・入職後ヒアリング



どちらも無料で併用可能です。「下の世話をしない働き方」を実現するために、複数エージェントに登録し、自分に合った求人を比較検討しましょう。
まとめ
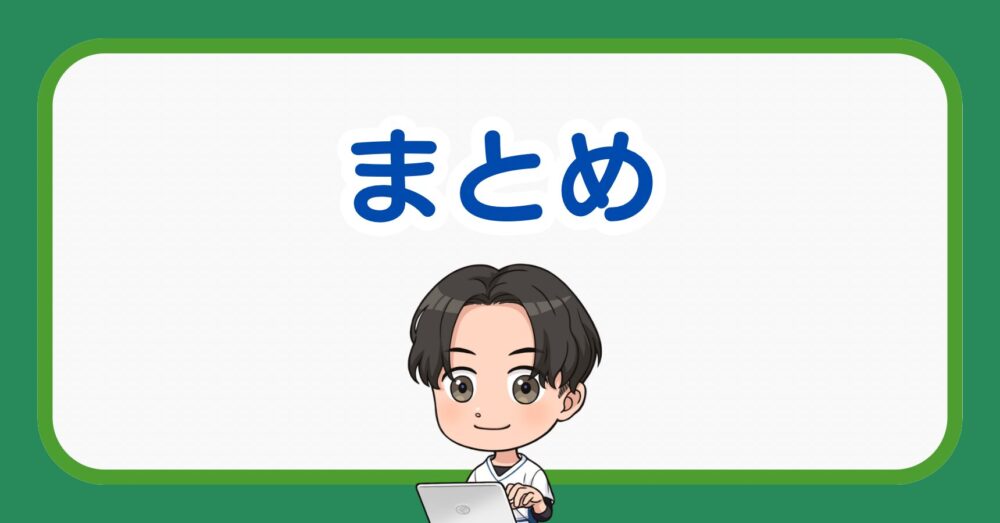
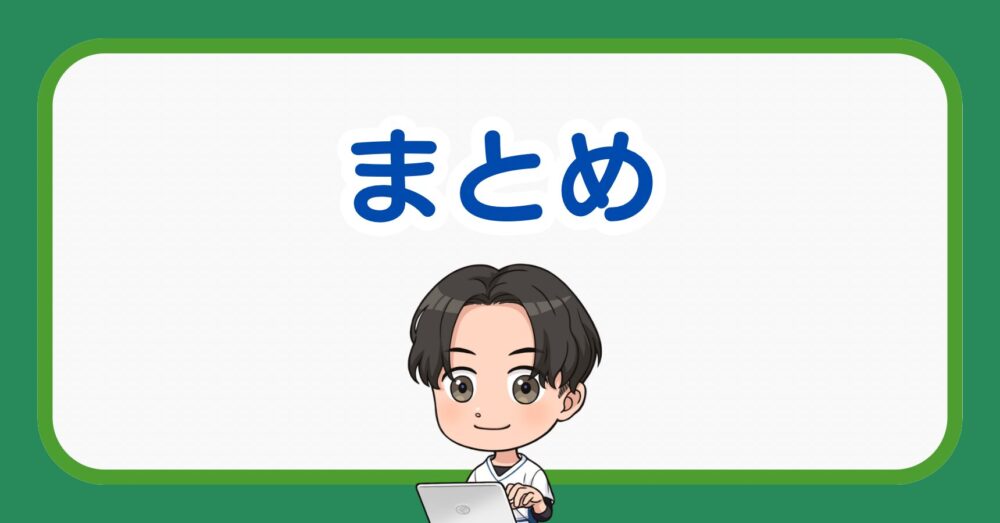
下の世話への抵抗感は臭いや汚れ、時間的負担、教育不足など複合的要因が絡む自然な感情です。決して「看護師として失格だ」などと思い詰める必要はありません。排泄援助への抵抗感は防臭対策や作業フロー改善、チーム協力で軽減できます。どうしても合わない場合はクリニックや産業看護師など排泄介助の少ない職場へ転職する選択肢も有効です。
≫看護師資格が使える珍しい求人10選!筆者も経験した好条件の職場も紹介
メンタルケアで自己肯定感を保ち、専門知識を深めることで患者との信頼関係が築け、下の世話への苦手意識は徐々に薄れていくでしょう。



できることとできないことを見極め、自分に合った働き方を選ぶことが長く看護を続ける秘訣です。
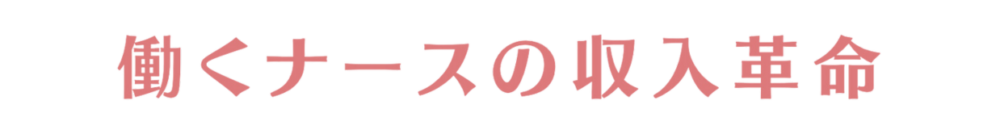
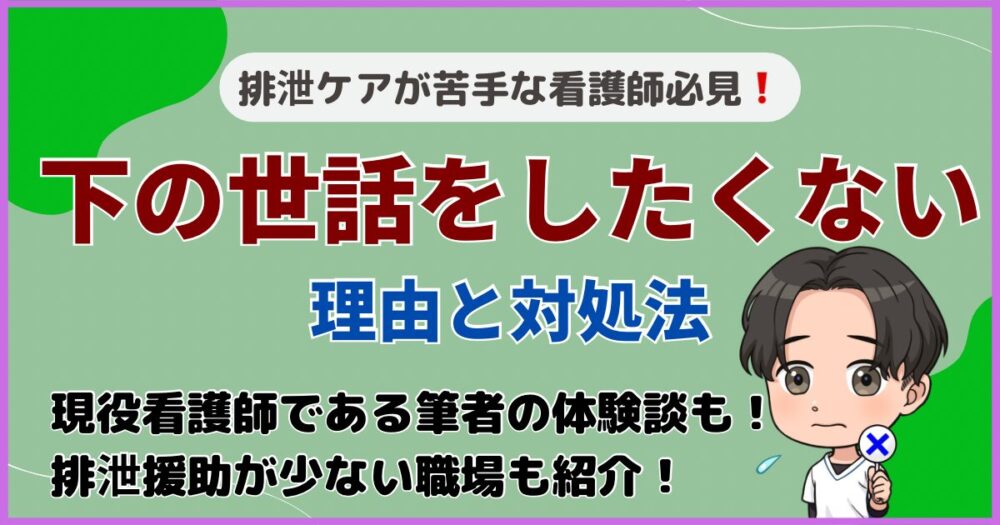

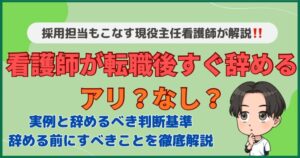
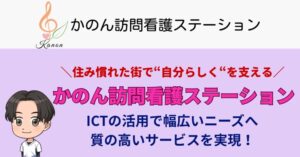
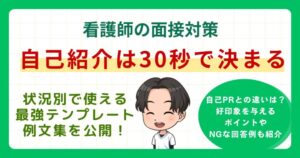

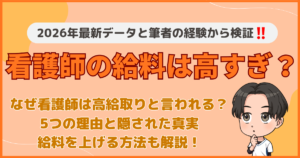
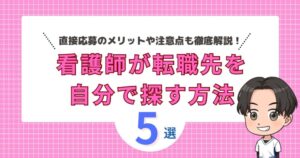
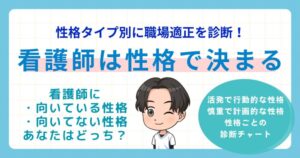

コメント