※この記事はプロモーションが含まれます。
看護師主任の役割は、看護師長の補佐やスタッフの教育・管理だけではありません。私はこれまでに急性期病院や精神科病院など、様々な職場を経験し、現在は介護施設で主任として活躍しています。
 ryanta73
ryanta73実際に働く中で、主任という役職の役割や苦悩を実感しています。
この記事では、現役主任の筆者が自身の経験を基に、具体的な業務内容や必要なスキル、中間管理職としての苦労ややりがいを本音で解説します。年収や夜勤事情といったリアルな疑問にもお答えするので、主任を目指す方や現職で悩んでいる方の不安が解消され、キャリアを考えるヒントが見つかります。
主任のしんどさは「能力不足」じゃなく、職場の体制・役割設計で決まることも多いです。まずは条件を整理しませんか?
看護師における主任の役割
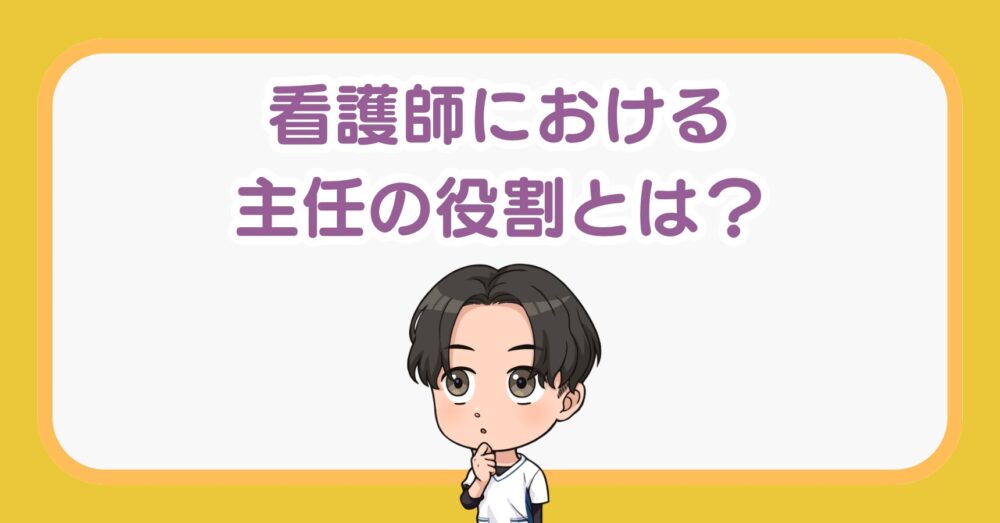
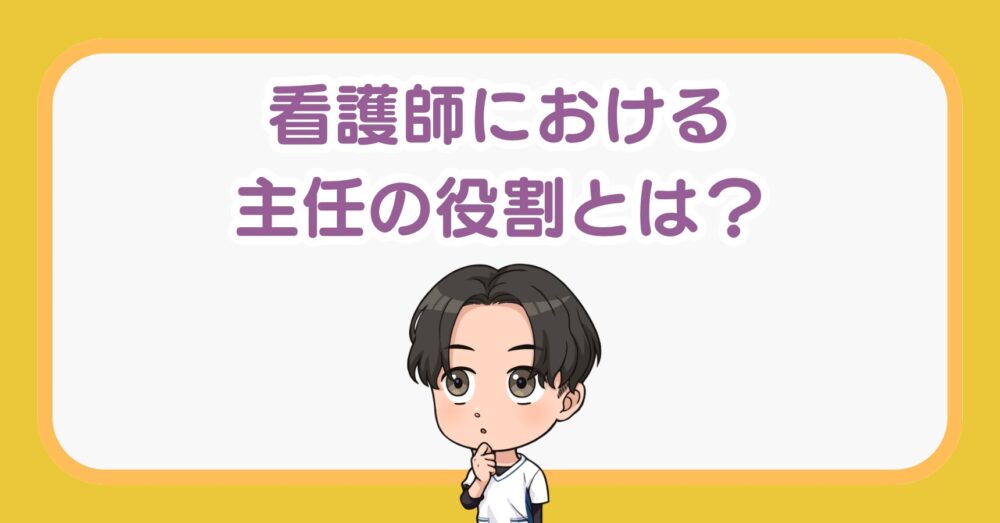
看護主任は、看護現場のリーダーとして、また管理職への第一歩として、非常に重要なポジションを担います。単に経験年数が長いベテラン看護師というだけではなく、現場の要として多岐にわたる役割を求められるのが特徴です。
ここでは、看護師主任が担う5つの基本的な役割について、具体的な業務内容を交えながら詳しく解説します。
- 看護師長の補佐
- スタッフの教育・相談・トラブル対応
- シフト・業務調整
- 医師や多職種との連携
- インシデント・ヒヤリ対策の実務対応
看護師長の補佐
多くの病院では、主任は病棟や外来の看護師長を補佐する「副師長」的な役割を担います。看護師長が病棟全体の管理や看護部全体の方針決定に関わるのに対し、主任はより現場に近い立場で、師長の方針をスタッフに浸透させ、業務が円滑に進むようサポートします。
具体的な業務には以下のようなものがあります。
- 看護師長不在時の代理業務(緊急時の判断や指示など)
- 目標達成に向けた実行計画の立案と進捗管理
- 看護部や他部署との会議で決定した事項の現場への伝達
- 看護サービスの質向上のための業務改善提案
一方で、看護師長が配置されていないクリニックや介護施設などでは、主任が看護部門の事実上の責任者となるケースも少なくありません。その場合、施設の管理者(施設長や院長)の補佐役として、看護スタッフのマネジメントだけでなく、一部経営的な視点も求められることがあります。



私も介護施設の主任なので、実質的に師長と同等の役割を担っています。
スタッフの教育・相談・トラブル対応
主任は、現場スタッフにとって最も身近な指導者であり、相談相手です。チーム全体の看護の質を底上げするため、個々のスタッフの成長を支援する役割は非常に重要です。
- 教育・指導
- 新人や若手看護師に対して、日々の業務を通じたOJT(On-the-Job Training)はもちろん、個々のスキルや習熟度に合わせた指導計画を立て、実践します。プリセプター(指導担当者)への助言やサポート、院内研修や勉強会の企画・運営も主任の仕事です。日本看護協会が示す「看護師のクリニカルラダー」のような能力開発プログラムに沿って、スタッフのキャリア形成を支援する役割も担います。
- 相談・メンタルヘルスケア
- スタッフが抱える業務上の悩みや人間関係、キャリアパスに関する相談に応じ、精神的な支えとなることも大切な役割です。定期的な面談を通じてスタッフの状況を把握し、問題が大きくなる前に対処します。個々のスタッフが安心して働き続けられる環境を整えることは、離職防止にも繋がります。
- トラブル対応
- スタッフ間の意見の対立や、患者・利用者さんとの間で生じた小さなトラブルなど、現場で起こる様々な問題の初期対応と仲裁を行います。感情的な対立を冷静にときほぐし、建設的な解決策を見出す調整力が求められます。
シフト・業務調整
チームが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、日々の業務や人員配置を最適化するのも主任の重要な役割です。これは単なる事務作業ではなく、高度なマネジメント能力が求められます。
- シフト作成・調整
- スタッフの希望休や有給休暇を尊重しつつ、個々のスキル、経験、心身のコンディション、そして公平性を考慮して勤務表を作成します。急な体調不良者が出た際の迅速な人員調整も主任の腕の見せ所です。適切なワークライフバランスを保ち、スタッフの燃え尽きを防ぐための配慮が欠かせません。
- 業務量の調整(ワークロード管理)
- 日々の患者・利用者さんの重症度やケアの必要性に応じて、各スタッフの受け持ち業務が偏らないように調整します。リーダー業務や委員会活動、新人指導といった役割も考慮し、チーム全体の業務負担が平準化されるように采配を振るいます。
医師や多職種との連携
質の高い医療やケアは、看護師だけで完結するものではありません。主任は、医師や他の専門職と現場スタッフとを繋ぐ「ハブ」として、チーム医療・チームケアを推進する中心的な役割を担います。カンファレンスの調整や進行役を務め、各専門職からの情報を集約し、最適な治療方針やケアプランが立案・実行されるよう働きかけます。



職種間の意見が対立した際には、患者・利用者の利益を最優先に考え、円滑なコミュニケーションを通じて合意形成を図ります。
連携する主な職種は、働く場所によって以下のように異なります。
| 職場 | 連携する主な職種 |
| 病院 | 医師、薬剤師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、管理栄養士、臨床検査技師、放射線技師、医療ソーシャルワーカー(MSW) など |
| 介護施設 | 介護福祉士、ケアマネジャー(介護支援専門員)、生活相談員、機能訓練指導員(PT・OT・STなど)、嘱託医、管理栄養士 など |
| クリニック | 医師、医療事務、臨床検査技師、放射線技師 など |
このように、多様な専門職と円滑な関係を築き、情報を正確に伝達・共有する能力は、主任にとって不可欠なスキルです。
インシデント・ヒヤリ対策の実務対応
医療・看護の現場では、インシデント(予期せぬ出来事)やヒヤリ・ハットをゼロにすることはできません。主任は、医療安全(リスクマネジメント)の観点から、これらの事象に適切に対応し、再発防止に繋げる実務的な役割を担います。
- 発生時の対応と分析
- インシデントが発生した際は、まず患者・利用者さんの安全確保を最優先に、迅速かつ的確な初期対応を指揮します。同時に、当事者となったスタッフへの精神的なフォローも行い、過度な自責の念に駆られることがないよう配慮します。その後、インシデントレポートの作成を促し、客観的な事実に基づいて原因を分析します。
- 再発防止策の立案と周知
- 分析結果をもとに、具体的な再発防止策(業務マニュアルの見直し、ダブルチェック体制の強化など)を立案し、チーム全体に周知徹底します。重要なのは、個人を責めるのではなく、システムや環境の問題として捉え、組織全体で改善に取り組む文化を醸成することです。そのためにも、スタッフが萎縮することなく些細なことでも報告できるような、風通しの良い職場環境を作ることも主任の重要な務めです。
主任看護師として担っている私の役割
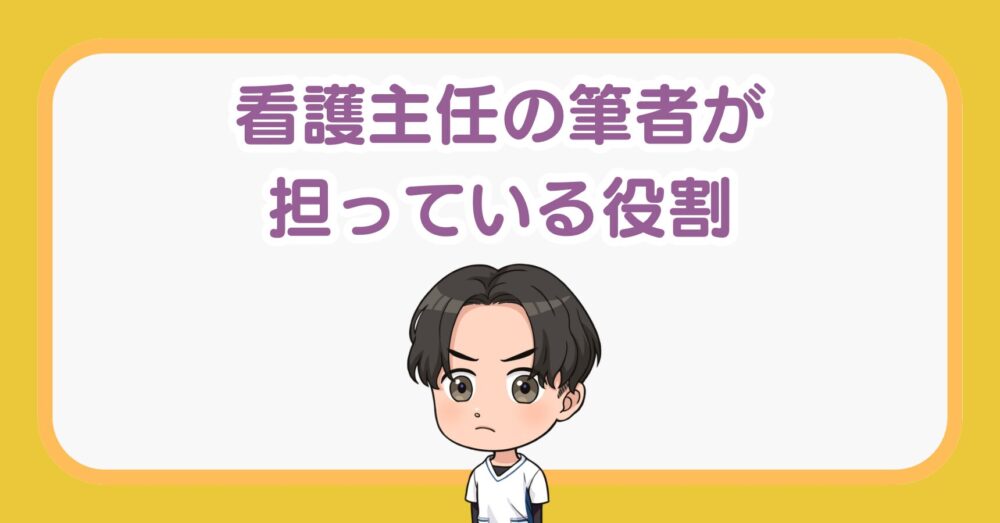
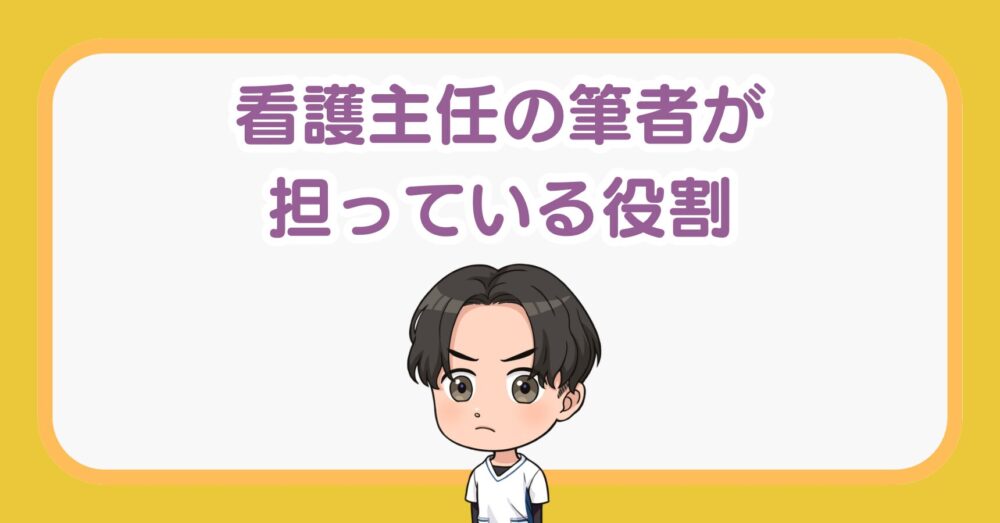
看護師主任の役割は、教科書通りにはいかないことばかりです。ここでは、私が実際に介護施設で看護主任として日々どのような役割を担っているのか、具体的なエピソードを交えながらご紹介します。現場のリアルな声として、キャリアプランの参考にしてください。
- 介護施設での看護主任として1日のスケジュール
- スタッフ間の橋渡し役|実際にあった人間関係の仲裁例
- 現場の声を上に届ける“中間管理職”の難しさ|上司と部下の板挟みにあった実例
介護施設での看護主任として1日のスケジュール
私の勤務する介護施設での、ある1日のスケジュールをご紹介します。主任の業務は、利用者のケアだけでなく、スタッフの管理や多職種との連携など多岐にわたります。



自分のタスクと全体の動きを常に把握し、臨機応応変に対応することが求められる毎日です。
| 時間 | 業務内容 | 役割とポイント |
| 8:30 | 出勤・夜勤者からの申し送り | 夜間の利用者様の状態変化や特記事項を正確に把握。スタッフ全員に情報が共有されるよう、ポイントを整理して伝えます。 |
| 9:00 | 全体朝礼・ラウンド | 護・介護スタッフ全員で情報共有。その後、フロアをラウンドし、利用者様の状態だけでなく、スタッフの表情や業務の進捗状況も確認します。 |
| 10:00 | カンファレンス・ケアプラン調整 | ケアマネジャーやリハビリスタッフと合同でカンファレンスを実施。利用者様の状態に合わせたケアプランの見直しや、サービス内容の調整を行います。 |
| 11:00 | 新人看護師への指導 | 新人が行う処置に付き添い、技術的な指導や精神的なフォローを行います。不安を解消し、自信を持ってケアにあたれるようサポートするのも重要な役割です。 |
| 12:30 | 昼食・休憩 | スタッフとコミュニケーションを取りながら交代で休憩。午後の業務に備えます。 |
| 13:30 | 委員会資料の作成 | 担当している「褥瘡対策委員会」の資料を作成。院内全体のケアの質向上に向けたデータ分析や改善案をまとめます。 |
| 15:00 | 急な欠員によるシフト修正 | スタッフから急な体調不良の連絡。急遽、翌日以降のシフトを再調整し、他のスタッフへ連絡。人員不足でも安全なケア体制を維持できるよう奔走します。 |
| 16:00 | ご家族への連絡・対応 | 利用者様の状態変化についてご家族へ連絡。不安に寄り添い、丁寧な説明を心がけます。時には、ご意見やクレームの初期対応も行います。 |
| 17:00 | 日勤業務の締め・記録の確認 | 各スタッフの記録に目を通し、報告漏れや問題がないか最終確認。必要に応じてフォローアップします。 |
| 17:30 | 退勤 | 残務整理を行い、夜勤スタッフへ申し送りをして退勤。頭の中は明日の業務のことでいっぱいです。 |
スタッフ間の橋渡し役|実際にあった人間関係の仲裁例
主任の最も重要な役割の一つが、スタッフ間の人間関係の調整です。看護の現場はチームワークが命。スタッフ間の小さな亀裂が、大きな医療事故につながることもあります。



先日、実際に私が仲裁に入ったケースをご紹介します。
事の発端は、経験豊富なベテラン看護師Aさんと、入職半年の新人看護師Bさんの関係でした。Aさんは「Bさんは報告が遅いし、観察が甘い」と苛立ち、Bさんは「Aさんはいつも不機嫌で質問しづらい」と萎縮していました。フロアの雰囲気も悪くなり、私は双方から個別に話を聞くことにしました。
まずは、それぞれの言い分を傾聴し、感情を受け止めます。
「Bさんを指導したいという熱意は素晴らしいです。ただ、少し伝え方が厳しいと感じさせているかもしれません。Bさんが報告しやすいように、例えば『午前中に一度、変わりないか声をかけてもらえる?』と具体的に伝えてみてはどうでしょうか?」
「Aさんに質問しづらい気持ちはよくわかります。でも、利用者さんの安全のためには報告は不可欠です。わからないことを放置する方がもっと怖いことだと考えて、勇気を出して声をかけてみましょう。私もフォローします。」



その後、私が間に入る形で、報告のタイミングや方法について具体的なルールを一緒に決めました。
一方的にどちらかを責めるのではなく、お互いの立場を理解し、チームとして機能するための具体的な解決策を見つける手助けをすることが、主任としての「橋渡し役」の使命だと考えています。
現場の声を上に届ける“中間管理職”の難しさ|上司と部下の板挟みにあった実例
主任は現場のリーダーであると同時に、看護師長や施設長といった上層部と現場スタッフをつなぐ「中間管理職」でもあります。



この立場で最も苦労するのが、いわゆる「板挟み」です。
以前、こんな出来事がありました。施設長から「経営改善のため、全フロアで使用している体位変換クッションを、より安価な製品に変更するように」という指示が出たのです。しかし、現場スタッフからは「新しいクッションは硬くて利用者の体に合わない」「褥瘡リスクが高まるのではないか」と強い反発の声が上がりました。
私自身も、経営的な視点は理解できるものの、現場の意見はケアの質と利用者の安全に直結するため、無視することはできません。まさに、上司と部下の間で板挟み状態です。
この時、私が取った行動は以下の通りです。
- 客観的なデータの収集
- まず、新しいクッションを試験的に使用し、皮膚の発赤や利用者の不快の訴えがなかったか、スタッフの作業効率に変化はあったかなどを記録しました。
- 現場の意見の整理
- スタッフの感情的な反発だけでなく、「なぜこのクッションではダメなのか」を専門職としての根拠(褥瘡発生メカニズムなど)と共に整理し、レポートにまとめました。
- 代替案の提示
- ただ「反対」するだけでなく、コストと品質のバランスが取れた別の製品をいくつかピックアップし、代替案として提示する準備をしました。
これらの資料を持って施設長と面談し、「コスト削減の意図は理解できます。しかし、この変更は長期的に見て褥瘡の発生率を高め、結果的に医療コストの増大や施設の評判低下に繋がるリスクがあります」と、データに基づいて冷静に伝えました。結果、全面的な変更は見送られ、品質を維持できる別の製品を検討することになりました。



上からの指示をただ現場に伝えるだけ、現場の不満をただ上に報告するだけでは、中間管理職の役割は果たせません。
双方の意見を翻訳し、客観的な事実やデータに基づいて調整・交渉することが、主任に課せられた重要な役割だと痛感した出来事でした。
主任看護師の役割を果たすのに必要なスキルとマインド
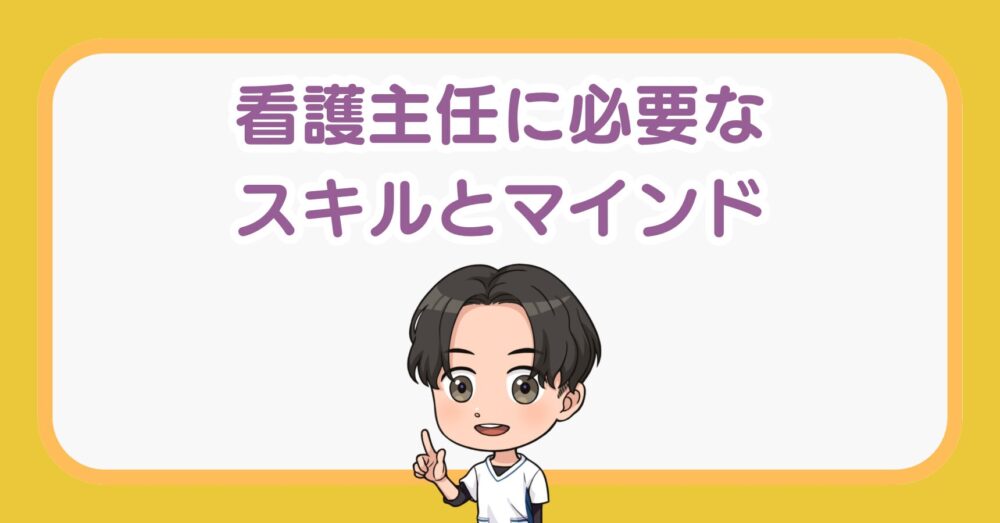
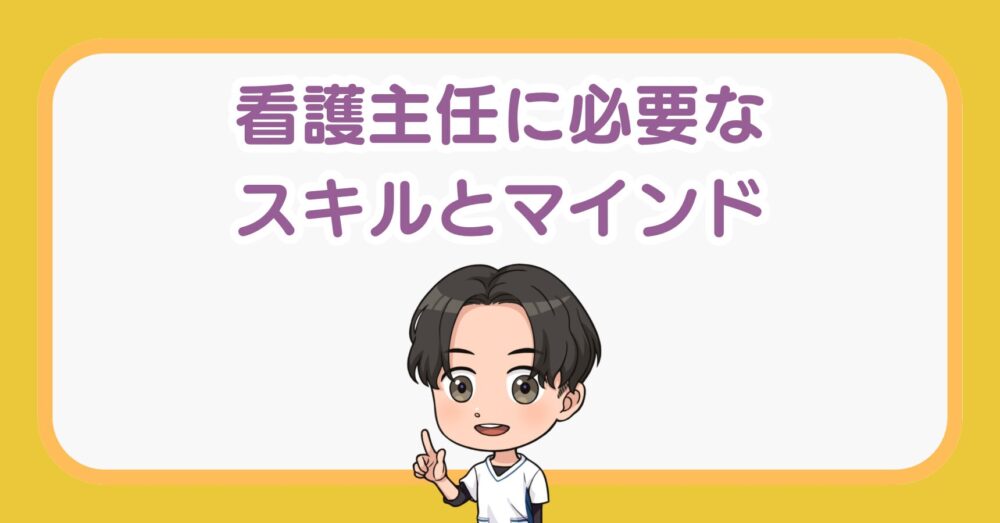
看護師主任は、一人の優れたプレイヤーであるだけでは務まりません。スタッフをまとめ、部署全体を円滑に運営する管理職としてのスキルと、チームを牽引するリーダーとしてのマインドセットが不可欠です。ここでは、主任として現場で求められる3つのスキルについて、私の具体的な経験を交えながら解説します。
- コミュニケーション能力
- 判断力と冷静さ
- チームマネジメント力
コミュニケーション能力
看護主任の業務は、人と人との間に入って調整することが大半を占めます。上司である看護師長や施設長、部下である現場スタッフ、医師やリハビリ職などの多職種、そして患者やその家族。あらゆる立場の人と円滑な人間関係を築き、情報を正確に伝達するコミュニケーション能力は、主任にとって最も重要なスキルと言えるでしょう。
単に「話すのがうまい」ということではありません。相手の話を真摯に聴く「傾聴力」、自分の意見を押し付けるのではなく相手を尊重しながら主張する「アサーティブコミュニケーション」、そして対立する意見を調整し合意形成を図る「ファシリテーション能力」など、多角的なコミュニケーションスキルが求められます。



例えば、私には以下のような経験があります。
ケース1:いつも不機嫌で怒りっぽい先輩への対応
私の職場にも、些細なことでイライラし、後輩にきつく当たってしまうベテランスタッフがいます。周囲は萎縮し、報告・連絡・相談が滞るなど、チームワークに悪影響が出始めていました。



そこで私は、まずその先輩と1対1で話す時間を作りました。(正直、怖かったですが‥)
いきなり注意するのではなく、「最近、何か大変なことはありますか?」「〇〇さんの経験はチームに不可欠なので、力を貸してほしいんです」と、まずは相手を尊重し、頼る姿勢を見せました。
すると、実は家庭の事情でストレスを抱えていたこと、そして自分の態度が周囲に悪影響を与えていることへの罪悪感を感じていたことを打ち明けてくれました。感情的に叱責するのではなく、相手の背景を理解しようと努めたことで、少しずつ態度が軟化しています。
その後は、業務負担を調整したり、彼女の知識を若手に伝えてもらう役割をお願いしたりすることで、チーム内での孤立を防ぎ、関係を再構築することができました。
ケース2:ミスをするたびに泣いてしまう看護師への対応
一方で、インシデントを起こすたびに落ち込んで泣いてしまい、仕事を抱え込んでしまう人もいました。彼女に対しては、まず「ミスは誰にでもあること。大切なのは次にどう活かすかだよ」と伝え、安心感を与えることを最優先しました。そして、ミスした状況を一緒に振り返り、「何が原因だったと思う?」「次はどうすれば防げるかな?」と、本人に考えさせる形でフィードバックを行いました。



これは「コーチング」と呼ばれる手法で、一方的に答えを与えるのではなく、本人の気づきと成長を促すことが目的です。
責めるのではなく、寄り添い、一緒に考える姿勢を見せました。彼女は徐々に自信を取り戻し、少しずつですが自ら積極的に質問や相談ができるようになりました。
判断力と冷静さ
医療・介護の現場では、いつ何が起こるか予測できません。特に利用者の急変といった緊急事態において、主任の判断一つがその後の結果を大きく左右します。パニックに陥りそうなスタッフを落ち着かせ、的確な指示を出し、チームを動かすためには、豊富な知識と経験に裏打ちされた「判断力」と、どんな状況でも動じない「冷静さ」が不可欠です。



これは主任になる前の話ですが、以下のような出来事がありました。
私が勤務する介護施設で、ある利用者が食堂で突然意識を失い、けいれん発作を起こしたことがありました。その場にいたほとんどは介護職員だったこともあり、近くにいたスタッフは動揺し、立ち尽くしてしまいましたが、私はすぐに駆け寄り、次のように指示を出しました。
- 「Aさん、すぐに救急車を要請して!状況を正確に伝えて!」
- 「Bさん、他の利用者さんを別室へ誘導して!不安にさせないように落ち着いて!」
- 「Cさん、救急カートと酸素ボンベを持ってきて!Dさんは僕の横で記録をお願い!」
- 「大丈夫、まずは気道確保。体を横に向けて誤嚥を防ぎましょう」
瞬時に状況をアセスメントし、誰が・何を・いつまでに行うべきかを明確に指示することで、チームは混乱なく動くことができました。幸い、迅速な初期対応と救急隊への引き継ぎが功を奏し、利用者は一命をとりとめました。日頃から急変時対応のシミュレーションを繰り返し行い、スタッフそれぞれの役割を明確にしておくことの重要性を痛感した出来事です。
チームマネジメント力
主任は、個々のスタッフが持つ能力を最大限に引き出し、チームとして1+1が2以上になるような成果を生み出す「チームマネジメント力」も求められます。優れたチームは、質の高い看護・介護を提供できるだけでなく、スタッフの離職率低下や満足度向上にも繋がります。



私がチーム全体を支えるために、特に心がけていることは次の3つです。
| 心がけていること | 具体的な行動 | 目的・効果 |
| 1. 公平な評価とポジティブなフィードバック | スタッフ一人ひとりの働きを日頃からよく観察し、目標達成に向けた面談を定期的に実施。良い点は「〇〇さんの今日の声かけ、すごく良かったよ」と具体的に褒め、改善点は「こうすればもっと良くなるかも」と前向きな言葉で伝える。 | スタッフのモチベーションを高め、成長を促す。えこひいきがないという信頼感が、チームの一体感に繋がる。 |
| 2. 心理的安全性の確保 | 会議の場で、まずは自分から「私はこう思うんだけど、どうかな?」と意見を出す。若手や反対意見も決して否定せず、「なるほど、そういう視点もあるね」と一度受け止める。インシデント発生時は個人を責めず、仕組みの問題として全員で再発防止策を考える。 | 誰もが安心して発言できる風通しの良い職場環境を作る。多様な意見から、より良いケアのアイデアが生まれる。 |
| 3. 明確なビジョンと目標の共有 | 「今月は『丁寧な言葉遣い』を徹底しよう」「半年後までに、褥瘡発生率をゼロにしよう」といった、チームが目指す方向性を具体的に示す。なぜその目標が必要なのか、背景や意義を丁寧に説明し、全員の納得感を得る。 | スタッフが同じ方向を向いて業務に取り組めるようにする。日々の業務に意味や目的を見出し、やりがいを感じてもらう。 |
これらのスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。日々の業務の中で意識的に実践し、時には失敗から学びながら、少しずつ自分なりの主任像を築いていくことが大切です。



私も常に意識はしていますが、これらを完璧にこなすことはまだできません。
看護師主任の苦悩・プレッシャーとの向き合い方
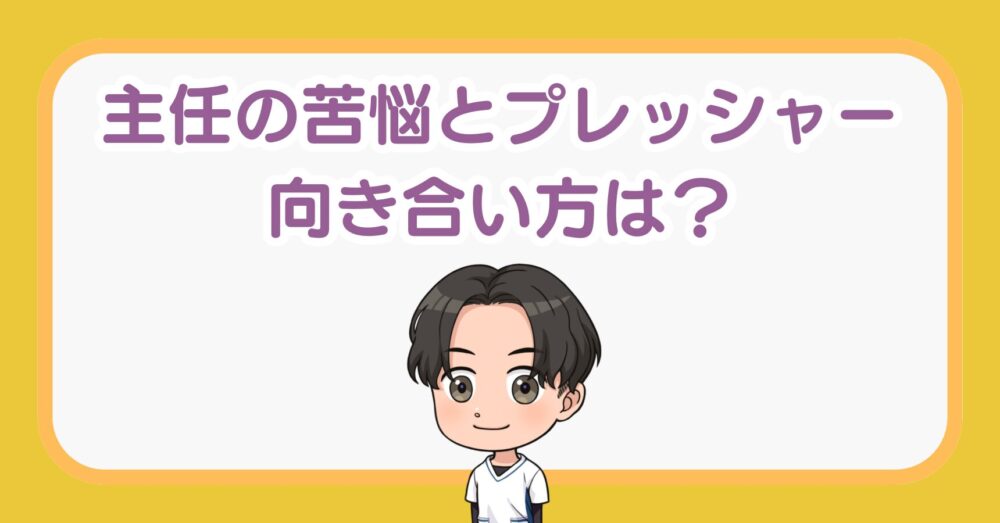
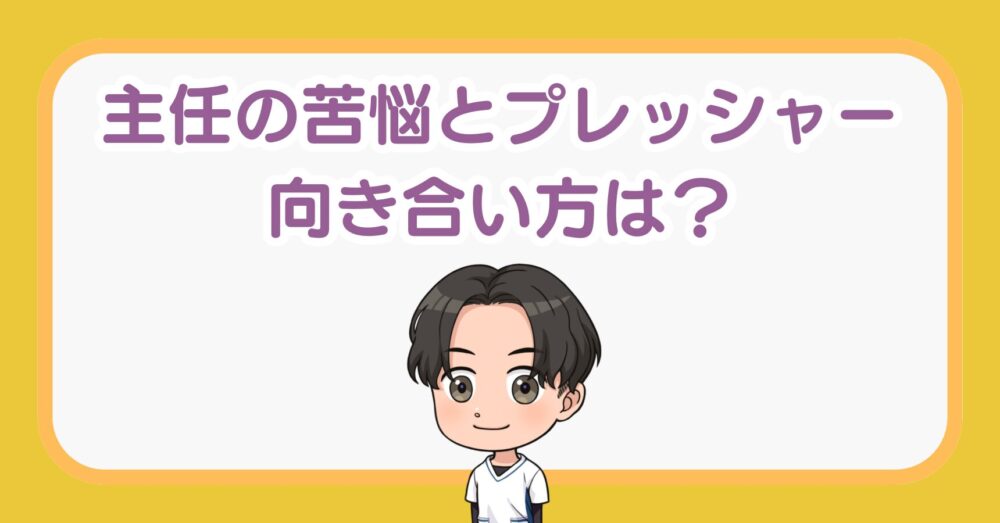
看護師主任は、現場のリーダーとして大きなやりがいを感じられる一方、その立場特有の苦悩やプレッシャーが伴います。ここでは、私が実際に経験した苦悩や、プレッシャーと上手に付き合っていくための具体的な方法をご紹介します。
- 責任の重さに押しつぶされそうになった経験
- 判断力と冷静さ|利用者の急変時の的確な指示経験
責任の重さに押しつぶされそうになった経験
主任になると、個人の責任だけでなく、チーム全体の責任を問われる場面が格段に増えます。スタッフが起こしたインシデントや、患者・家族からのクレーム対応など、矢面に立たなければならない状況は、想像以上の重圧です。
初めてクレーム対応を任された日
私が主任になって間もない頃、ある利用者さんのご家族から厳しいクレームを受けました。「スタッフの対応がいい加減で冷たい」という内容でした。まずは真摯に謝罪し、ご家族のお話を傾聴しましたが、怒りは収まりません。スタッフを守りたい気持ちと、組織として謝罪しなければならない立場の間で、どう振る舞うべきか頭が真っ白になりました。



最終的に施設長に助けを求めましたが、自分の無力さを痛感しました。
この経験から、クレーム対応は一人で抱え込まず、初期段階で上司に報告・相談する「エスカレーション」の重要性を学びました。
リーダー会議で吊るし上げられたこと
月に一度のリーダー会議は、主任にとってプレッシャーのかかる場のひとつです。
ある会議で、私の部署の残業時間が他部署より突出していることを指摘されました。データと共に「マネジメントができていないのではないか」「業務改善の意識が低い」と厳しい言葉を浴びせられ、まるで自分一人が責められているような感覚に陥りました。スタッフは日々懸命に働いてくれているのに、それを上手く伝えられず、守れなかった悔しさでいっぱいになりました。
この出来事をきっかけに、日頃から業務の課題やスタッフの頑張りを客観的なデータや具体的なエピソードとして記録し、いつでも説明できるように準備しておくことの必要性を痛感しました。
ストレスを溜めないために実践していること
主任としての重圧と上手く付き合っていくためには、セルフケアが不可欠です。ストレスは放置すると心身の不調につながり、良いパフォーマンスを発揮できなくなります。



ここでは、私が実践しているストレスマネジメント術をご紹介します。
質の高い休み方を意識する
休日に仕事のことが頭から離れない、という状態は多くの主任が経験しているのではないでしょうか。大切なのは、意識的に心と体を仕事から切り離すことです。
私は「デジタルデトックス」を心がけ、休日は仕事用のスマートフォンを見ないようにしています。代わりに、好きな音楽を聴きながら散歩をしたり、友人と全く仕事と関係のない話をしたりしてリフレッシュします。たとえ短い時間でも、自分が「楽しい」「心地よい」と感じることに没頭する時間を作ることが、次の勤務へのエネルギーになります。
上司との距離感を最適化する
上司である看護師長や施設長は、最も身近な相談相手です。しかし、評価者でもあるため、何でも話せるわけではないと感じるかもしれません。大切なのは、適切な距離感を保ちつつ、信頼関係を築くことです。
私は、業務上の報告・連絡・相談は迅速かつ客観的に行うことを徹底しています。その上で、少し雑談を交えたり、上司が関心を持っていることについて話したりして、円滑なコミュニケーションを心がけています。



一人で抱え込まず、良き相談相手として上司を頼ることで、精神的な負担は大きく軽減されます。
部署内外に相談相手を持つ
悩みを一人で抱え込むのは危険です。私は、立場や悩みを共有できる同期と定期的に情報交換をしています。「うちの職場でも同じ問題があるよ」と聞くだけで、孤独感が和らぎます。
客観的なアドバイスが欲しいときは、他部署の信頼できる先輩に相談することもあります。院内・施設内だけでなく、外部の研修で知り合った看護師や、学生時代の友人に話を聞いてもらうのも良いでしょう。必要であれば、専門の相談窓口を利用することも有効な手段です。日本看護協会では、看護職のための相談窓口を設けています。
自分自身が発しているストレスサインに早めに気づき、対処することも重要です。以下にストレスサインと対処法の例をまとめました。
| 心がけていること | 具体的な行動 | 目的・効果 |
| 身体的サイン | 頭痛、肩こり、不眠、食欲不振、疲労感が抜けない | 十分な睡眠をとる、バランスの良い食事を心がける、軽い運動(ストレッチや散歩)を取り入れる |
| 精神的サイン | イライラしやすい、不安感が強い、気分の落ち込み、集中力の低下 | 趣味に没頭する時間を作る、リラックスできる音楽を聴く、信頼できる人に話を聞いてもらう |
| 行動的サイン | 仕事のミスが増える、飲酒や喫煙量が増える、遅刻や欠勤が増える | 業務の優先順位を見直す、上司や同僚に相談して業務量を調整する、有給休暇を取得して休養する |



主任は大変なことも多いですが、その分大きなやりがいを感じられるポジションです。自分なりのストレス対処法を見つけ、前向きに役割を全うしていきましょう。
看護師主任に向いてる人・向いてない人
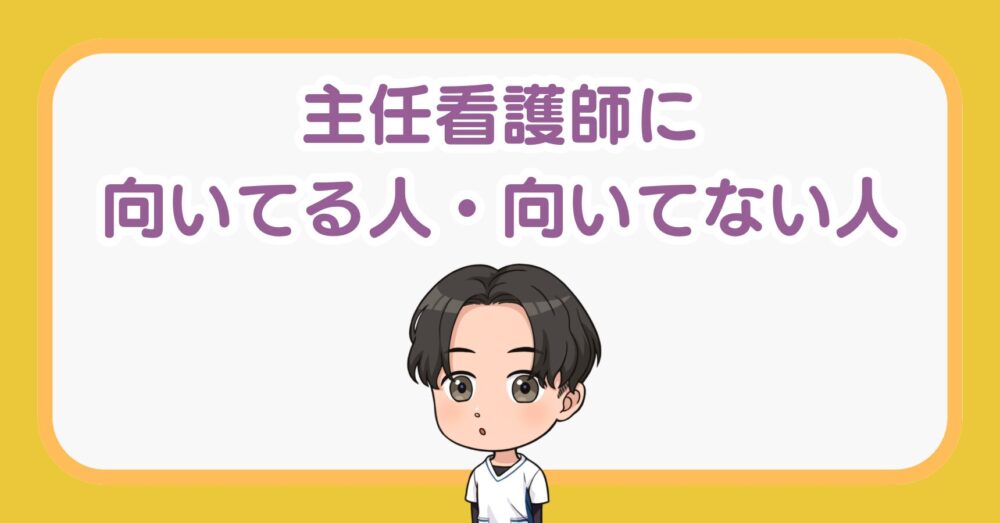
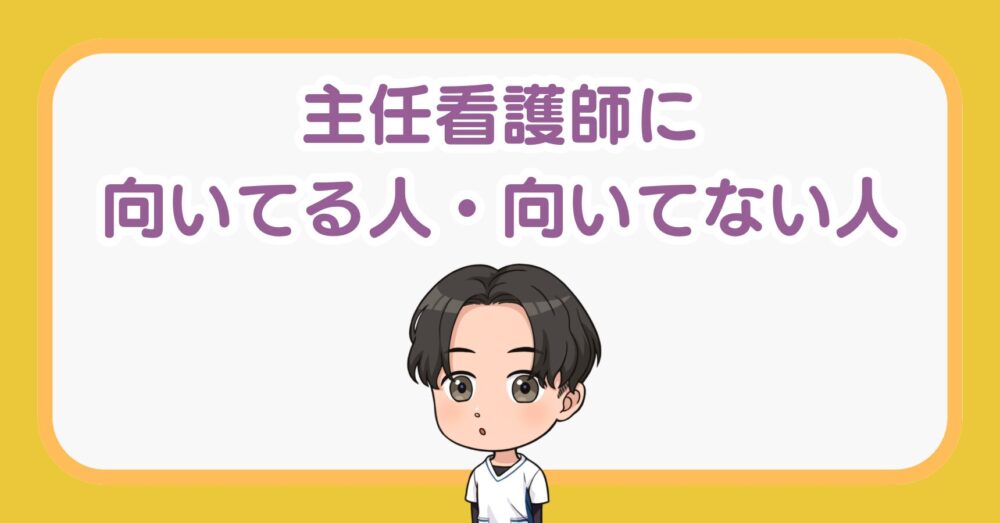
看護師主任は、スタッフの模範となりチームをまとめる重要なポジションです。そのため、求められる資質や適性があります。ここでは、看護師主任の役割をスムーズに果たすことに向いている人と向いていない人の具体的な特徴を、私の経験も踏まえて解説します。
向いている人の特徴
主任という役職は、単に看護スキルが高いだけでは務まりません。チーム全体を動かし、より良いケアを提供するための資質が求められます。以下のような特徴を持つ人は、看護師主任として活躍できる可能性が高いです。
≫看護師に向いている人の特徴5選!理想の職場選びのコツも解説
- 冷静で多角的に物事を見られる人
- 強い責任感を持ち、最後までやり遂げる人
- 人の成長を支援し、フォローするのが得意な人
冷静で多角的に物事を見られる人
医療や介護の現場では、利用者の急変やスタッフ間のトラブル、予期せぬクレームなど、突発的な出来事が日常的に発生します。そんな時、感情的にならずに状況を客観的に分析し、冷静に判断できる能力は主任にとって不可欠です。
一つの視点に固執せず、スタッフ、利用者様、ご家族、そして経営側の視点など、多角的に物事を捉えることで、最も適切で公平な解決策を導き出すことができます。



パニックにならず、常に一歩引いて全体を見られる人は、チームで頼れる存在となれるでしょう。
強い責任感を持ち、最後までやり遂げる人
主任は、自分の業務だけでなく、部署全体の運営やスタッフの行動、提供されるケアの質にも責任を負う立場です。部下の失敗をただ責めるのではなく、「自分の指導不足だったかもしれない」と考え、一緒に改善策を考える姿勢が求められます。
困難な課題や面倒な業務から逃げずに、部署の代表として最後までやり遂げる強い責任感と当事者意識は、上司や部下からの信頼を得るための土台となります。
人の成長を支援し、フォローするのが得意な人
主任の重要な役割の一つに「スタッフの育成」があります。自分の成功体験を押し付けるのではなく、一人ひとりの個性や能力、課題を理解し、成長をサポートすることに喜びを感じられる人は主任に向いています。
悩んでいるスタッフの話に耳を傾ける「傾聴力」、良い点を具体的に褒めて伸ばす「承認力」、そしてチーム全体の業務が円滑に進むように目配り・気配りをする「調整力」。こうした細やかなフォローができる人は、スタッフが安心して働けるポジティブな職場環境を作り出すことができます。



私の前任の主任は、この能力に長けていました。まさに目指すべき存在です。
向いていない人の特徴
一方で、以下のような特徴を持つ人は、看護師主任の役割を担うことで本人も周囲も苦労してしまう可能性があります。
≫看護師に向いてない人の特徴5選!実体験から学ぶ対処法と職場探しのコツを紹介
- 感情の起伏が激しく、態度に出やすい人
- 人間関係の調整や板挟みが苦手な人
- 自分本位で、チームより個人を優先する人
感情の起伏が激しく、態度に出やすい人
自分の機嫌によってスタッフへの態度を変えたり、ミスをした部下を感情的に叱責したりする人は、チームの雰囲気を著しく悪化させます。主任の感情的な言動は、スタッフを萎縮させ、報告・連絡・相談がしにくい職場環境を生み出す原因となります。



これは、重大なインシデントの隠ぺいにつながるリスクもはらんでいます。
常に安定した精神状態でいること、そして自分の感情をコントロールするスキルは、管理職にとって最低限必要な資質です。
人間関係の調整や板挟みが苦手な人
主任は、スタッフ同士、医師や他職種、そして上司と部下の間に立つ「調整役」であり、まさに「中間管理職」です。それぞれの立場や意見が衝突することも少なくありません。そんな時に対立を避けたり見て見ぬふりをしたりする人は、主任の役割を放棄しているのと同じです。
異なる意見を調整し、落としどころを見つけるといった、泥臭いコミュニケーションから逃げてしまう人は、チームを機能不全に陥らせてしまうでしょう。
自分本位で、チームより個人を優先する人
「自分はプレイヤーとして優秀だから」という意識が強く、チーム全体の成果よりも個人の都合ややり方を優先する人は、主任には向いていません。例えば、面倒な業務を部下に押し付けたり、自分のやり方だけが正しいと信じて他者の意見に耳を貸さなかったりする姿勢は、チームワークを根底から崩します。



主任に求められるのは個人のスーパースターではなく、チーム全体の力を最大限に引き出す監督役です。
ここまで解説した特徴を、より分かりやすく表にまとめました。ご自身の特性と照らし合わせてみてください。
| 観点 | 向いている人 | 向いていない人 |
| 問題発生時の対応 | 仕事のスタンス | 感情的になり、場当たり的な対応をしてしまう |
| 責任の捉え方 | チームの課題を自分事として捉え、最後まで関わる | 責任の所在を他者に求め、面倒なことから逃げようとする |
| 他者への関心 | スタッフの成長や働きやすさに関心を持ち、支援する | 自分の業務や評価にしか関心がなく、部下を放置する |
| コミュニケーション | 異なる意見を調整し、建設的な対話を促す | 人間関係の対立を避けたり、一方的な意見を押し付けたりする |
| 仕事のスタンス | チーム全体の利益や目標達成を最優先に考える | 自分のやり方や都合、個人の成果を優先する |
看護師のキャリアは多様であり、誰もが管理職を目指す必要はありません。臨床のスペシャリストや認定看護師など、様々な道があります。自身の適性やキャリアプランを考える上で、日本看護協会の示す看護職のキャリアパスなども参考に、自分に合った道を見つけることが大切です。
看護師主任の役割に関するよくある質問
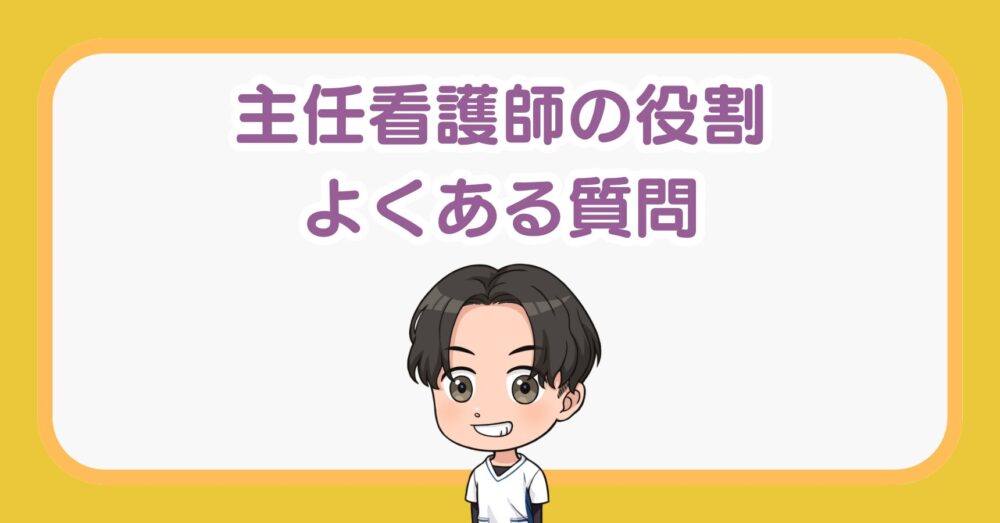
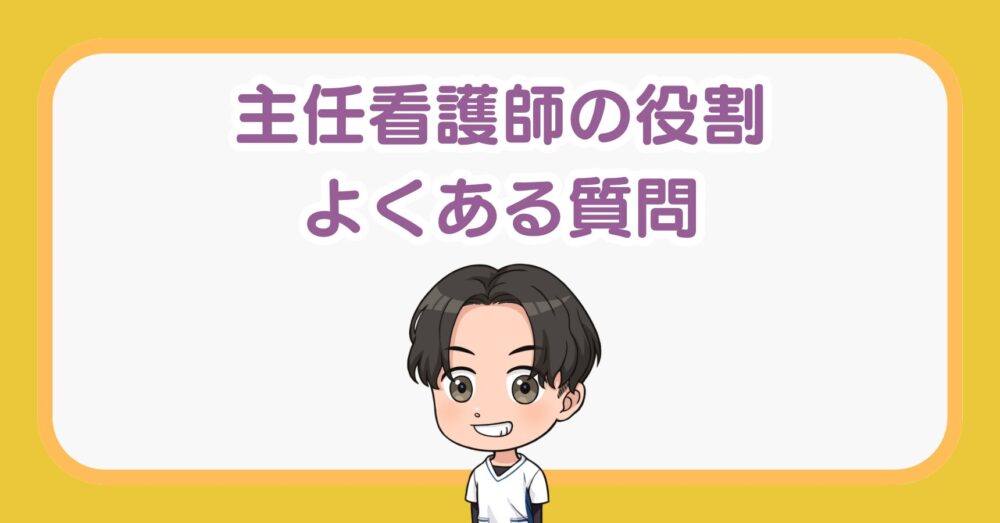
ここでは、主任看護師について多くの看護師が気になる質問に、現場の視点から具体的にお答えします。
- 主任看護師の年収はどのくらい?
- 昇格したらどのくらい忙しくなる?
- 主任になると夜勤はなくなる?
- 断ることはできる?断ると不利になる?
主任看護師の年収はどのくらい?
主任看護師の年収は、勤務する施設の形態(大学病院、一般病院、クリニック、介護施設など)、規模、地域、そして個人の経験年数によって大きく変動しますが、一般的には年収500万円〜650万円程度が目安となります。
≫看護師が主任になると年収はいくら上がる?現役主任の筆者が明かす給与の実態



厚生労働省の調査によると、看護師全体の平均年収は約508万円です。
主任に昇格すると、基本給の昇給に加えて「役職手当」が支給されるため、スタッフ看護師よりも高い給与水準となります。
役職手当の相場は月額1万円〜5万円程度ですが、これも施設によって差があります。以下に給与モデルの一例をまとめました。
| 役職 | 月収(目安) | 年収(目安) | 備考 |
| スタッフ看護師 | 約35万円 | 約508万円 | 夜勤手当など各種手当を含む。 |
| 主任看護師 | 約38万円~45万円 | 約550万円~650万円 | 基本給の昇給に加え、役職手当(月1~5万円程度)が上乗せされる。 |
より高い年収を目指す場合は、規模の大きい病院や給与水準の高い都市部の施設、あるいは専門性を活かせる分野への転職もキャリアプランの一つとして考えられるでしょう。
≫【2025年最新】看護師の給料は上がる?昇給時期・金額を徹底解説!



同じ主任でも、役職手当(1〜5万円目安)や基本給は職場で差が出ます。今の条件、相場と比べてみませんか?
昇格したらどのくらい忙しくなる?
結論から言うと、ほとんどの場合、スタッフ時代より忙しくなります。ただし、その「忙しさ」の種類が変化することを理解しておくことが重要です。
主任の忙しさは、主に以下の3つの側面から構成されます。
- 業務量の増加
- 自身の看護業務(プレイヤー業務)に加えて、スタッフの指導・育成、シフト管理、委員会活動、看護計画のチェック、各種レポート作成といったマネジメント業務が大幅に増えます。特に書類作成や会議のための時間外労働が発生しやすくなる傾向があります。
- 責任範囲の拡大
- 担当部署で起こるインシデントやトラブルの第一次対応、患者さんやご家族からのクレーム対応など、責任者として判断を求められる場面が増加します。常に部署全体に気を配る必要があり、精神的な緊張感は高まります。
- 役割の複雑化
- 現場のスタッフと看護師長や他部署との「板挟み」になりやすい立場です。双方の意見を調整し、円滑な連携を図るためのコミュニケーションコストは、目に見えない負担としてのしかかります。



もちろん、これらの忙しさは大きなやりがいにも繋がります。
チームをまとめ、より良い看護を提供できた時の達成感は、主任ならではのものです。昇格後は、いかに業務を効率化し、一人で抱え込まずに周囲を巻き込んでいけるかが、自身の負担を軽減する鍵となります。
主任になると夜勤はなくなる?
「役職が上がれば夜勤がなくなる」というイメージがあるかもしれませんが、主任の段階では夜勤の有無や回数は施設の方針によって大きく異なります。



私は主任になった時点で夜勤がなくなりましたが、一概になくなるとは言えません。
主なパターンは以下の通りです。
- 夜勤がなくなる・免除されるケース
- 看護師長と同様に管理業務に専念する体制が整っている大規模な病院など。日勤帯のマネジメントに集中するため、夜勤は他のスタッフに任されます。
- 夜勤回数が減るケース
- 最も多いパターンです。管理業務があるため回数は配慮されるものの、現場のリーダー業務や人員不足を補うために、月に数回の夜勤に入る必要があります。
- 夜勤回数が変わらない・むしろ責任者として入るケース
- 特に病床数の少ない病院や介護施設では、主任がプレイングマネージャーとして夜勤シフトの主軸を担うことも珍しくありません。夜間の責任者として、急変対応などの最終判断を任されます。
自身のライフプランと照らし合わせ、昇進後どのような勤務形態になるのかを事前に上司や人事に確認しておくことが非常に重要です。
≫看護師が夜勤をやめてよかった5つの理由|10年以上夜勤を続けた私の体験談
断ることはできる?断ると不利になる?
上司から主任への昇進を打診された際、自身のキャリアプランやプライベートの状況から、すぐに「はい」と返事ができない場合もあるでしょう。ここでは、昇進の打診に対する対応について解説します。
主任への昇進は断れる?
はい、断ること自体は可能です。昇進は強制ではなく、本人の意思が尊重されるべきものです。
ただし、断る際には伝え方が非常に重要です。単に「できません」「やりたくありません」と拒否するのではなく、まずは打診してくれたことへの感謝を伝えた上で、断る理由を誠実に説明しましょう。
例えば、「今はプレイヤーとして現場の看護スキルをさらに高めたい」「家庭の事情で、今は責任の重い役職に就くのが難しい」といった前向きな理由や正直な事情を伝えることで、上司も納得しやすくなります。今後の関係性を良好に保つためにも、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
昇進を断ると不利になる?
「不利になる」と一概には言えませんが、今後のキャリアに何らかの影響が出る可能性はあります。
考えられる影響としては、以下が挙げられます。
- 一度断ると、次の昇進の機会が回ってくるまでに時間がかかる、あるいは声がかかりにくくなる可能性がある。
- 「管理職への意欲が低い」と見なされ、人事評価にわずかに影響することがある。
- 役職手当がつかないため、同年代の主任クラスとの給与差が開いていく。
しかし、自分のキャパシティを超えて無理に引き受け、心身のバランスを崩してしまったり、マネジメントがうまくいかずに部署に混乱を招いたりする方が、結果的に自分にとっても組織にとってもマイナスです。



自分のキャリアで何を大切にしたいのかをじっくり考え、納得のいく決断をすることが最も大切です。
まとめ
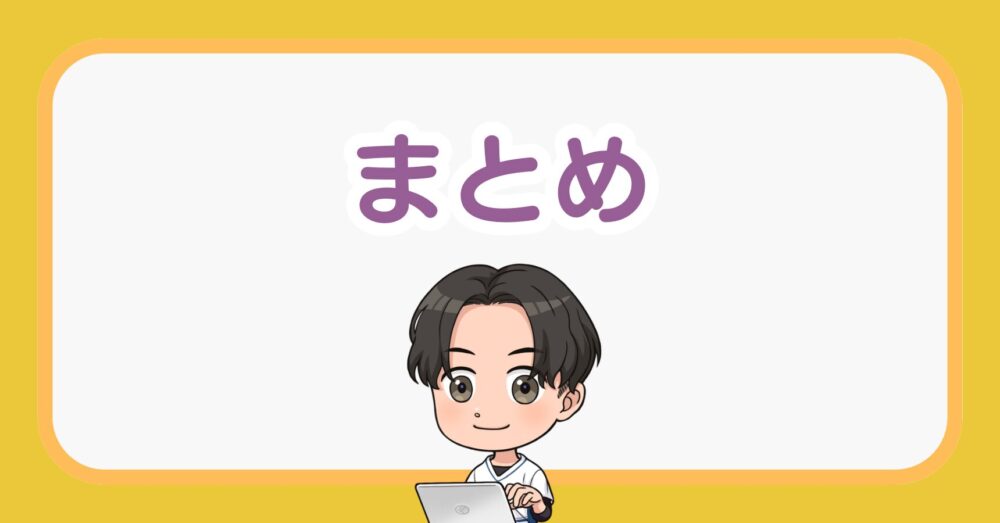
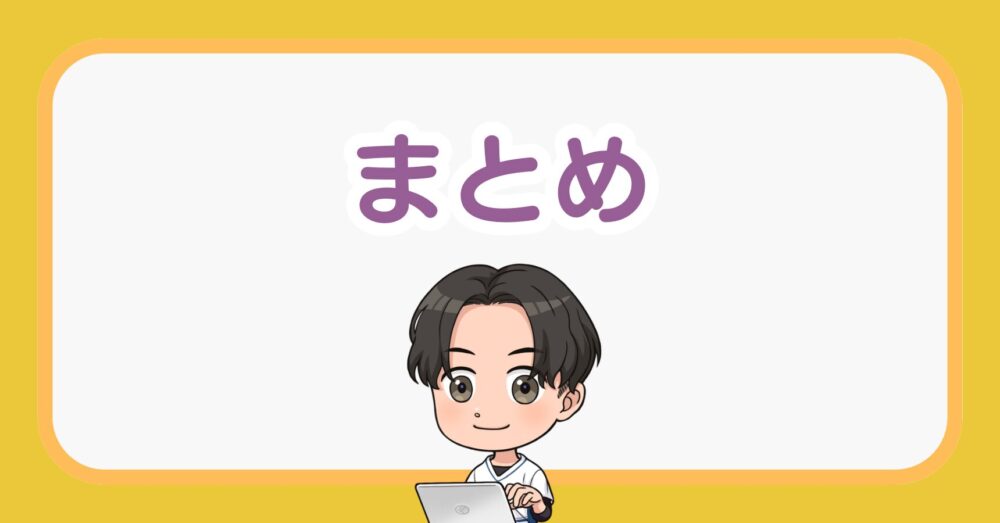
本記事では、現役主任の視点から看護師主任の役割、業務内容、必要なスキルについて詳しく解説しました。
主任は、師長の補佐やスタッフの教育、多職種連携など、現場と管理職をつなぐ重要な「橋渡し役」です。そのため、高いコミュニケーション能力や冷静な判断力が求められ、責任の重さからプレッシャーを感じることも少なくありません。
しかし、チームをまとめ、より良いケアを実現する大きなやりがいがあるのも事実です。この記事が、あなたのキャリアを考えるきっかけとなれば幸いです。
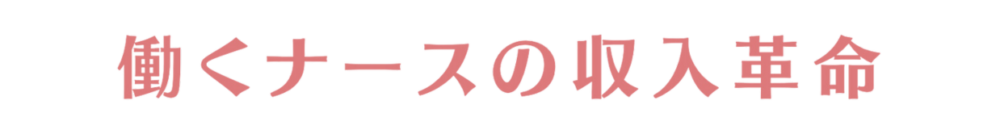


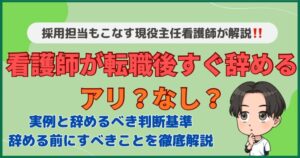
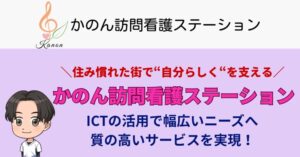
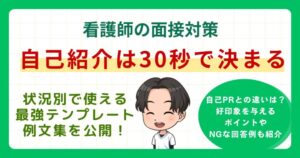

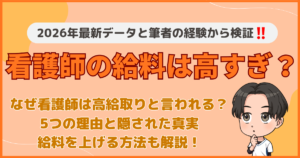
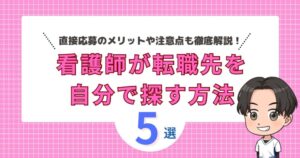
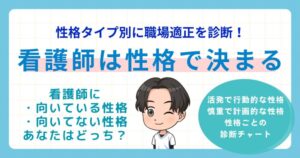

コメント