看護師の離職率は高く、多くの医療機関が人材確保に悩まされています。現役の看護師はさまざまな悩みを抱えているのが現状です。この記事では、看護師の離職率の現状や理由、離職率の高い・低い病院の特徴、離職率を低減する対策について解説します。
記事を読めば、自身のキャリアを見直す機会となり、よりよい職場環境を選ぶ方法がわかります。看護師の離職率を下げるには、労働環境の改善とキャリア支援が必要です。病院側と看護師が努力すれば、より働きやすい環境を作れます。
 ryanta73
ryanta73転職先を選ぶヒントにもなるので、それぞれの病院の特徴は理解しておきましょう。
看護師の離職率の現状
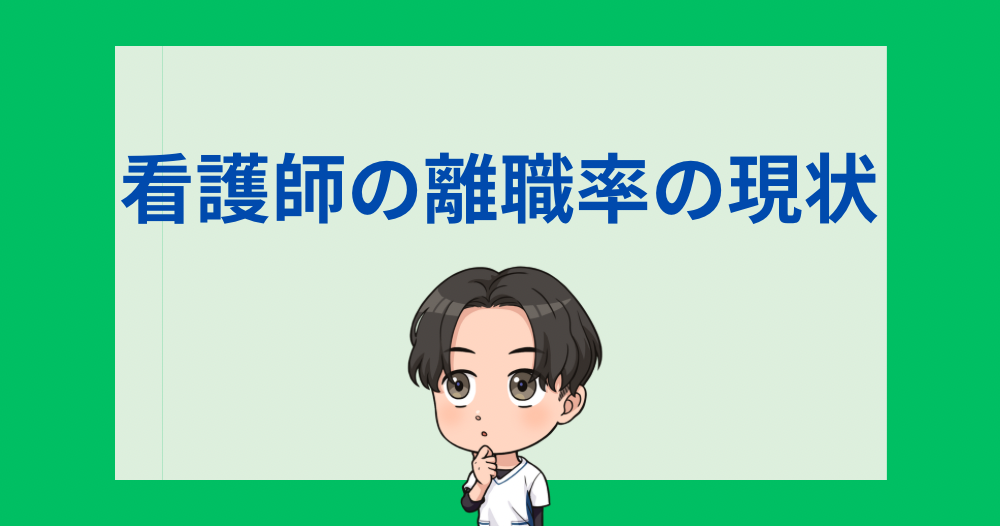
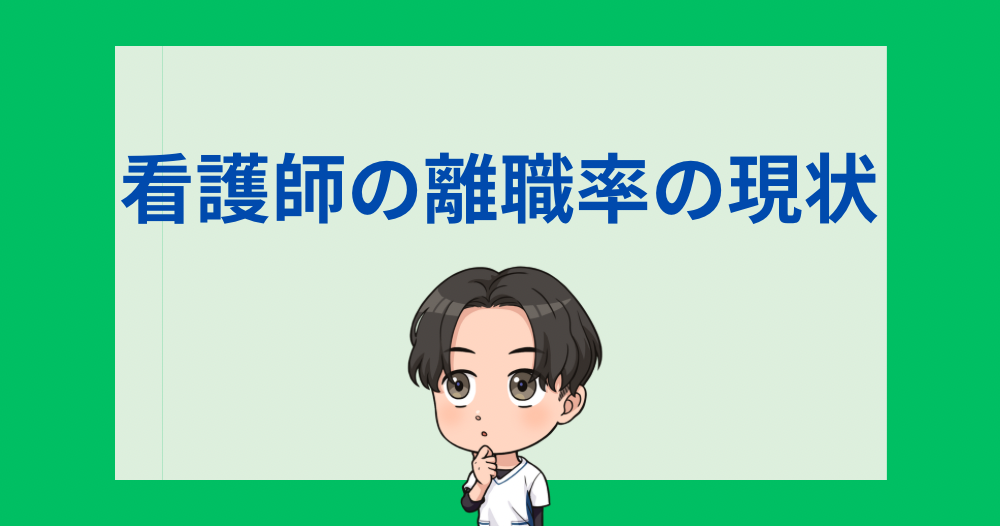
看護師の離職率の現状について、以下の3点を解説します。
- 全国平均離職率
- 都道府県別の離職率
- 病床規模・設置主体別の離職率
全国平均離職率
看護師の全国平均離職率は、2021年のデータでは10.6%です。新卒看護師は8.2%、常勤看護師は10.9%で、全産業の離職率(14.9%)より低い水準です。2010年以降、看護師の離職率は11%前後で推移しており、安定しています。
看護師の離職率は改善傾向にあり、2007年の12.6%から2%低下しました。新卒看護師の離職率も2004年の9.3%から改善しています。離職率は地域や病院の規模によって差があるため、すべての看護師や医療機関に当てはまるわけではありません。



このデータから看護師の離職率が改善傾向にあることが分かりますが、地域や病院の規模によって異なるため、個別の状況に応じた対策が必要です。
※出典:日本看護協会「2021 年病院看護・外来看護実態調査」
都道府県別の離職率


都道府県別の離職率には差があります。都道府県別の離職率は、以下のとおりです。
- 東京都が最も高く15.9%
- 沖縄県は2番目に高く15.5%
- 最も低いのは富山県で8.3%
- 2番目に低いのは石川県で8.7%
大都市圏や離島、北海道や九州などは離職率が高い傾向です。関東圏では、東京都に加えて神奈川県や千葉県も高めの離職率を示しています。関西圏では大阪府が高い離職率です。地方や中小都市では低い傾向にあります。中部地方や東北地方は全体的に離職率が低いのが特徴です。



この結果の理由として、都市部の過密労働や生活費の高さ、地方の人材不足や労働環境の違いなどが考えられます。
都道府県別の離職率の違いは、看護師として働く場所を選ぶ際の参考になります。離職率だけでなく、給与や労働環境なども考慮して、総合的に判断しましょう。
病床規模・設置主体別の離職率
病床規模・設置主体によって、看護師の離職率に違いがあります。病床規模が小さいほど離職率が高いのが現状です。99床以下の小規模病院では離職率が約15%と高く、500床以上の大規模病院では約10%と低くなっています。



大規模病院は小・中規模の病院と比べて高待遇だったり、部署異動などで離職を避けられたりすることが理由として考えられます。
設置主体別に見ると、民間病院の離職率が約12%と高いのが特徴です。公立病院が約9%、国立病院が約8%と低めの離職率です。精神科病院は一般病院より、療養型病床は急性期病床より、それぞれ離職率が高い傾向にあります。設置主体や病床規模によって、2〜7%の差があるのが現状です。
» 看護師の働き方を就業場所別、雇用形態別、勤務形態別に解説!
看護師が離職する理由
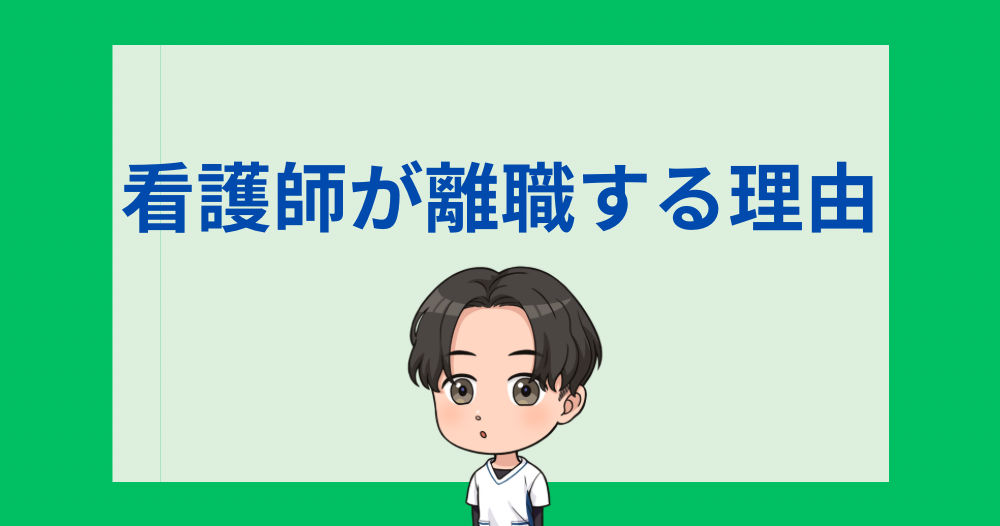
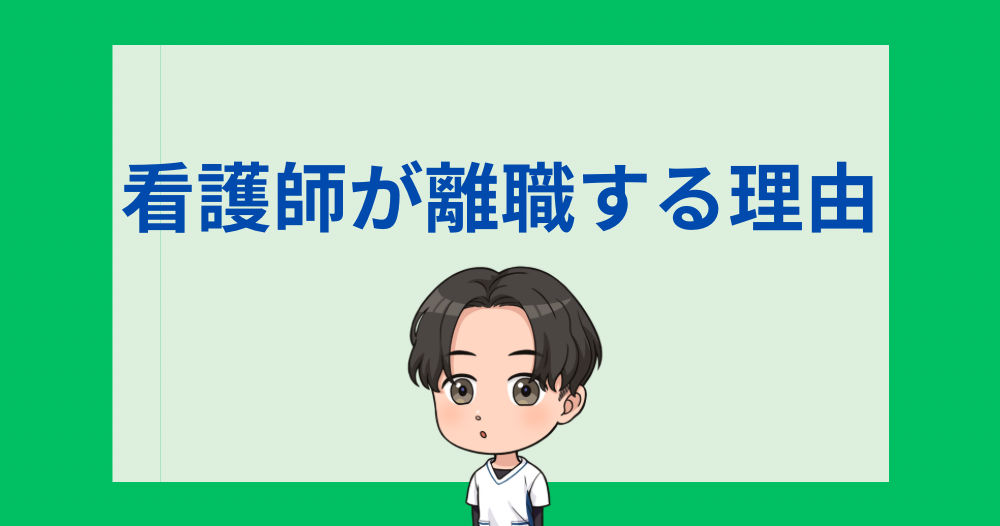
看護師が離職する理由として、以下の5点を解説します。
- 人間関係の問題
- 給与や待遇への不満
- 労働時間やワークライフバランスへの不満
- キャリアアップやスキルアップ
- 結婚・出産などのライフイベント
関連記事:看護師の私が転職で後悔した5つの原因|年収アップの裏でやらかした失敗と対策
人間関係の問題
職場での人間関係の問題は、離職を考える主な原因です。人間関係の具体的な問題は、以下のとおりです。
- 上司や同僚とのコミュニケーション不足
- チーム内での協力体制の欠如
- パワーハラスメントやいじめの存在
- 医師とのコミュニケーション不足
- 世代間のギャップ
人間関係の問題は、看護師の心理的負担を増大させ、仕事へのモチベーションを低下させます。改善するには、適切な対策が必要です。定期的なミーティングやチームビルディング活動を通じて、スタッフ間のコミュニケーションを促進しましょう。ハラスメント防止研修の実施や、相談窓口の設置も効果的な方法です。
人間関係の改善は、職場環境の向上につながり、看護師の離職率を下げます。良好な人間関係は、仕事の満足度を高め、キャリア形成に良い影響を与えます。
» 看護師の人間関係が悪化する原因や良好な職場の特徴を解説



職場文化の改善やリーダーシップの質も重要です。リーダーが積極的に部下の声に耳を傾け、支援する姿勢を示すことで、職場の雰囲気が改善し、離職率低下につながる可能性があります。
給与や待遇への不満
看護師の給与や待遇への不満は、離職の理由の一つです。多くの看護師が収入に満足していません。給与面での不満として、基本給の低さや手当が不十分、昇給のなさ、賞与の少なさが挙げられます。非正規雇用の看護師は、正社員と比べて不利な条件で働いている点も現状です。
待遇面での不満もあります。残業代が適切に支払われないことや福利厚生が不十分なこと、他の医療機関と比べて待遇が悪いなどの問題があります。地域や病院規模による給与格差も大きく、都市部と地方、大規模病院と小規模病院では給与に差がある点も現状です。
労働時間やワークライフバランスへの不満


労働時間やワークライフバランスへの不満は、離職理由の一つです。長時間労働や不規則な勤務シフトにより、プライベートな時間の確保が難しくなっています。休憩時間が十分に取れないことや、業務量が多すぎて時間内に仕事が終わらないことは、ストレスの要因です。
勤務時間外の研修や会議への参加も、ワークライフバランスを崩す原因です。夜勤明けの休息時間の不足も、看護師の体力や集中力の低下につながります。労働時間の問題を改善し、看護師が働きやすい環境を整えることが、離職率の低下につながります。
» 看護師の仕事がきついと感じる理由と対処方法を解説
キャリアアップやスキルアップ
キャリアアップやスキルアップの機会不足が、看護師の離職理由です。看護師は、専門性を高め、高度な医療に携わりたいと考えています。看護師は、キャリアの停滞を感じると転職を考えます。状況を改善するための病院側の取り組みは、以下のとおりです。
- 継続的な教育プログラムを提供
- 専門看護師・認定看護師の資格取得を支援
- 他の医療機関との人事交流を提供
- 最新の医療機器を扱う機会の提供
自己啓発の時間の確保や学会・研究発表への参加は、キャリアアップの効果的な手段です。看護師自身も、キャリアアップの機会を広げましょう。
結婚・出産などのライフイベント
多くの看護師が、家庭生活と仕事の両立に困難を感じているのが現状です。結婚や配偶者の転勤、出産・育児休暇後の職場復帰、子育てと仕事の両立などで悩んでいます。柔軟な勤務体制や育児・介護支援制度の充実が必要不可欠です。看護師が安心して働ける職場環境づくりが、離職率の低下につながります。
ライフステージの変化によって、価値観やキャリアプランが変わる場合があります。子どもの病気や、学校行事への対応と仕事の調整が難しいと感じる看護師が多くいるのが現状です。育児・介護休業制度が不十分な場合は、ワークライフバランスを重視した働き方へ転換する看護師も増えています。
» 看護師を辞めたいと感じる理由と退職手続きの流れを解説



まだまだ看護師は女性が多くを占めています。ライフステージの変化でやむを得ず離職を選ぶ人も多いです。
看護師の離職率の高い病院の特徴
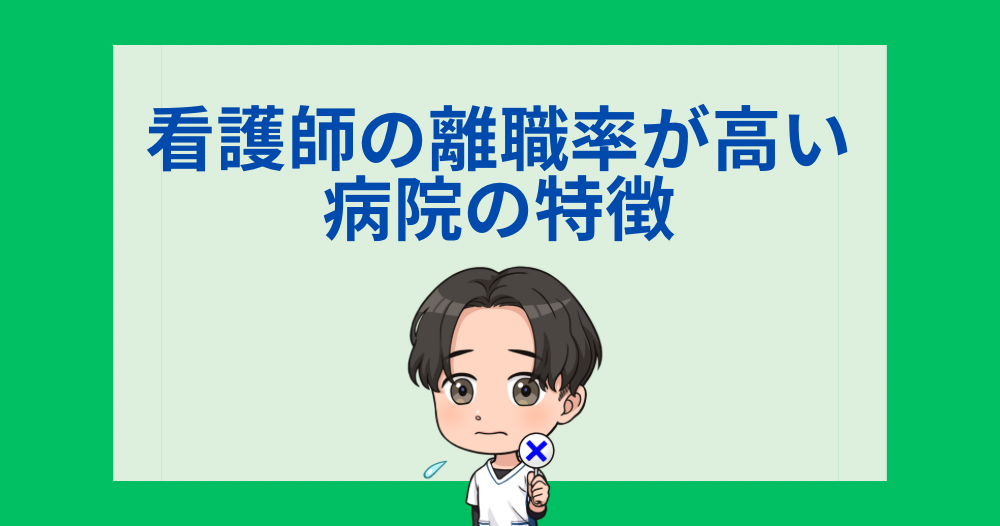
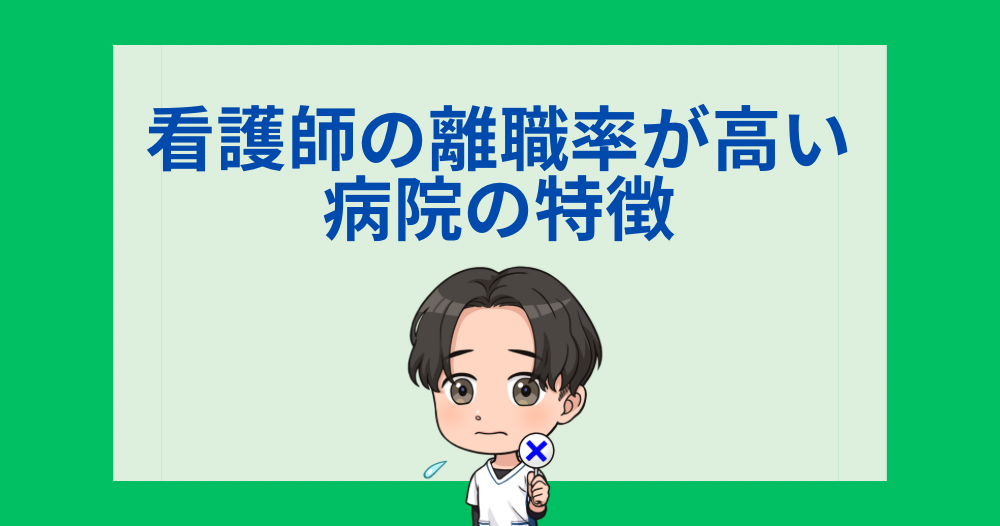
看護師の離職率が高い病院の特徴は以下のとおりです。
- 規模が小さい
- 民間が運営している
- 慢性的な人手不足が続いている



すべての該当病院が悪いわけではないので、実際の労働環境や待遇を確認しましょう。
規模が小さい
規模が小さい病院は、看護師の離職率が高い傾向があります。小規模病院では、経営資源に限りがあるため、待遇改善や設備投資が難しい状況です。大規模病院と比べて給与水準が低く、一人あたりの業務負担が大きくなる特徴があります。
休暇取得や勤務シフトの調整が難しく、キャリアアップの機会や専門性を高める環境が整っていないのが現状です。最新の医療機器や設備が不足していたり、経験できる症例が限られていたりします。



一方で、コミュニケーションが取りやすく、家族的な雰囲気の中で働ける点は小規模病院のメリットです。
民間が運営している
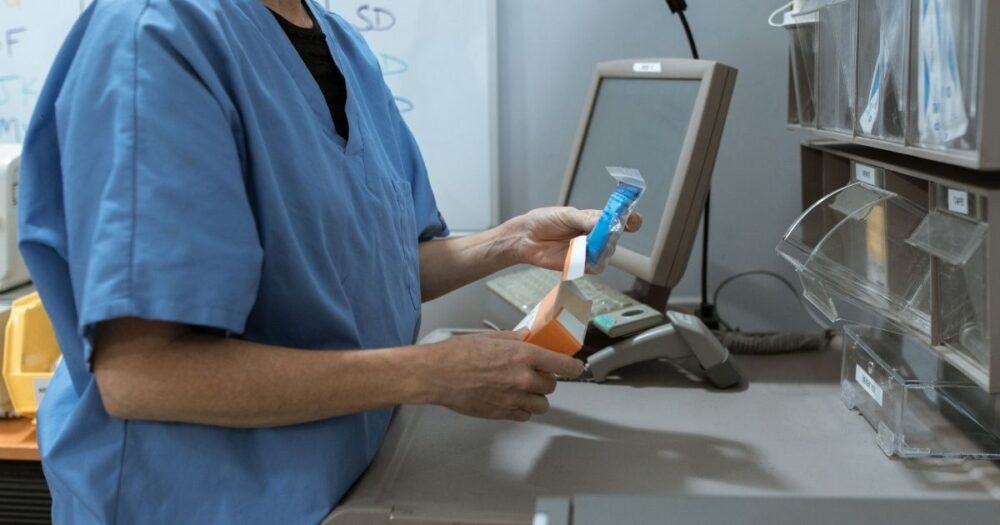
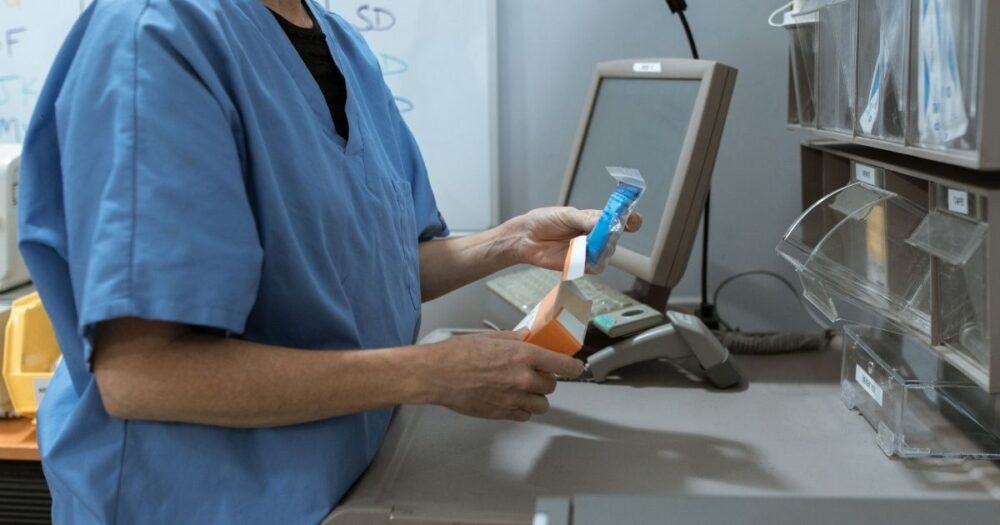
民間が運営している病院は、経営方針と労働環境が看護師の離職率の高さに関係しています。利益を重視して看護師の労働環境改善に消極的な場合が多いからです。民間が運営している病院の問題点は、以下のとおりです。
- 給与水準が低い
- 人員の配置が少ない
- 福利厚生制度が充実していない
- 教育・研修制度が少ない
経営状況によって待遇が変動しやすいのも特徴になります。労働組合がない場合が多く、看護師の声が経営陣に届きにくいのが現状です。人事評価制度が不透明や未整備なことも多く、キャリアアップの機会が限られています。長時間労働や夜勤が多いので、ワークライフバランスを保てません。
慢性的な人手不足が続いている
慢性的な人手不足は、多くの医療機関が抱える問題の一つです。看護師一人あたりの業務負担の増加や残業、休日出勤の多さは、疲労やストレスが蓄積する原因です。人手不足は、患者へのケアの質にも影響します。時間をかけて丁寧なケアを行えないからです。
新人教育に時間を割けられず、人材育成や組織づくりも困難になっているのが現状です。職場の雰囲気が悪化しやすく、離職者が出ると悪循環に陥ります。多くの医療機関が採用活動を行っていますが、人材確保は容易ではありません。
慢性的な人手不足は、看護師にとって負担ですが、経験豊富な看護師にとってはキャリアアップのチャンスです。人手不足の中で培った経験や技能は、キャリアの強みとなります。
» 看護師の転職タイミングとは?理想の職場の探し方
看護師の離職率の低い病院の特徴
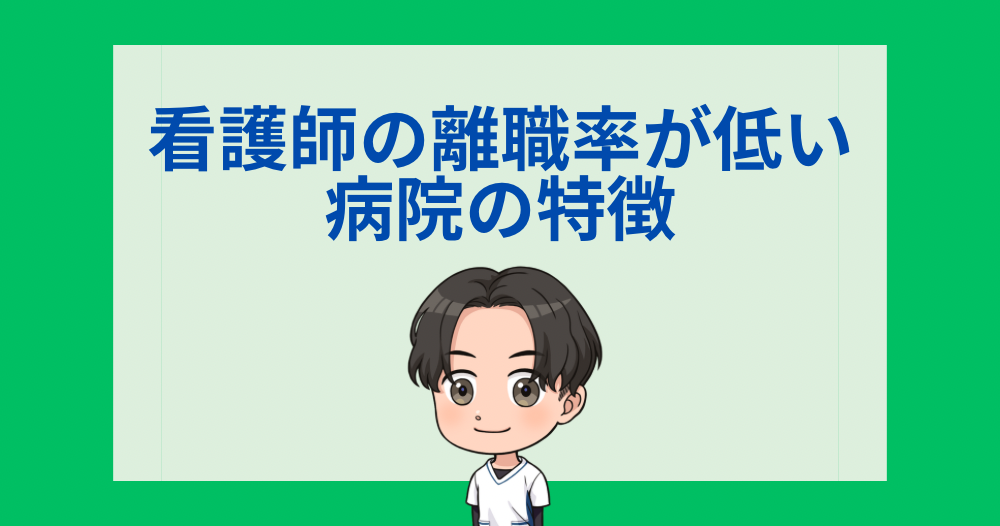
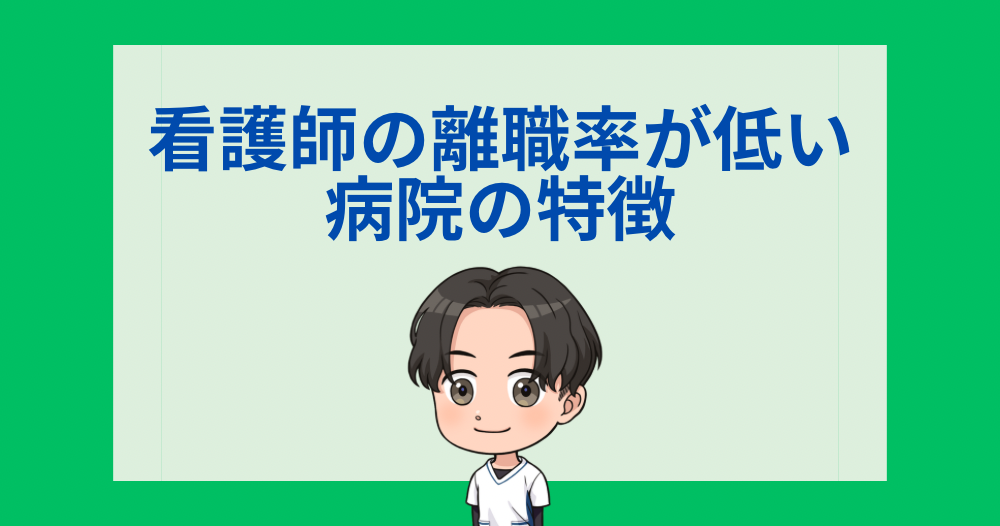
看護師の離職率の低い病院の特徴は以下のとおりです。
- 福利厚生が充実している
- 職場の雰囲気が良い
- 教育・研修制度が整っている
福利厚生が充実している
福利厚生の充実は、離職率を低く抑える重要な要因です。多くの病院では、看護師をサポートするさまざまな制度があります。健康診断や人間ドック、育児・介護支援制度、住宅手当や寮の提供、有給休暇やリフレッシュ休暇などです。
福利厚生は、看護師の生活の質を向上させるだけでなく、仕事への満足度も高めます。資格取得支援制度や奨学金返済支援、退職金制度などはキャリアアップを助けてくれます。院内保育所や食事手当、通勤手当は日常生活の負担軽減に効果的な福利厚生です。



規模が大きい病院ほど、福利厚生が充実している傾向があります。
職場の雰囲気が良い


雰囲気の良い職場は、看護師の離職率を低下させます。良好な職場環境は、仕事へのモチベーションを高め、長期的な勤務を促進します。雰囲気が良い職場の特徴は以下のとおりです。
- コミュニケーションが取りやすい
- 協力的な雰囲気がある
- 上司・先輩がサポートしてくれる
- 意見や提案を尊重してくれる
- ハラスメントやいじめがない
- 失敗を責めずに改善点を一緒に考えてくれる
- 仕事とプライベートの境界線が明確にある
- 専門性や役割を尊重し合える
- 親睦会や交流イベントが定期的にある
職場の雰囲気が良いと、看護師同士の絆が深まり、協力的な職場環境になります。



看護師にとって雰囲気の良い職場は貴重なので、多少条件に難があっても働き続ける人が多いです。
教育・研修制度が整っている
教育・研修制度が整っている病院は、看護師のスキルアップとキャリア発展に積極的です。仕事への満足度が高まり、離職率が低下します。新人向けの充実した研修プログラムや定期的なスキルアップ研修、専門資格取得のためのサポートなどが効果的な制度です。
院内勉強会や症例検討会を定期的に開催し、知識や技術を学ぶ機会を提供する病院もあります。最新の医療技術や機器の使用方法を学べ、最新の医療に対応できる力を身に付けられる点が特徴です。さまざまな角度から成長をサポートする教育・研修制度が整っていることは、離職率の低い病院の特徴です。
» 大学病院看護師の年収は?具体的な年収と年収アップの方法を解説
看護師の離職率を低減するための対策
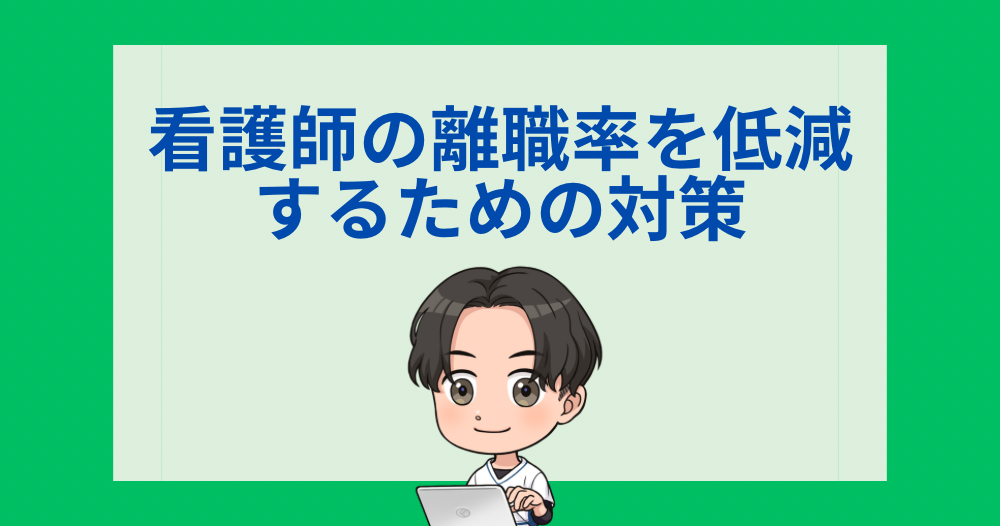
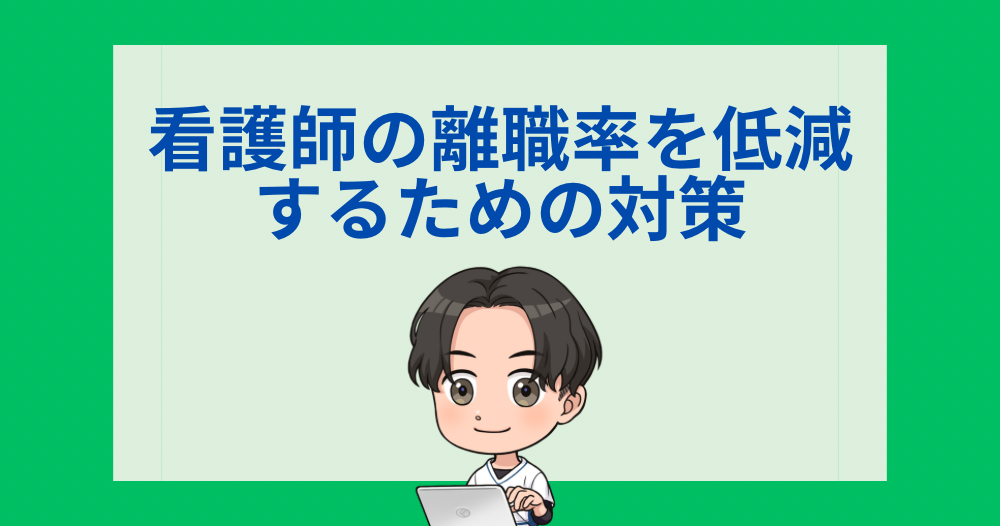
看護師の離職率を低減する対策は、ワークライフバランスの改善やモチベーションの向上が期待できます。看護師の離職率を低減する対策は、以下のとおりです。
- コミュニケーションの促進
- 労働環境や条件の見直し
- メンタルヘルスケアの充実
- キャリアアップの支援
- 昇進・昇給制度の明確化
コミュニケーションの促進
コミュニケーションの促進は、離職率を低減する重要な対策です。職場内での良好な人間関係を築け、仕事への満足度が高まり、離職を防げます。定期的な面談や個別相談、チーム制の導入、部署間の交流イベントなどが効果的な手段です。



コミュニケーションを促進することでスタッフ間の信頼関係が深まり、問題の早期発見や解決につながります。
オープンな意見交換の場を設けると、職場の雰囲気が改善され、働きやすい環境が整います。SNSやグループチャットを活用し、リアルタイムで情報共有をしましょう。匿名での意見箱を設置すれば、直接言いづらい意見も収集できます。看護師一人ひとりが大切にされていると感じられる職場づくりが、離職率低減のために大切です。
≫【実体験】看護師の人間関係がドロドロすぎる…乗り越えた私の7つの対処法
労働環境や条件の見直し
適切な労働環境や条件を整えると、看護師の満足度が向上し、長く働き続けられます。看護師の身体的・精神的負担を軽減し、夜勤や交代勤務のスケジュールを改善させましょう。無理のない勤務体制を整えると、ワークライフバランスが取りやすくなります。労働環境や条件の見直しは、以下の対策が効果的です。
- 労働時間の適正化と残業削減
- 柔軟な勤務体制の導入
- 給与体系の見直しと昇給制度の改善
- 有給休暇の取得促進
- 休憩時間の確保と休憩スペースの整備
育児・介護支援制度の充実や福利厚生の拡充も効果的な手段です。保育所の設置や住宅手当の支給など、生活面でのサポートがあれば、仕事に集中できます。業務の効率化や最新の設備や機器の導入、安全対策の徹底も必要な対策です。病院側の長期的な視点での人材確保・育成が求められています。
≫看護師の休みが少ない理由とは?希望通りに休むコツとおすすめの職場も紹介!
メンタルヘルスケアの充実


ストレスの多い医療現場で働く看護師のメンタルヘルスを守れば、離職防止につながります。ストレスチェックやメンタルヘルス研修は、看護師の心の健康を守るための有効な手段です。上司や同僚によるサポート体制の構築や産業医との連携強化など、職場全体でメンタルヘルスケアに取り組みましょう。
ワークライフバランスの推進や休暇取得の促進は、メンタルヘルスケアの一環です。仕事と生活のバランスを取れると心身のリフレッシュにつながります。メンタルヘルスケアは離職防止だけでなく、医療サービスの質の向上にも役立ちます。心身ともに健康な看護師は、患者に寄り添えるからです。



現在では、事業者はストレスチェックなどを実施して従業案のメンタルヘルスケアを行うことが義務付けられています。
キャリアアップの支援
多くの看護師は、自身のスキルを向上させ、より高度な医療に携わりたいと考えています。キャリアアップの支援があれば、看護師は自身の成長を実感でき、モチベーションの向上につながります。支援制度を設けるだけでなく、看護師のニーズに合わせて柔軟に対応できると効果的です。
専門看護師や認定看護師を目指す人には、資格取得に向けた時間や受験費用の補助などがあると助かります。管理職を目指す人には、リーダーシップ研修やマネジメント講座への参加機会などが必要な支援です。看護師一人ひとりのキャリア目標に応じた支援により、職場への定着率を高められます。
昇進・昇給制度の明確化
昇進・昇給制度の明確化は、看護師の離職率を下げる重要な対策の一つです。多くの看護師は、自身のキャリアパスや給与の上昇について不安を感じています。不安を解消し、モチベーションを高めるには、透明性のある昇進・昇給制度が必要です。昇進・昇給制度の改善策は以下のとおりです。
- 明確な昇進基準を設定する
- 定期的な評価制度を導入する
- 業績連動型の昇給システムを構築する
- キャリアラダーを導入する
スキルアップに応じた給与体系の整備が求められています。資格取得支援制度を充実させ、新しい知識や技術を習得した看護師に対して適切な評価と報酬を与えましょう。昇進・昇給制度の明確化は、看護師のキャリア形成を支援し、職場への定着率を高めます。病院側は優秀な人材を確保・育成できる有効な手段です。
まとめ


看護師の離職率は全国平均離職率は約10%ですが、地域や病院の規模によって差があります。離職の理由は、人間関係や給与、労働条件、キャリア、ライフイベントなどがあります。小規模な病院や民間病院、慢性的な人手不足に悩む病院は、離職率が高い点が特徴です。
福利厚生や職場環境、教育制度が充実している病院は離職率が低くなっています。離職率を低減するための対策が求められています。看護師の職場定着率を高め、医療サービスの質の向上につなげましょう。
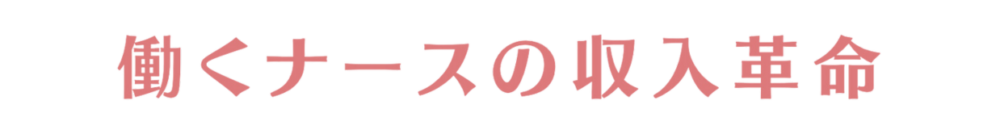
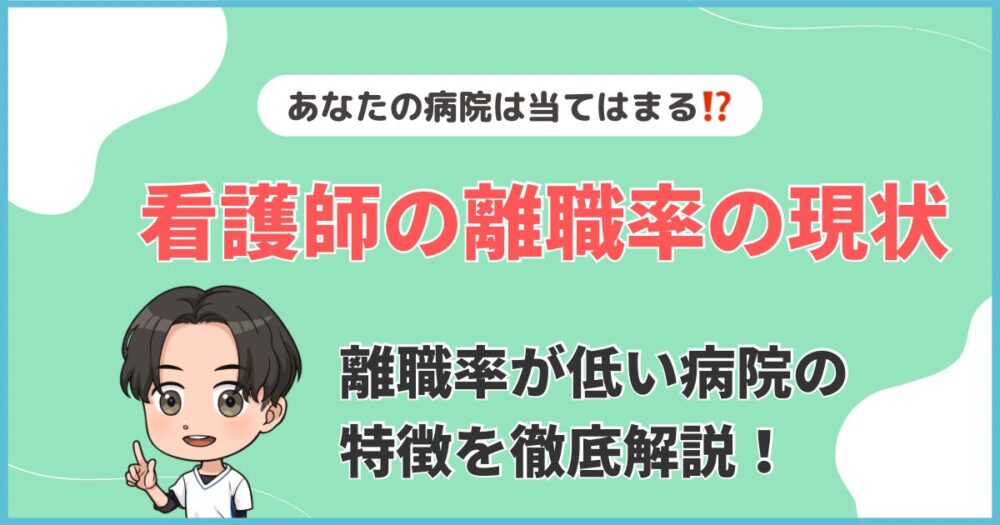

コメント