「もしかして私、看護師に向いてないかも…」と辛い気持ちを抱えていませんか?ひとつの失敗が患者の健康に関わることもある看護師の仕事。これは多くの看護師が一度は抱える悩みでもあります。
日本看護協会「2023年病院看護実態調査」によると、新卒看護師の離職者の約45%は「看護職員としての適正の不安」が理由です。
 ryanta73
ryanta73私も本気で看護師に向いてるのか悩んだ時期がありました。今でもたまに思いますが、それでも今は主任としてリーダーシップを発揮できているのも事実です。
この記事では、看護師に向いていないと感じる一般的な理由や特徴、そして悩んだ時の具体的な対処法を、自身の体験をもとに解説します。さらに、自分らしく働ける職場探しのコツもご紹介。
記事を読めば、今の悩みを整理し、あなたに合った働き方や次のステップを見つけるヒントが得られるでしょう。もし看護師に向いていないと感じても、必ずしも諦める必要はありません。
看護師に向いてないと感じる理由
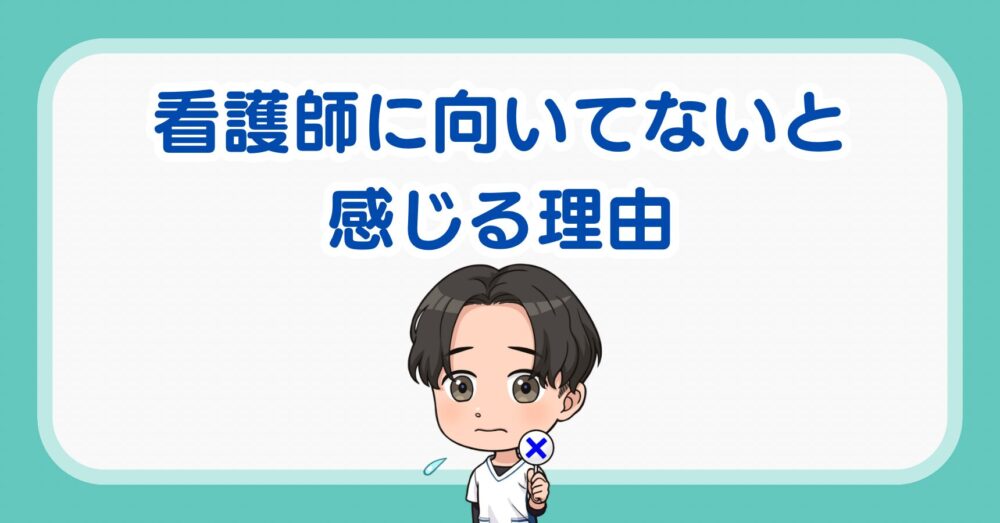
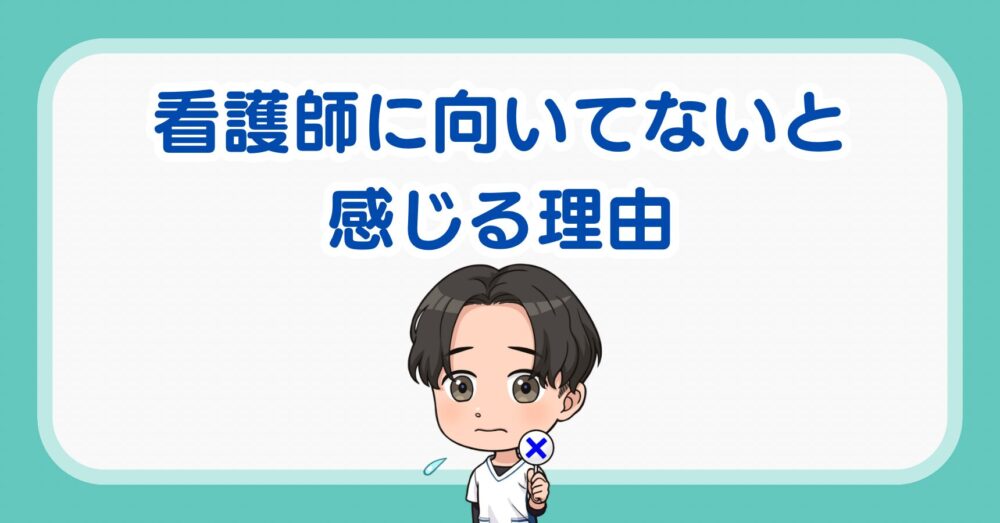
看護師が「向いていない」と感じてしまう具体的な理由について、深く掘り下げていきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。
- スキルや知識の不足による不安
- 命に関わる責任への重圧
- 人間関係や職場環境の問題
- ワークライフバランスの難しさ
≫看護師の仕事がきつい理由と転職を考えるタイミングについて解説!
スキルや知識の不足による不安
看護師の仕事は、常に新しい知識や技術の習得が求められます。医療は日々進歩しており、昨日までの常識が今日には通用しなくなることも少なくありません。この絶え間ない学習へのプレッシャーや、実際の現場で求められるスキルとのギャップが、大きな不安につながることがあります。
≫看護師4年目で「仕事できない」と悩む方へ|挫折を乗り越え主任になった私の乗り越え方
①絶えず求められる学習とアップデート
医学・看護学の進歩は目覚ましく、新しい治療法、薬剤、医療機器が次々と登場します。また、担当する診療科や部署が変われば、新たに専門知識を深く学ばなくてはなりません。
院内研修や自己学習が欠かせませんが、「勉強しても追いつかない」「新しいことを覚えるのが苦手だ」と感じると、スキル不足への不安が募り、「向いていないのでは?」という思いにつながりやすくなります。
②実践でのギャップとミスへの恐怖
教科書や研修で学んだ知識・技術が、実際の臨床現場でスムーズに活かせるとは限りません。患者の状態は一人ひとり異なり、マニュアル通りにいかない場面も多々あります。
特に新人看護師の場合、採血や点滴、ルート確保、体位変換、清拭、褥瘡ケアといった基本的な看護技術でさえ、最初は戸惑うことが多いでしょう。経験を積んだ看護師でも、アセスメント能力や急変時の対応など、より高度なスキルが求められる場面で、「自分の判断は正しかったのか」「もっとうまくできたのではないか」と不安を感じることがあります。
些細なミスが患者の状態に影響を与えかねないという緊張感は、常に付きまといます。



一度大きなミスを経験すると、それがトラウマとなり、自信を喪失してしまうこともありますよね。
命に関わる責任への重圧
看護師の仕事は、人の命や健康に直接関わる責任の重い職業です。その責任の重さが精神的な負担となり、「自分には荷が重すぎる」と感じてしまうことがあります。
患者のバイタルサインのわずかな変化を見逃さず、異常の早期発見に努めること、医師の指示を正確に実施すること、薬剤の投与量を間違えないことなど、看護業務の一つひとつに高い正確性が求められます。常に「間違ってはいけない」というプレッシャーの中で働き続けることは、精神的に大きな負担です。自分の判断や行動が患者に与える影響の大きさに、押しつぶされそうになることもあるでしょう。
患者の容態が急変する場面に遭遇することも多いです。心停止や呼吸困難など、一刻を争う状況下で、冷静かつ迅速・的確な判断と処置が求められます。このような緊迫した状況は、たとえ経験豊富な看護師であっても、強いストレスを感じるものです。急変対応が苦手だったり、パニックに陥りやすかったりすると、「自分は緊急時に役に立てないのではないか」と無力感を覚え、向いていないと感じる一因となります。
どれだけ注意していても、ヒューマンエラーを完全になくすことは困難です。インシデント(ヒヤリ・ハット)やアクシデント(医療事故)を起こしてしまった場合、患者や家族への謝罪はもちろん、報告書の作成、原因分析、再発防止策の検討など、精神的に大きな負担がかかります。自責の念に駆られたり、周囲からの視線が気になったりすることで、「もう看護師を続けられない」と感じてしまうこともあります。
人間関係や職場環境の問題


看護師が働く職場は、様々な職種の人々が協力し合い、チームで医療を提供しています。しかし、その特殊な環境ゆえに、人間関係の悩みや職場環境への不満が「向いていない」と感じる大きな要因となることがあります。
①医師や他職種との連携の難しさ
医師、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師、放射線技師、ケアマネージャーなど、多くの専門職と連携して患者さんのケアにあたります。それぞれの専門性や立場が異なるため、時には意見の対立やコミュニケーション不足が生じることもあります。
特に医師との関係においては、指示受けや報告・連絡・相談(報連相)の際に、高圧的な態度を取られたり、意見を聞き入れてもらえなかったりすると、ストレスを感じやすくなります。「多職種と円滑なコミュニケーションをとるのが苦手だ」と感じると、チーム医療の一員として働くことに困難を感じるかもしれません。



医師とのコミュニケーションは、全看護師が抱える悩みといっても過言ではありません。そんなときは、看護師が「一人でできる仕事」を選ぶのも良いでしょう。以下の記事で詳しく解説しています。
②複雑な同僚間の関係性
看護師の職場は女性が多い傾向にあり、独特の人間関係が存在する傾向があります。先輩からの厳しい指導(時には指導の範囲を超えたパワーハラスメント)、同僚間の派閥や陰口、無視といった、いわゆる「お局様」問題やいじめに悩むケースも聞かれます。
新人や中途採用者に対して十分なサポート体制が整っておらず、孤独感を深めてしまうこともあります。常に周囲に気を遣い、人間関係に疲れ果ててしまうと、「この職場で働き続けるのは無理だ」と感じ、看護師自体に向いていないと考えてしまうことがあります。
≫【実体験】看護師の人間関係がドロドロすぎる…乗り越えた私の7つの対処法
③患者・家族とのコミュニケーションストレス
患者や家族とのコミュニケーションも看護師の重要な役割ですが、時に大きなストレスとなることがあります。病気や怪我による不安や痛みから、感情的になったり、理不尽な要求をされたりすることもあります。
患者の死に直面したり、家族の悲しみに寄り添ったりする中で、精神的に消耗してしまうことも少なくありません。クレーム対応や難しい説明を求められる場面で、うまく対応できない状況が続くと、対人援助職としての適性に疑問を感じてしまうかもしれません。
ワークライフバランスの難しさ
看護師の仕事は、その勤務形態や業務内容から、プライベートとの両立が難しいと感じる場面が多くあります。仕事と私生活のバランスが取れないことが、「向いていない」と感じる理由になることも少なくありません。
①不規則な勤務形態と長時間労働
病院勤務の場合、夜勤を含む交代勤務が一般的です。2交代制や3交代制など、勤務形態は様々ですが、いずれも生活リズムが不規則になりがちです。夜勤明けでも十分な休息が取れなかったり、休日に緊急の呼び出しがあったりすることもあります。人手不足や業務量の多さから、定時で帰れず長時間労働になることも珍しくありません。
一般的な勤務形態とその特徴を以下に示します。
| 勤務形態 | 特徴 | 負担となりやすい点 |
|---|---|---|
| 2交代制 | 日勤(例: 8:30~17:30) 夜勤(例: 17:00~翌9:00) | 1回の夜勤拘束時間が長い(16時間程度)。勤務間のインターバルが短くなることがある。生活リズムの調整が難しい。 |
| 3交代制 | 日勤(例: 8:30~17:30) 準夜勤(例: 16:30~翌1:30) 深夜勤(例: 0:30~9:30) | 勤務間隔が短くなりやすく、十分な睡眠時間を確保しにくい。深夜勤前の仮眠や、準夜勤後の休息など、自己管理が重要。疲労が蓄積しやすい。 |
このような不規則な勤務や長時間労働は、体力的にも精神的にも大きな負担となり、「長く続けられる仕事ではない」と感じる原因となります。
≫「夜勤が体に悪いは嘘」という主張の真相|体験談とデータから見る正しい健康管理法
心身の疲労と健康への影響
不規則な生活や睡眠不足、立ち仕事や移乗介助などによる身体的な負担、そして精神的なストレスが積み重なることで、心身の不調をきたす看護師は少なくありません。肩こり、腰痛、不眠、食欲不振、頭痛、メンタルの不調(抑うつ気分、不安感など)といった症状が現れることもあります。
自身の健康を犠牲にしてまで働き続けることに疑問を感じ、「もっと健康的に働ける仕事があるのではないか」と考えるようになります。



メンタルヘルスが悪化すると、燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥ってしまうケースも見られます。
プライベートや家庭との両立困難
不規則な勤務時間は、友人や家族との時間を合わせにくく、プライベートな予定を立てづらいデメリットがあります。土日祝日が休みとは限らず、連休も取りにくい場合が多いでしょう。
結婚や出産、育児、介護といったライフイベントを迎えた際に、仕事との両立に悩む看護師も多くいます。子育て中の場合、夜勤への対応や急な子どもの病気への対応など、職場の理解やサポート体制が不可欠ですが、それが十分に得られない環境では、働き続けることが困難になります。「仕事のためにプライベートを犠牲にしすぎている」「家庭との両立ができない」と感じることが、「看護師に向いていない」という結論につながることがあります。
看護師に向いてない人の特徴5選
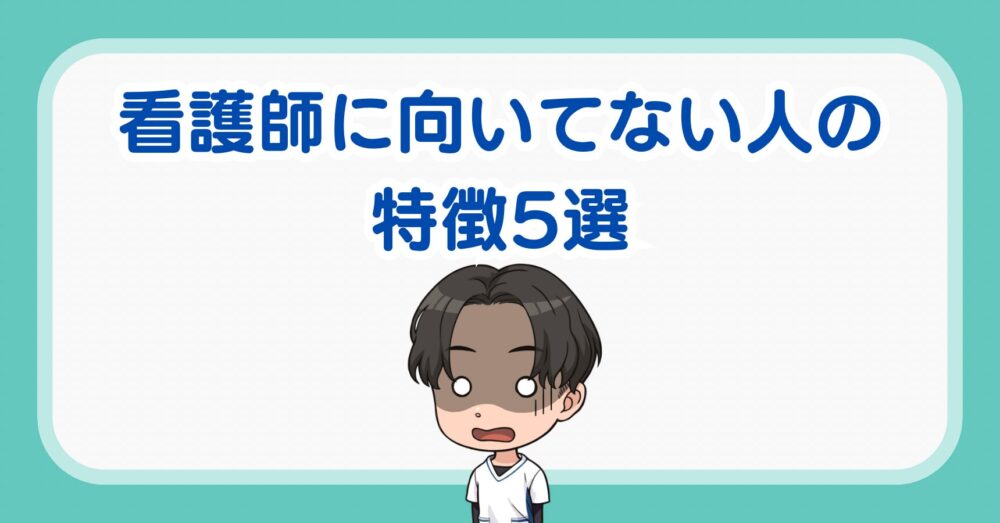
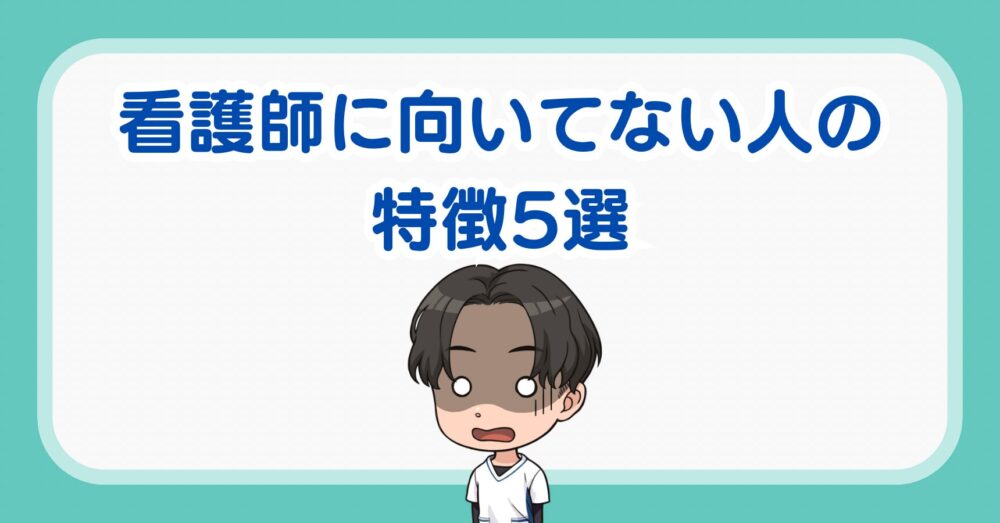
一般的に看護師に向いていないとされる人の5つの特徴を、それぞれの理由や具体的な場面とともに解説します。
»看護師は性格で向き不向きが決まる!現役主任がタイプ別に職場適正を診断
- 人と関わるのが苦手な人
- プレッシャーに弱い人
- 手先が不器用な人
- 汚物に抵抗がある人
- 気持ちの切り替えが苦手な人
人と関わるのが苦手な人
看護師の仕事は、患者やその家族はもちろん、医師、他の看護師、薬剤師、リハビリスタッフなど、非常に多くの人々と連携しながら進められます。そのため、円滑なコミュニケーション能力は不可欠です。
人と話すこと自体に強いストレスを感じたり、相手の気持ちを汲み取ったり、自分の考えを分かりやすく伝えたりすることが極端に苦手な場合、日々の業務で大きな困難を感じる可能性があります。
人との関わりで苦労する場面
- 患者さんへの対応
- 不安を抱える患者さんの話を丁寧に聞き、共感し、安心感を与えるような声かけや説明が求められます。コミュニケーションが苦手だと、患者さんとの信頼関係を築くのが難しくなることがあります。
- 家族への説明や対応
- 患者さんの状態や治療方針について、ご家族に分かりやすく説明し、質問に的確に答える必要があります。時には、デリケートな内容を伝えなければならない場面もあります。
- 他職種連携
- 医師への報告・連絡・相談(報連相)や、他の医療スタッフとの情報共有、カンファレンスでの意見交換など、チーム医療を円滑に進めるためのコミュニケーションが必須です。連携がうまくいかないと、患者さんに不利益が生じる可能性も否定できません。
- 申し送り
- 勤務交代時の申し送りでは、限られた時間の中で患者さんの情報を正確かつ簡潔に伝える能力が求められます。
もちろん、「内向的=コミュニケーションが苦手」というわけではありません。相手の話をじっくり聞ける、観察力が鋭いといった強みを持っている方もいます。しかし、チームで働くうえで必要な意思疎通や情報共有が困難だと感じるレベルであれば、看護師の仕事は精神的に大きな負担となる可能性があります。
プレッシャーに弱い人


看護師の仕事は、常に人の命に関わるという大きな責任が伴います。強いプレッシャーの中で冷静に判断し、的確に行動することが求められる場面が少なくありません。
以下のような状況で強いプレッシャーを感じ、それに押しつぶされそうになる方は、看護師の仕事がつらいと感じやすいでしょう。
- 人の命を預かる責任
- 自分の判断や行動が、患者の生命や健康に直結するという重圧は、看護師が常に感じているものです。特に新人時代や経験の浅い分野では、そのプレッシャーは大きくなります。
- 緊急時の対応
- 患者の容態が急変した場合など、迅速かつ的確な判断と処置が求められます。緊迫した状況下で冷静さを保ち、チームと連携して対応する必要があります。
- 多重課題への対応
- 複数の患者を受け持ち、様々な業務を同時並行でこなさなければならない場面が多くあります。優先順位を判断し、効率的に業務を進める能力が求められ、時間的なプレッシャーも大きいです。
- 医療ミスへの恐怖
- どれだけ注意していても、ヒューマンエラーのリスクはゼロではありません。インシデントやアクシデントを起こしてしまうことへの恐怖心は、常に付きまといます。
適度なプレッシャーは成長の糧にもなりますが、過度なプレッシャーによって精神的に追い詰められ、冷静な判断ができなくなったり、心身の不調をきたしたりするようであれば、働き方や環境を見直す必要があるかもしれません。



ストレスへの対処法を身につけることも重要ですが、プレッシャーに極端に弱い人は、精神的な負担の少ない働き方も選択肢の一つです。
手先が不器用な人
看護師の業務には、細かい手技が求められる場面が多いです。採血や注射、点滴のルート確保、創傷処置、医療機器の操作など、正確かつスムーズな手技は、患者の安全と安楽に直結します。
練習や経験によって上達する部分も大きいですが、もともと手先を使う作業が極端に苦手な場合、以下のような点で苦労する可能性があります。
- 患者への苦痛
- 採血や注射がスムーズにいかないと、患者に何度も針を刺すことになり、余計な苦痛を与えてしまいます。
- 医療安全上のリスク
- 点滴の接続ミスや医療機器の操作ミスは、重大な医療事故につながる可能性があります。
- 業務効率の低下
- 手技に時間がかかりすぎると、他の業務を圧迫し、時間内に仕事が終わらない原因にもなり得ます。
- 自己効力感の低下
- 何度練習してもなかなか上達しない、同期はできているのに自分だけできない、といった状況が続くと、自信を失い、仕事への意欲が低下してしまうこともあります。
手先の器用さに自信がない場合は、練習を重ねることはもちろんですが、比較的細かい手技が少ないとされる職場(例えば、精神科や健診センター、保育園など)を検討することも一つの方法です。



経験で上達することもありますが、採血などはセンスも大切です。どうしても苦手な手技がある場合は、割り切ることも必要です。
汚物に抵抗がある人
看護師の仕事は、血液、体液、排泄物、吐瀉物など、一般的に「汚物」と呼ばれるものに触れる機会は避けられません。これらは患者の健康状態を知るための重要な情報源であり、ケアを行う上で日常的に関わるものです。
清潔・不潔の概念を理解し、感染対策を徹底することは当然ですが、生理的に汚物への嫌悪感や抵抗感が極端に強い場合、看護師の業務を続けることが精神的に非常につらくなる可能性があります。
- 排泄ケア
- おむつ交換、陰部洗浄、ポータブルトイレの処理、ストーマケアなど、排泄物の処理は日常的な業務です。
- 清潔ケア
- 全身清拭や入浴介助では、汗や垢、皮膚からの浸出液などに触れます。
- 吸引
- 口腔内や気管内の痰を吸引する処置も頻繁に行います。
- 創傷処置
- 傷口からの血液や浸出液の処理を行います。
- 嘔吐物の処理
- 患者さんが嘔吐した場合の処理やケアも必要です。
- 検査補助
- 採血や検尿・検便などの検体採取や取り扱いも行います。
これらの業務に対して強い嫌悪感を抱いてしまうと、患者に必要なケアを提供すること自体が困難になったり、精神的なストレスが蓄積したりする可能性があります。



無意識に避けようとすることで、感染対策がおろそかになるリスクも考えられます。
「仕事だから」と割り切ることも大切ですが、どうしても生理的な嫌悪感が拭えない場合は、看護師としての働き方を見直す必要があるかもしれません。
気持ちの切り替えが苦手な人
看護師は、患者の喜びや回復に立ち会える一方で、苦痛、悲しみ、そして「死」といった非常に重い現実に日々向き合わなければなりません。また、患者やご家族からのクレーム、多忙な業務、複雑な人間関係など、様々なストレスにさらされる「感情労働」としての側面も持っています。
こうした状況の中で、自分の感情をコントロールし、仕事とプライベートのオンオフをうまく切り替えることが苦手な人は、精神的に消耗しやすい傾向があります。
- 感情移入しすぎる
- 患者の苦しみや悲しみに深く共感しすぎて、自分のことのように辛くなってしまう。
- ネガティブな感情を引きづる
- 仕事であった嫌なこと(患者の死、クレーム、同僚との衝突など)を家に帰ってもずっと考えてしまい、気分が落ち込んだままになる。
- 共感疲労
- 他者の感情に寄り添い続けることで、精神的なエネルギーが枯渇し、無気力になったり、逆に感情が鈍くなったりする。
- バーンアウト(燃え尽き症候群)
- 過度なストレスや感情的な負担が長期間続くことで、心身ともに疲れ果て、仕事への意欲や関心を失ってしまう。
患者さんに寄り添う気持ちは非常に大切ですが、プロフェッショナルとしてある程度の距離感を保ち、適切に処理していくスキルも求められます。



辛い出来事があっても、それを引きずりすぎずに気持ちをリセットし、次の業務や患者に向き合う力が必要です。
セルフケアの方法を身につけたり、信頼できる人に相談したりすることも有効ですが、どうしても気持ちの切り替えがうまくいかず、常に精神的な負担が大きいと感じる場合は、より感情的な負荷の少ない働き方や職場環境を検討することも大切です。
看護師に向いてないと感じたときの対処法
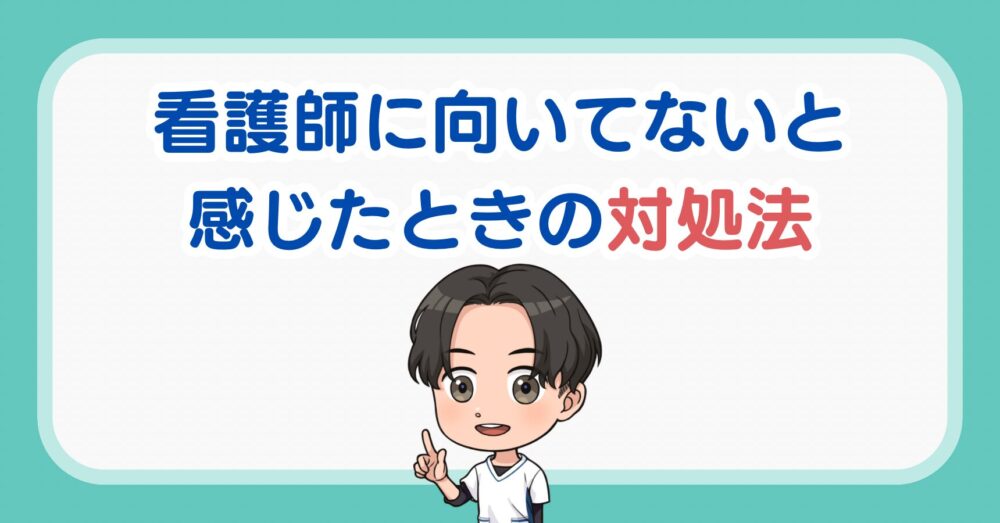
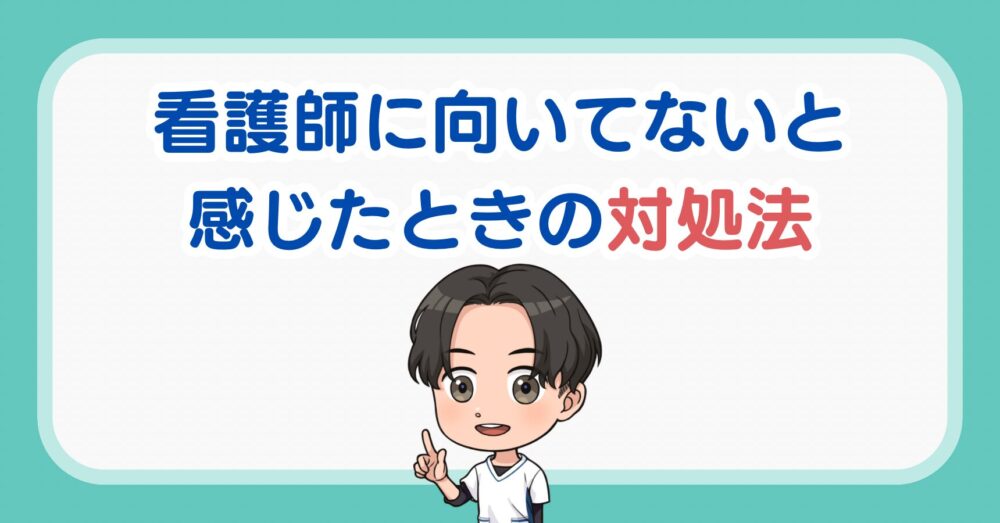
看護師に向いてないと感じたときに、どのように考え行動すれば良いのか、私が実践した具体的なステップを5つ紹介します。
- 自分の気持ちを整理する
- 同僚や上司に相談する
- 院内で異動を検討する
- 休暇を取ってリフレッシュする
- 新しい職場への転職
自分の気持ちを整理する


まず大切なのは、なぜ「向いてない」と感じるのか、その原因を具体的に探ることです。漠然とした不安や不満を抱えたままでは、適切な解決策を見つけることは困難です。以下の点を参考に、自分の気持ちと向き合ってみましょう。
- 何が「つらい」「嫌だ」と感じるのか具体的に書き出す
- スキル不足への焦り、特定の業務への苦手意識、人間関係の悩み、夜勤の負担、責任の重さなど、具体的な場面や感情をリストアップします。
- いつから、どんなきっかけでそう感じるようになったか振り返る
- 特定の出来事や環境の変化が影響している可能性もあります。
- 看護師になろうと思った理由や、仕事のやりがいを再確認する
- 初心に立ち返ることで、仕事へのモチベーションを取り戻せることもあります。
- 感情と事実を分けて考える
- 「つらい」という感情だけでなく、「何が原因でつらいのか」という事実を客観的に分析します。
»看護師のやりがいとは?現役看護師が本音で語る仕事の魅力と職場別の違い



ノートに書き出したり、マインドマップを活用したりするのも有効です。
信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが整理されることがあります。
同僚や上司に相談する
一人で抱え込まず、身近な人に相談することも重要です。特に、同じ職場で働く同僚や先輩、上司は、あなたの状況を理解しやすく、具体的なアドバイスをくれる可能性があります。
- 信頼できる同僚や先輩に相談する
- 同じような悩みを経験したことがあるかもしれません。共感を得られたり、具体的な乗り越え方を聞けたりすることで、気持ちが楽になることがあります。
- 直属の上司や看護師長に相談する
- 業務量の調整や部署異動など、具体的な解決策につながる可能性があります。相談する際は、感情的に訴えるだけでなく、「何に困っていて、どうしたいのか」を具体的に伝えることが大切です。
- 職場の相談窓口を利用する
- 病院によっては、メンタルヘルス相談窓口やハラスメント相談窓口などが設置されている場合があります。プライバシーに配慮された環境で、専門家(臨床心理士や産業カウンセラーなど)に相談できることもあります。
相談する相手を選ぶ際は、口が堅く、親身になって話を聞いてくれる人を選びましょう。相談することで、問題解決の糸口が見つかるだけでなく、精神的な支えを得られることも少なくありません。



私は職場の動機や看護学校時代の仲間に相談しています。
院内で異動を検討する
現在の部署や病棟の環境が、どうしても自分に合わないと感じる場合、院内異動も有効な選択肢の一つです。看護師の働く場所は多岐にわたります。同じ病院内でも、部署が変われば業務内容や人間関係、求められるスキルも大きく異なります。
異動先の例
- 急性期病棟から慢性期病棟へ
- 緊急対応のプレッシャーから解放され、患者とじっくり向き合える環境を求める場合に。
- 病棟から外来へ
- 夜勤がなくなり、比較的規則的な生活リズムで働きたい場合に。
- 病棟から手術室やICUへ
- 高度な専門知識や技術を身につけたい、チーム医療の中心で働きたい場合に。
- その他
- 訪問看護ステーション(病院併設の場合)、健診センター、透析室、内視鏡室など、専門性を活かせる部署も検討できます。
異動にはメリットとデメリットがあります。以下の表を参考に、自分にとって最適な選択か考えてみましょう。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 環境 | 業務内容や人間関係が変わり、心機一転できる可能性がある。 | 新しい環境や業務に慣れるまで時間と努力が必要。 |
| スキル | 新しい知識や技術を習得できる。キャリアの幅が広がる。 | これまでの経験が活かせない場合がある。一から学び直す必要がある。 |
| 人間関係 | 苦手な人との関わりが減る可能性がある。 | 新しい部署の人間関係が良好とは限らない。 |
| 実現性 | 転職よりはハードルが低い場合がある。 | 希望通りの部署に異動できるとは限らない。人員状況や適性による。 |
異動を希望する場合は、まず上司(看護師長など)に相談し、異動願の提出方法や時期、異動先の希望などを伝える必要があります。異動理由を明確に説明できるように準備しておきましょう。



私は立ちっぱなしの手術室が苦手で、アクティブに動ける病棟勤務が良いと常々上司に漏らしていました。あるタイミングで実際に病棟へ異動となった際は嬉しかったです。
休暇を取ってリフレッシュする
心身の疲労が蓄積し、「燃え尽き症候群(バーンアウト)」に近い状態になっていると、「向いてない」と感じやすくなります。一度仕事から離れて、心と体を休ませることも非常に重要です。
リフレッシュの方法
- 有給休暇を取得する
- まとまった休みが取れなくても、1日でも休暇を取って休息するだけでも効果があります。
- 長期休暇を活用する
- まとまった休みが取れなくても、1日でも休暇を取って休息するだけでも効果があります。
- 休暇中の過ごし方を工夫する
- 旅行に行く、趣味に没頭する、好きなことをして過ごす、あるいは простоゆっくり休むなど、自分が最もリラックスできる方法を選びましょう。
- 休職を検討する
- 心身の不調が深刻な場合は、医師の診断書を取得して休職することも選択肢の一つです。休職期間中にしっかりと療養し、今後のキャリアについてじっくり考える時間を持つことができます。傷病手当金などの制度についても確認しておきましょう。
リフレッシュすることで、視野が広がり、客観的に自分の状況を見つめ直すことができます。疲れた状態では正しい判断が難しくなるため、意識的に休息を取り、エネルギーを回復させることが大切です。
新しい職場への転職
様々な対処法を試しても状況が改善しない場合や、現在の職場環境や働き方そのものが自分に合わないと感じる場合は、転職やキャリアチェンジを視野に入れることも必要です。
≫看護師資格が使える珍しい求人10選!筆者も経験した好条件の職場も紹介
看護師資格を活かせる病院以外の職場
- クリニック・診療所
- 介護施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)
- 訪問看護ステーション
- 健診センター・人間ドック
- 保育園・幼稚園
- 企業(産業看護師)
- コールセンター(メディカルコールセンター)
多様な働き方
雇用形態を変えることで、働きやすさが改善されることもあります。
- 非常勤(パート・アルバイト)
- 派遣看護師
- 単発・スポット
転職活動の進め方
転職を決意したら、計画的に進めることが大切です。
- 自己分析とキャリアプランニング
- なぜ転職したいのか、どんな働き方をしたいのか、将来どうなりたいのかを明確にする。
- 情報収集
- 求人サイト、転職エージェント、ハローワーク、日本看護協会の運営する「eナースセンター」などを活用し、希望条件に合う求人を探す。
- 応募・選考
- 履歴書・職務経歴書を作成し、応募する。面接対策も行う。
- 内定・退職準備
- 条件を確認し、内定承諾。現在の職場への退職交渉を進める。
看護師専門の転職エージェントを利用すると、非公開求人の紹介や、履歴書添削、面接対策、条件交渉などのサポートを受けられる場合があります。自分に合った方法で情報収集を進めましょう。



最終的には、看護師以外の職種へのキャリアチェンジも選択肢の一つです。
看護師が自分に向いてる職場を見つけるコツ
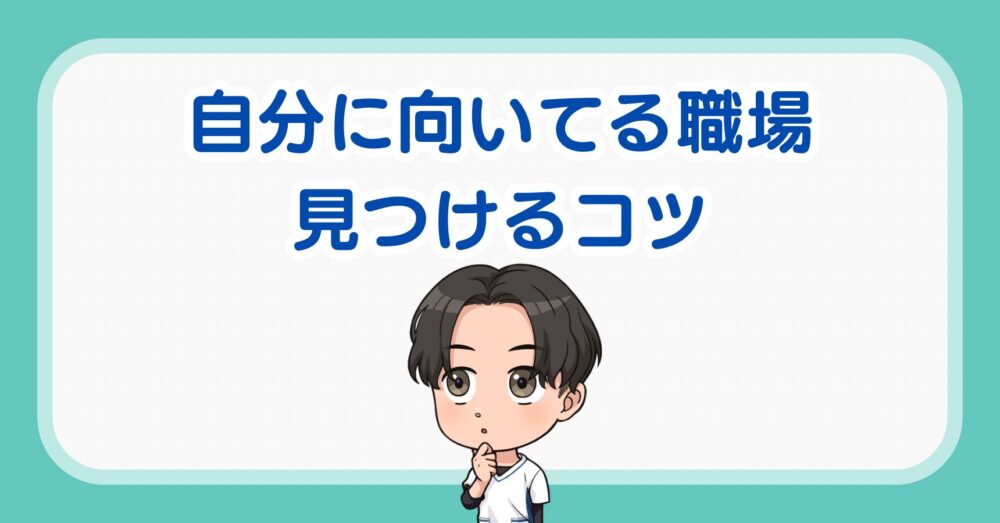
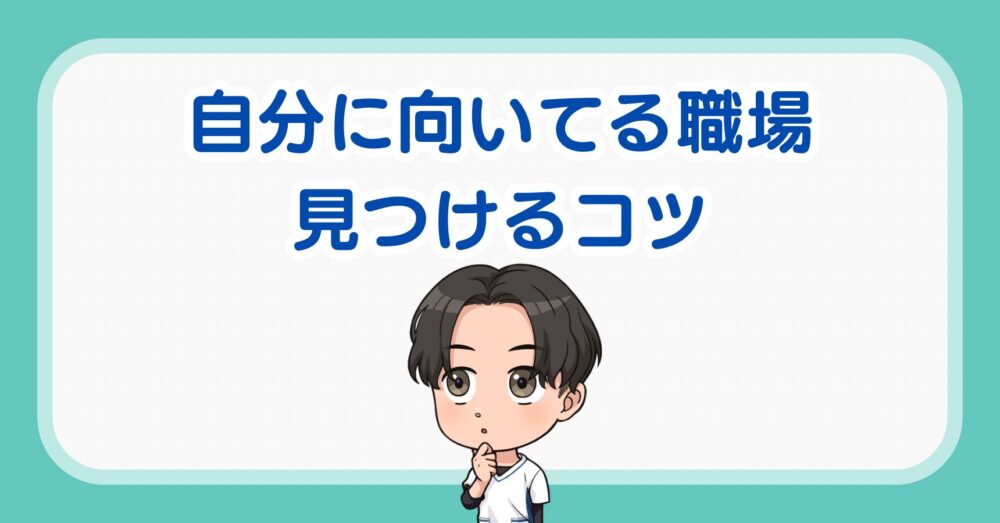
「看護師に向いてないかも…」と感じても、それは特定の職場や働き方が合わないだけで、看護師という仕事自体が完全に不向きとは限りません。ここでは、自分に合った職場を見つけるための具体的なコツをご紹介します。
- プライベートを重視できる職場を探す
- 一人ひとりに向き合える環境を選ぶ
- スキルアップが見込める職場を探す
- 自分の専門性や経験を活かせる場所を見つける
プライベートを重視できる職場を探す
「仕事とプライベートのバランスを取りたい」「時間に追われるのではなく、心にゆとりを持って働きたい」と感じる方は、ワークライフバランスを重視できる職場を探すのがおすすめです。急性期病院のような忙しさとは異なる働き方ができる場所はたくさんあります。
代表的な職場例と働き方
以下のような職場では、比較的規則的な勤務時間で、残業が少なかったり、夜勤がなかったりするケースが多く見られます。
| 職場例 | 主な特徴 | 働き方のポイント |
|---|---|---|
| クリニック・診療所 | 外来診療が中心。入院施設がない場合、夜勤なし。 | 日勤のみ、日曜・祝日休みが多い。地域密着型で患者さんと長く関われることも。 |
| 健診センター・人間ドック | 健康診断や人間ドックの実施。予防医療が中心。 | 日勤のみ、残業少なめ。採血や測定などの手技が中心。 |
| 保育園・幼稚園 | 園児の健康管理、怪我や病気の対応、保健指導。 | 日勤のみ、土日祝休みが多い。子ども好きには魅力的。 |
| 企業(産業看護師・ヘルスキーパー) | 従業員の健康管理、健康相談、メンタルヘルスケア。 | 日勤のみ、土日祝休みが多い。デスクワークや面談が中心。福利厚生が充実している場合も。 |
| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰を目指す高齢者のリハビリや医療ケア。 | 夜勤がある場合もあるが、病院に比べると医療処置は少ない傾向。比較的落ち着いた環境。 |
求人情報をチェックする際のポイント
- 勤務時間・休日
- 「日勤のみ」「完全週休2日制」「年間休日120日以上」などの記載を確認しましょう。
- 残業時間
- 「残業月平均〇時間」「残業ほぼなし」といった具体的な情報を確認します。面接時に実態を聞くことも重要です。
- 有給休暇消化率
- 休暇が実際に取得しやすい環境かどうかの指標になります。
- 福利厚生
- 住宅手当や託児所の有無など、プライベートを支える制度も確認しましょう。
厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」なども参考に、自分に合った働き方ができる職場を探してみてください。
一人ひとりに向き合える環境を選ぶ
「忙しすぎて患者さんとゆっくり話せない」「もっと一人ひとりの気持ちに寄り添ったケアがしたい」と感じる方は、患者や利用者とじっくり関われる環境を選ぶと、やりがいを感じられるかもしれません。大規模病院のスピード感とは異なる、丁寧な関わりが求められる職場があります。
代表的な職場例と特徴
以下のような職場では、比較的時間をかけてケアを提供できる傾向があります。
| 職場例 | 主な特徴 | 求められるスキル・やりがい |
|---|---|---|
| 訪問看護ステーション | 利用者の自宅を訪問し、療養生活を支援。医療処置から家族ケアまで幅広い。 | 個別性の高いケアの実践。利用者や家族との信頼関係構築。コミュニケーション能力、アセスメント能力。 |
| 療養型病院・病棟 | 長期的な医療・療養が必要な患者さんが入院。 | 状態が安定している患者さんが多く、比較的落ち着いた環境でじっくり関われる。日常生活援助が中心。 |
| 介護施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど) | 高齢者の生活支援と健康管理が中心。 | 利用者の生活に寄り添ったケア。多職種連携。看取りケアに関わることも。 |
| 精神科病院・病棟 | 精神疾患を持つ患者さんのケア。 | コミュニケーションを通じた信頼関係構築が重要。心理的なサポート、社会復帰支援。 |
| 緩和ケア病棟・ホスピス | 終末期の患者さんの苦痛緩和とQOL向上を目指すケア。 | 患者さんや家族の心に寄り添うケア。高いコミュニケーション能力、精神的サポート力。 |
職場選びのポイント
- 看護体制
- 患者一人あたりに対する看護師の配置人数を確認しましょう。手厚い配置であれば、より丁寧な関わりが期待できます。
- 施設の方針・理念
- どのようなケアを大切にしているか、共感できるかどうかを確認しましょう。
- 教育・研修
- 未経験の分野(例: 訪問看護)に挑戦する場合、研修制度が充実しているか確認すると安心です。
- 多職種連携:
- 医師、リハビリスタッフ、介護士、ケアマネージャーなど、他職種とどのように連携しているかを確認しましょう。チームでケアを提供する体制が整っているかが重要です。
スキルアップが見込める職場を探す
「今の職場では物足りない」「もっと専門的な知識や技術を身につけたい」という向上心のある方は、スキルアップやキャリアアップが可能な環境を選ぶことがモチベーション維持につながります。教育制度や資格取得支援が充実している職場を探しましょう。
スキルアップに適した職場例
- 大学病院・教育機関附属病院
- 最新医療に触れる機会が多く、研究や教育にも力を入れている。研修プログラムが体系化されていることが多い。
- 専門病院・センター
- 特定の疾患領域(がん、循環器、脳神経など)に特化しており、深い専門知識・技術を習得できる。
- 教育制度が充実した中核病院
- クリニカルラダー制度やプリセプターシップがしっかり機能しており、段階的にスキルアップできる。院内研修や勉強会が活発。
- 資格取得支援制度のある施設
- 認定看護師や専門看護師などの資格取得を目指す場合に、費用補助や研修期間の勤務配慮などがある。
確認すべきポイント
- 教育プログラムの内容
- 新人教育だけでなく、中堅やベテラン向けの研修、専門分野別の研修などが用意されているか。
- キャリアラダー制度
- 目標設定や評価に基づき、段階的にキャリアアップできる仕組みがあるか。
- 資格取得支援の実績
- 実際に制度を利用して資格を取得した看護師がいるか、どのようなサポートを受けられるか具体的に確認する。
- 院内・院外研修への参加機会
- 学会発表や外部研修への参加が奨励されているか、費用補助などがあるか。



日本看護協会では、認定看護師や専門看護師などの資格認定制度を設けています。キャリアアップに関心のある方は、「日本看護協会 資格認定制度」のページも参考にしてみてください。
自分の専門性や経験を活かせる場所を見つける
これまでの看護師経験で培ってきた特定のスキルや知識、あるいは看護師資格そのものを活かして、病院以外のフィールドで活躍することも可能です。「臨床現場のプレッシャーから離れたい」「違った形で医療や健康に関わりたい」と考える方は、多様な選択肢を検討してみましょう。
専門性や経験を活かせる職場例
| 職場例 | 主な業務内容 | 活かせる経験・スキル |
|---|---|---|
| 専門クリニック(不妊治療、美容外科など) | 特定の分野に特化した看護ケア、カウンセリング。 | 関連分野での臨床経験、高いコミュニケーション能力、専門知識。 |
| 企業(治験コーディネーター CRC) | 新薬開発の臨床試験(治験)のサポート、被験者ケア、データ管理。 | 臨床経験、コミュニケーション能力、調整力、PCスキル。 |
| 企業(クリニカルスペシャリスト) | 医療機器メーカーなどで、自社製品の医療従事者への説明・デモンストレーション。 | 特定の医療機器の使用経験、専門知識、プレゼンテーション能力。 |
| 行政機関(保健師) | 地域住民の健康相談、健康増進活動、母子保健、感染症対策など。(別途、保健師資格が必要) | 看護師経験、公衆衛生に関する知識、コミュニケーション能力。 |
| コールセンター(医療系) | 患者さんや家族からの電話相談対応、健康相談。 | 幅広い臨床知識、コミュニケーション能力、傾聴力。 |
| 看護系教育機関 | 看護学生への指導、講義、実習指導。(教員要件を満たす必要あり) | 豊富な臨床経験、指導力、専門知識。 |
キャリアチェンジを考える際のポイント
- 自分の強み・興味の明確化
- これまでの経験で何を得意とし、何に関心があるのかを整理しましょう。
- 必要な資格・スキルの確認
- 転職先によっては、特定の資格(保健師、助産師など)やPCスキル、語学力が求められる場合があります。
- 情報収集
- 転職エージェントや求人サイト、各業界団体のウェブサイトなどを活用し、具体的な仕事内容や待遇、求められる人物像を調べましょう。
- 未経験分野への挑戦
- 未経験でも応募可能な求人もあります。研修制度の有無やサポート体制を確認することが大切です。
看護師の資格や経験は、臨床現場以外でも多様な分野で求められています。固定観念にとらわれず、幅広い選択肢の中から自分に合ったキャリアパスを探してみましょう。
まとめ
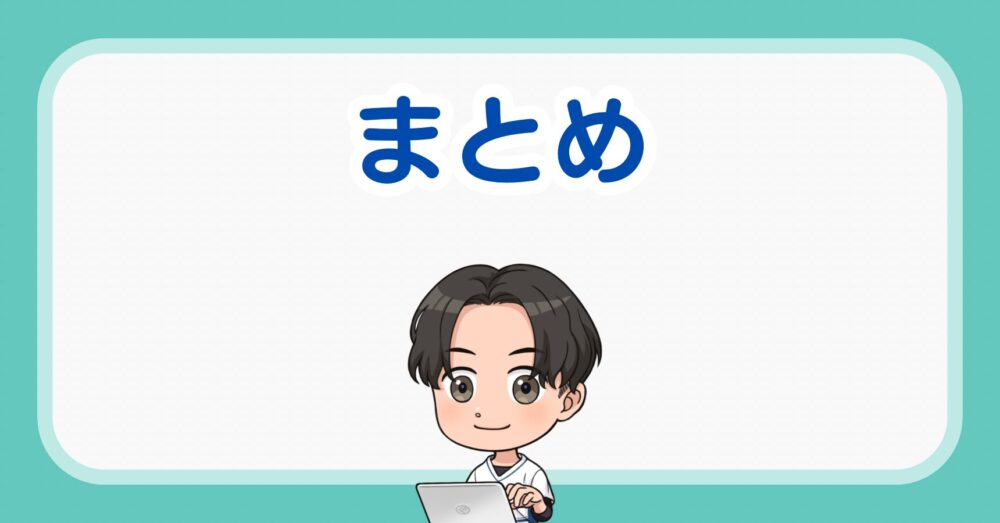
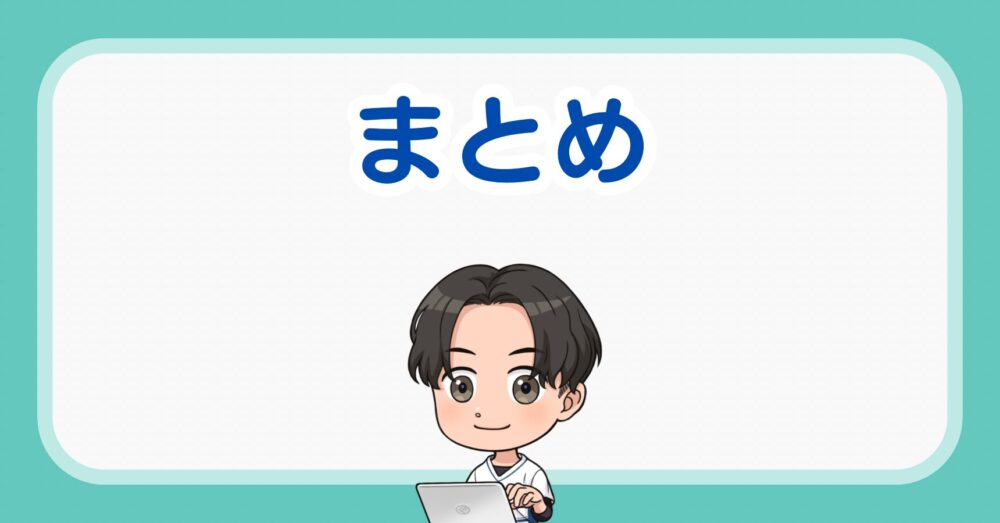
看護師に向いていないと感じる背景には、スキル不足への不安、命を預かる責任の重さ、職場の人間関係、ワークライフバランスの問題などがあります。特に、コミュニケーションが苦手、プレッシャーに弱い、手先が不器用、汚物への抵抗感、気持ちの切り替えが難しいといった特徴があると、辛さを感じやすいかもしれません。
しかし、すぐに諦める必要はありません。まずは自分の気持ちを整理し、同僚や上司への相談、異動、休暇取得といった対処法を試してみましょう。それでも難しい場合は、自分に合った職場環境を探すことが大切です。焦らず、あなたらしい働き方を見つける一歩を踏み出しましょう。
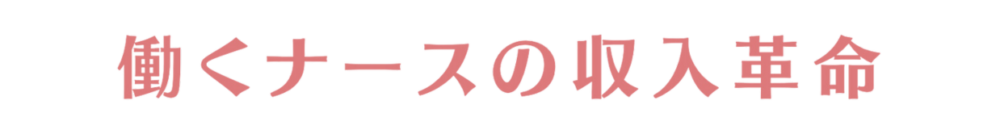
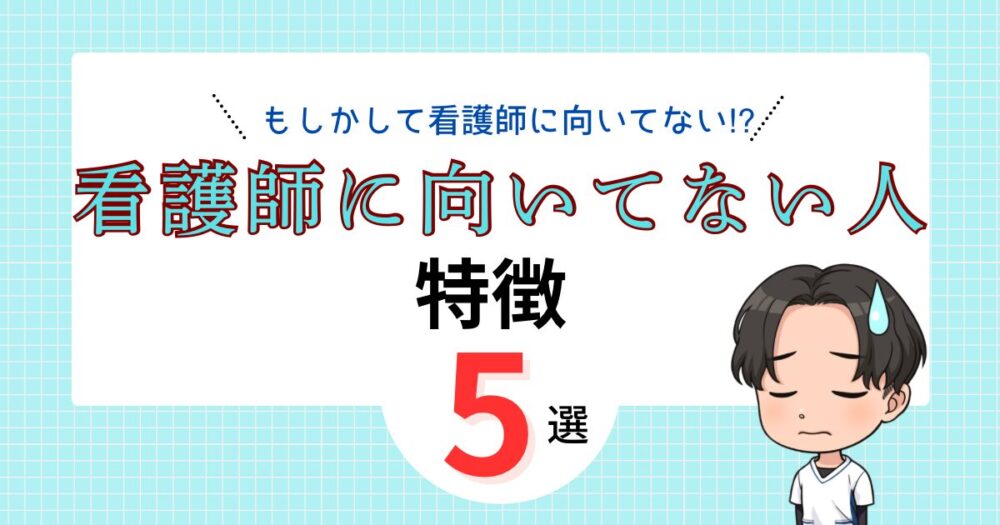

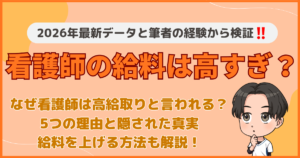
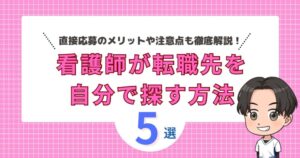
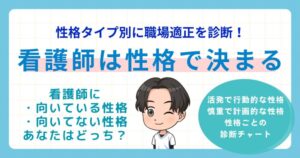

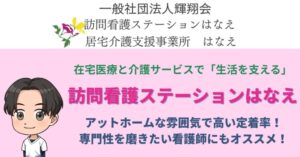
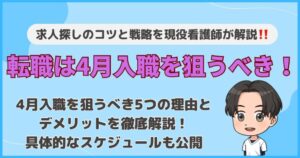
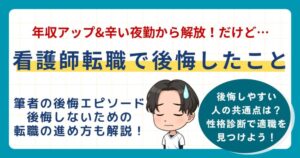
コメント